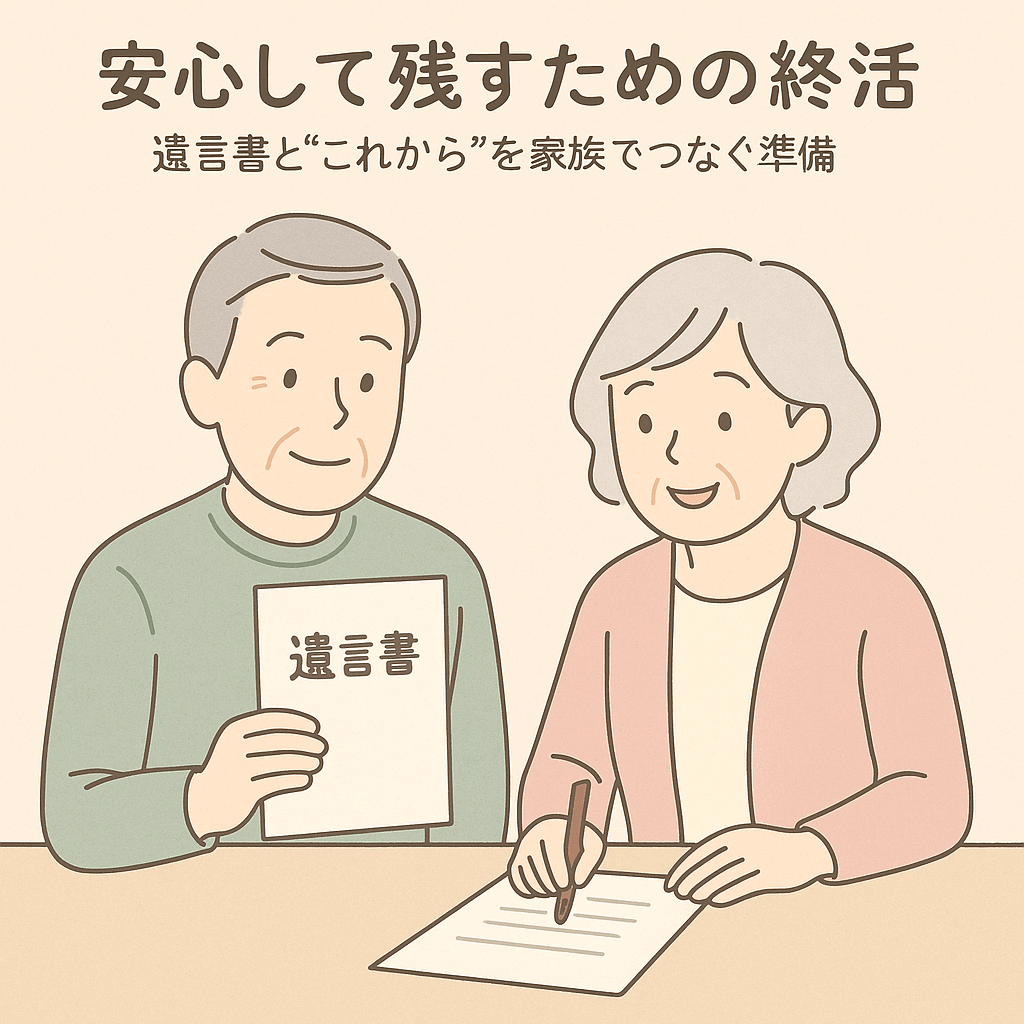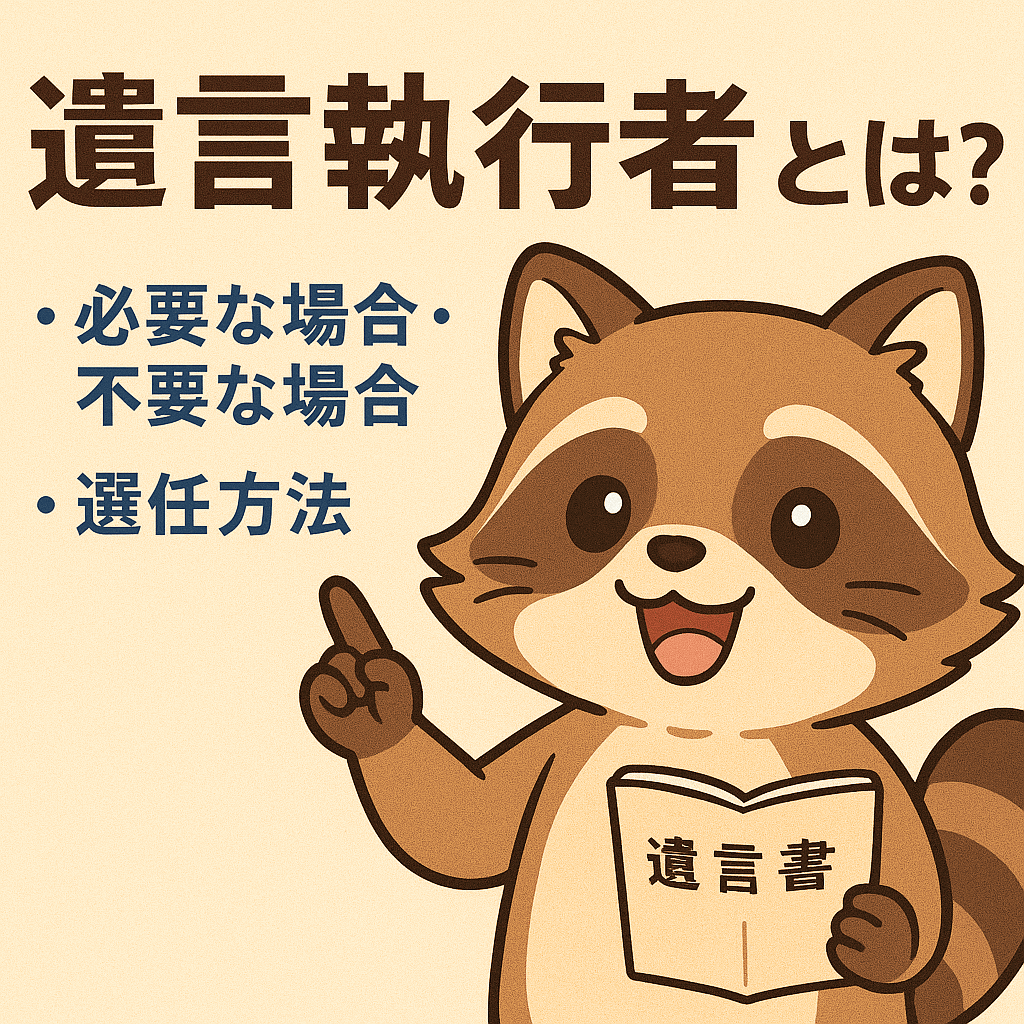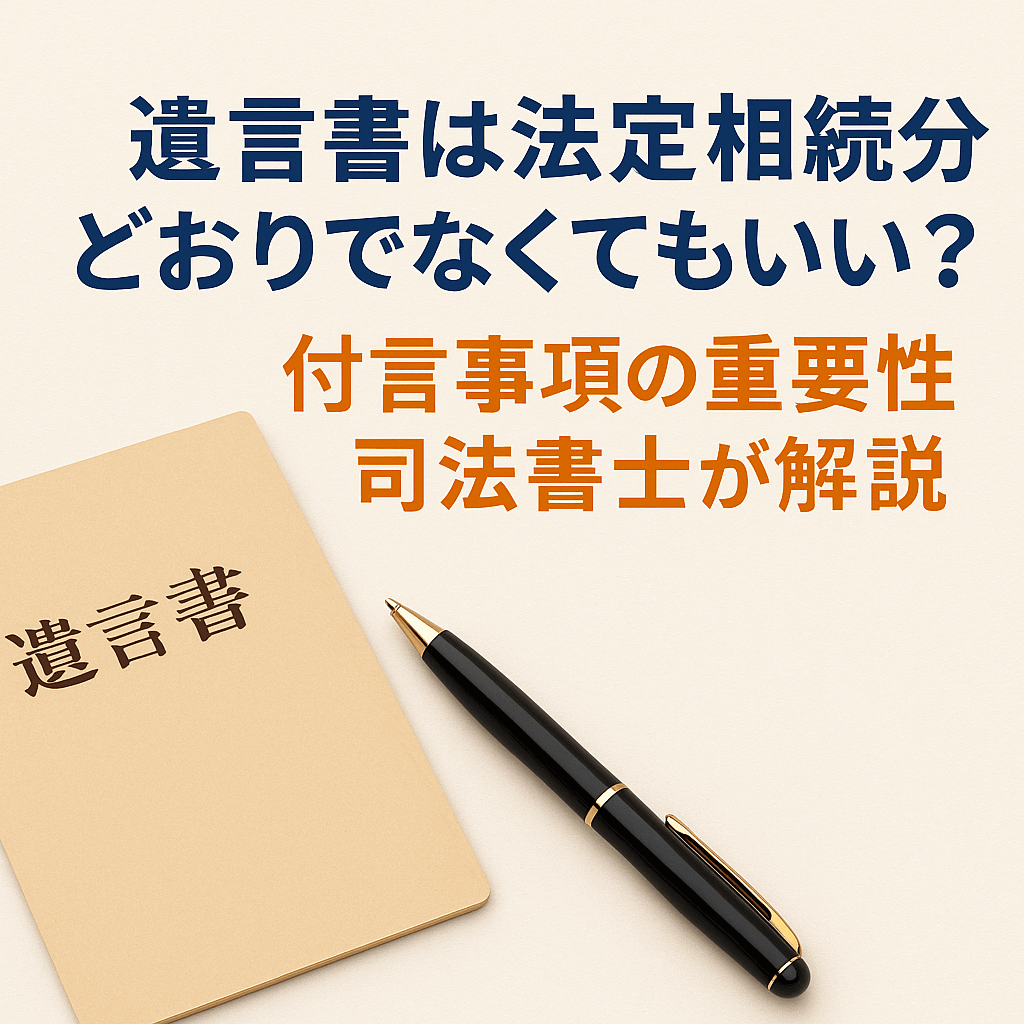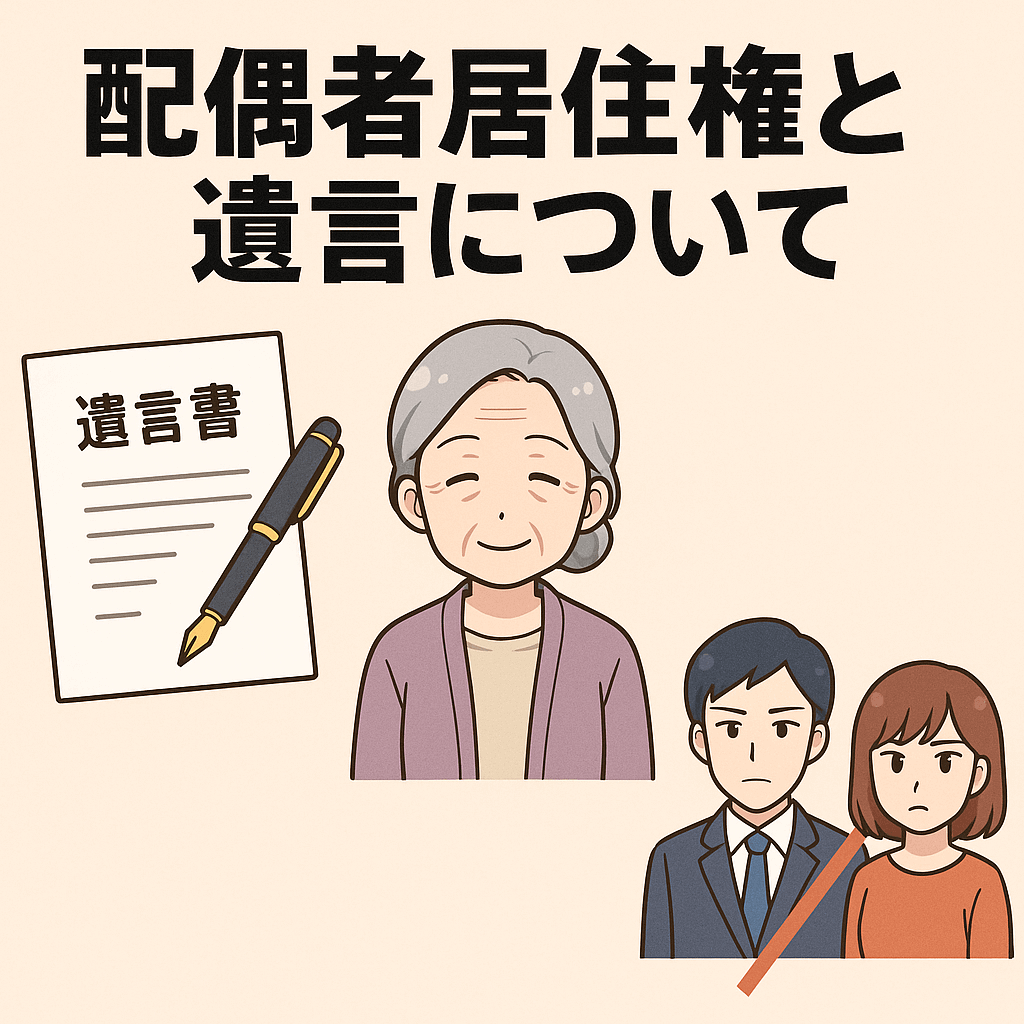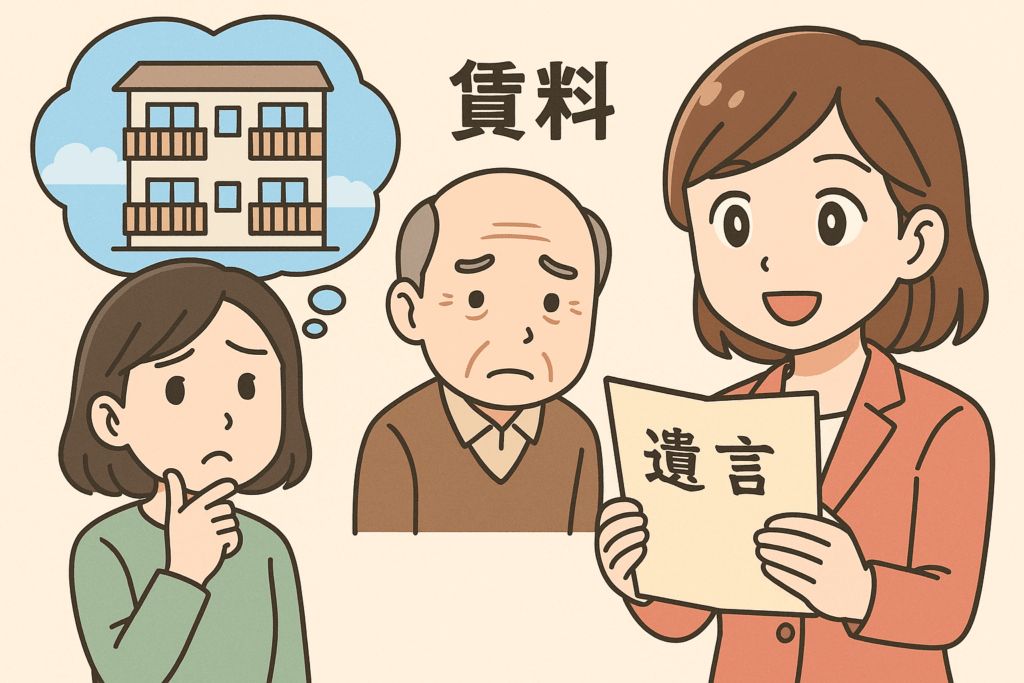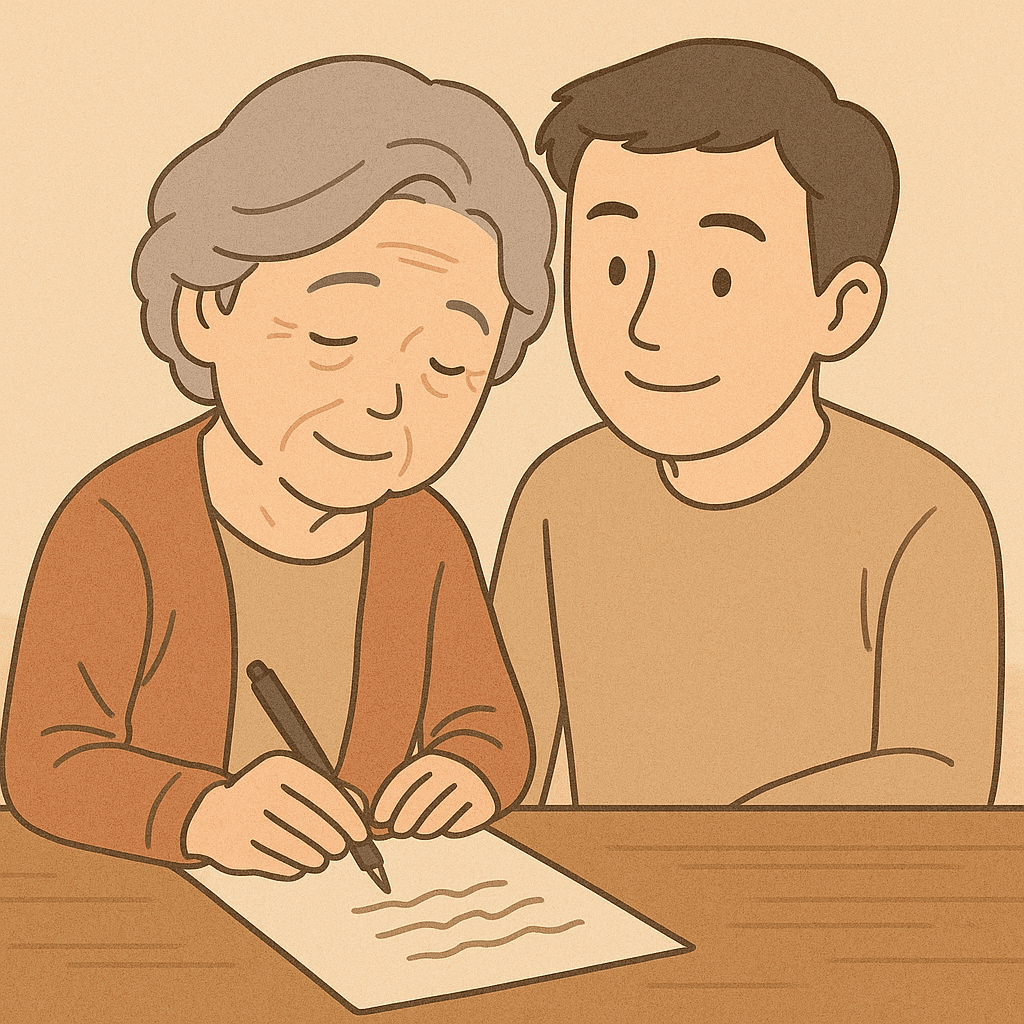東京都文京区湯島の司法書士行政書士の栗栖英俊です。
今回は、どのような内容の遺言書を作成すべきかという内容面について解説させていただきます。
まず、基本的な遺言書について、お伝えさせてください。

遺言書に記載できる事項について
遺言書には何でも記載すれば、効力を生じるというものではありません。
遺言は、遺言できると法律に限定列挙されていることについてしたものにだけ法的効力が認められます。
以下は、民法上に定められている事項です。
【① 相続外の事項に関する遺言】
※相続に直接関係しないが、遺言で定めることができる事項。
| 項目 | 民法条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 相続外の認知 | 民781条2項 | 非嫡出子を認知(父子関係の確定)できる。 |
| 未成年後見人の指定 | 民839条1項 | 未成年の子の親が死亡した後の後見人を指定できる。 |
| 未成年後見監督人の指定 | 民848条 | 後見人を監督する者を指定できる。 |
【② 相続に関する事項に関する遺言】
※被相続人の死亡によって生じる相続に関係する事項。
| 項目 | 民法条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 推定相続人の廃除・取消し | 民893条・894条2項 | 素行不良などの相続人の資格を奪う・回復する。 |
| 祭祀主宰者の指定 | 民897条1項 | 仏壇・墓などを管理する者を指定できる。 |
| 相続分の指定 | 民902条 | 各相続人の取り分を指定できる。 |
| 特別受益としない旨の意思表示 | 民903条3項 | 生前贈与などを「相続分の前渡し」とみなさないとする意思表示。 |
| 遺産分割方法の指定・禁止 | 民908条 | 財産の分け方を指定したり、一定期間分割を禁止できる。 |
| 遺産分割における担保責任 | 民914条 | 取得財産に瑕疵があった場合の責任に関する指定。 |
| 包括遺贈・特定遺贈 | 民964条 | 遺贈(遺言による贈与)を包括的または特定の財産について行う。 |
| 遺言執行者の指定 | 民1006条1項 | 遺言の内容を実現する人を指定する。 |
基本的な遺言書の文例
基本的な遺言書の文例を参考までに簡潔に作成しておきます。
第1条 遺言者の長女山田幸子(昭和46年3月30日生)に別紙1の土地建物を相続させる。
第2条 遺言者は、長男山本一郎(昭和43年10月4日生)に別紙2の建物を相続させる。
第3条 遺言者は、その他の財産を全部長女山田幸子に相続させる。
令和4年7月1日 遺言者 甲野太郎㊞

たすきがけ遺言(予備的遺言)の必要性について
遺言で「全財産をA(配偶者)に相続させる」としていても、もしA(配偶者)が先に亡くなってしまった場合、その遺言の効力は失われてしまいます。
せっかく遺言を残しても、意図したとおりに財産を引き継ぐことができなくなる可能性があるのです。
そこで安心なのが、「予備的遺言」という方法です。たとえば、「もしA(配偶者)が私より先に亡くなった場合は、Bに相続させる」といった形で記しておけば、A(配偶者)が先に亡くなった場合でも、遺言の内容が無効にならずに済みます。
この方法は、相続人が先に亡くなる場合だけでなく、相続放棄をする可能性がある場合にも有効です。大切な財産を希望する人に確実に引き継ぐために、予備的遺言を活用することをおすすめします。
予備的遺言の一例です。
第1条 遺言者は、その所有する不動産、預貯金、現金等を含む全ての財産を遺言者の妻A(昭和36年2月19日生)に相続させる。
第2条遺言者は、前記Aが遺言者の死亡以前に死亡したときは、前条に変えて前条記載の財産を、遺言者の弟B(昭和37年8月24日生、本籍 東京都)に相続させる。
事実婚カップルが遺言書を作成すべき理由と注意点
近年、事実婚を選ぶカップルが増えていますが、法律上の配偶者ではないため、相続権がありません。そのため、パートナーに財産を遺すためには、遺言書を作成することが不可欠です。
1. 遺言書を作成する重要性
事実婚のパートナーには法定相続権がなく、遺言書を作成しなければ、亡くなった後の財産はすべて法定相続人(子・親・兄弟姉妹)に引き継がれます。たとえ長年連れ添ったとしても、何も手続きをしていなければ、パートナーは一切の財産を相続できません。
特に次のようなケースでは、遺言書の有無が大きな影響を与えます。
✅ 自宅の名義がパートナーのものである場合
→ 遺言がなければ、法定相続人が相続し、住み続けられなくなる可能性があります。
✅ パートナーの預貯金を引き継ぎたい場合
→ 相続権がないため、遺言書がなければ一切受け取れません。
✅ 事業や資産を守りたい場合
→ 法定相続人が財産を相続すると、パートナーが経済的に困窮する可能性があります。
このような事態を避けるためにも、遺言書を作成し、パートナーへの「遺贈」を明確に指定しておくことが大切です。
2. 遺言書作成の注意点
「遺贈」の形にすること
事実婚のパートナーには相続権がないため、財産を承継させるには「遺贈」または「死因贈与契約」を活用する必要があります。特に、確実に財産を遺すには遺言書による遺贈が最も有効です。
必要な資料を準備すること
遺言による遺贈をスムーズに進めるためには、同一生計であったことを証明する資料を用意しておくことが重要です。例えば、以下の書類が必要になる可能性があります。
- 居住建物の賃貸借契約書(共同で居住していた証明)
- 生命保険の受取手続きのための資料(生計を共にしていた証明)
これらの書類がないと、パートナーとしての関係を証明できず、財産承継に支障が出ることがあります。
相続税の負担に注意
事実婚のパートナーは法定相続人ではありません。
この場合、法定相続人ではない第三者に対する遺贈では、その第三者に対する税金は贈与税ではなく相続税となります(相続税法1条の3)。
この場合、事実婚の配偶者には、本来の相続税額の2割が加算されることに注意が必要です。

事実婚の遺言書の文面の一例
第1条 遺言者は、遺言者が所有する下記の財産を乙山春子(昭和〇年〇月〇日生、住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)に遺贈する。
推定相続人がいない「おひとりさま」の遺言書作成
日本では、高齢化が進む中で推定相続人(法定相続人となる予定の人)がいない「おひとりさま」が増えています。こうした方こそ、遺言書の作成が非常に重要です。なぜなら、遺言がなければ、亡くなった後の財産が自分の望む形で使われない可能性があるからです。
遺言がない場合、財産はどうなる?
推定相続人がいない場合、遺産は以下の流れで処理されます。
- 特別縁故者への分与
生前に特に親しかった人(内縁の配偶者、長年世話をしてくれた友人など)が家庭裁判所に請求すれば、一部の財産を受け取れる可能性があります。
→ ただし、請求しなければ受け取れません。 - 最終的には国庫(国の財産)へ
特別縁故者の請求がない場合、または認められなかった場合、財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものになってしまいます。
遺言書があれば、自分の意志を反映できる
遺言書があれば、財産の行き先を自分で決めることができます。例えば、
- 長年お世話になった友人や支援してくれた人に遺贈する
- 応援したい団体(NPO法人や福祉施設)に寄付する
- お墓や供養に使う資金を確保する
このように、自分の大切な財産を「誰のために、どのように使うか」を指定できるのです。
さらに、遺言書で遺言執行者を指定しておけば、遺産の調査や債権者への弁済などの手続きを執行者に任せることができます。
推定相続人がいない方の場合、財産を受け取る人は「遺贈」によって取得するため、その手続きを行う遺言執行者の役割は不可欠といえます。
遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容が円滑に実現され、財産が適切に処理されることにつながります。
どんな遺言書を作ればいい?
推定相続人のいない方の場合、遺言書は特に公正証書遺言が安心です。公証役場で作成すれば、紛失や偽造の心配がなく、確実に内容が実行されます。
また、遺言執行者を指定しておくことで、財産の管理や分配がスムーズに行われるため、より確実な遺言の実現が可能です。