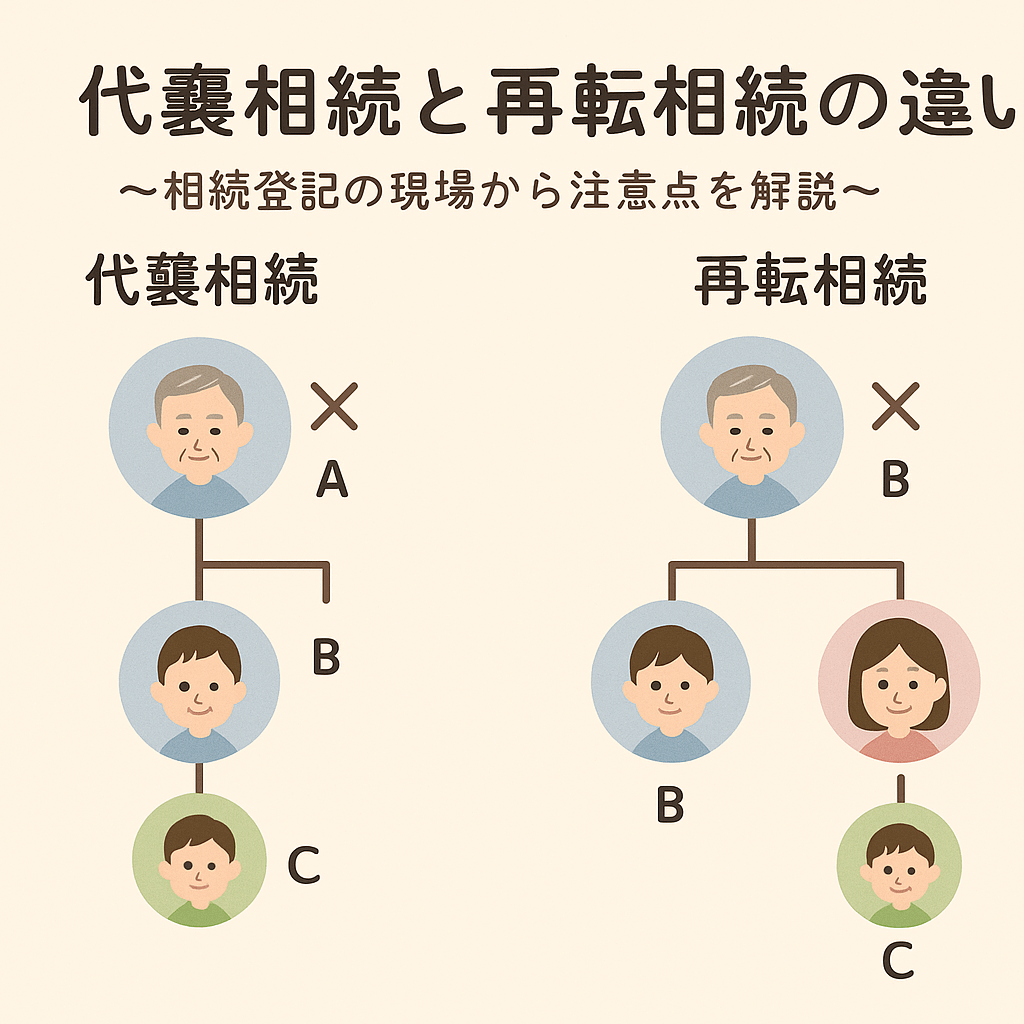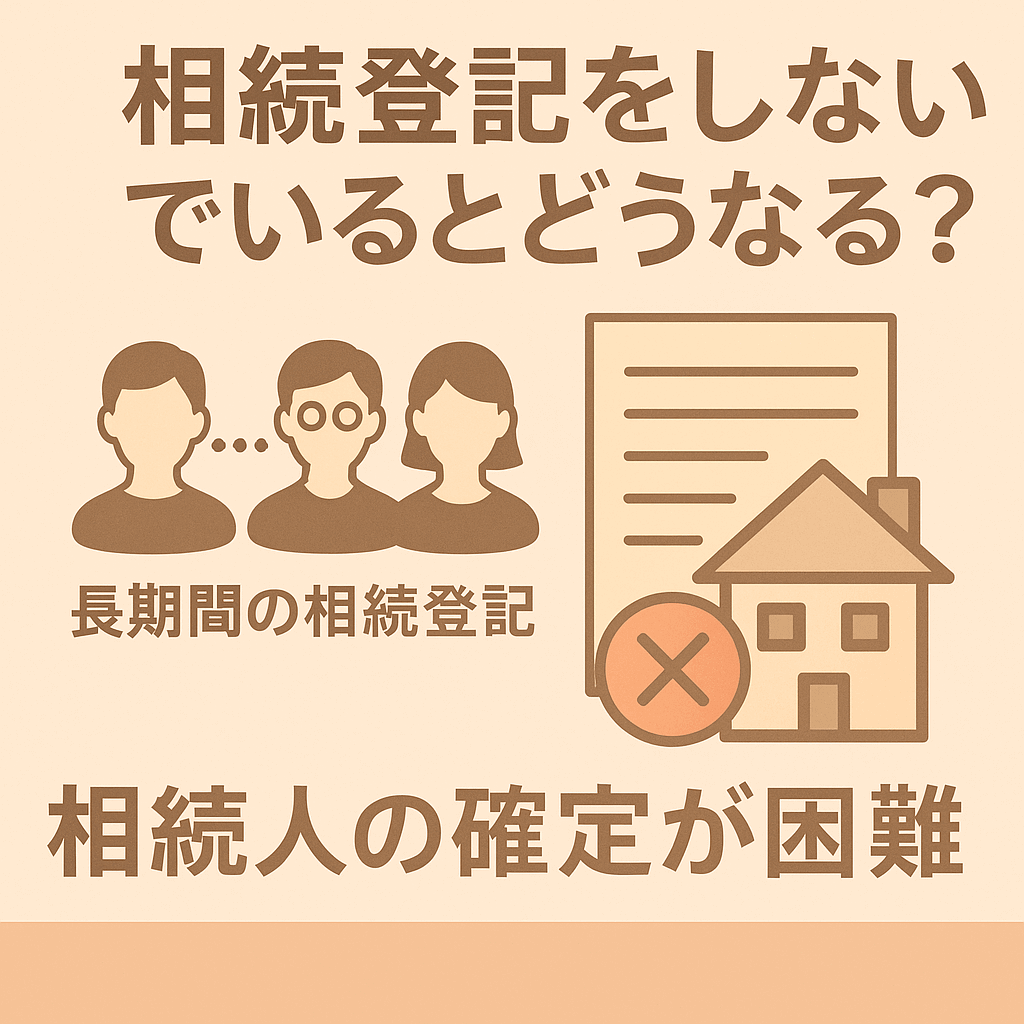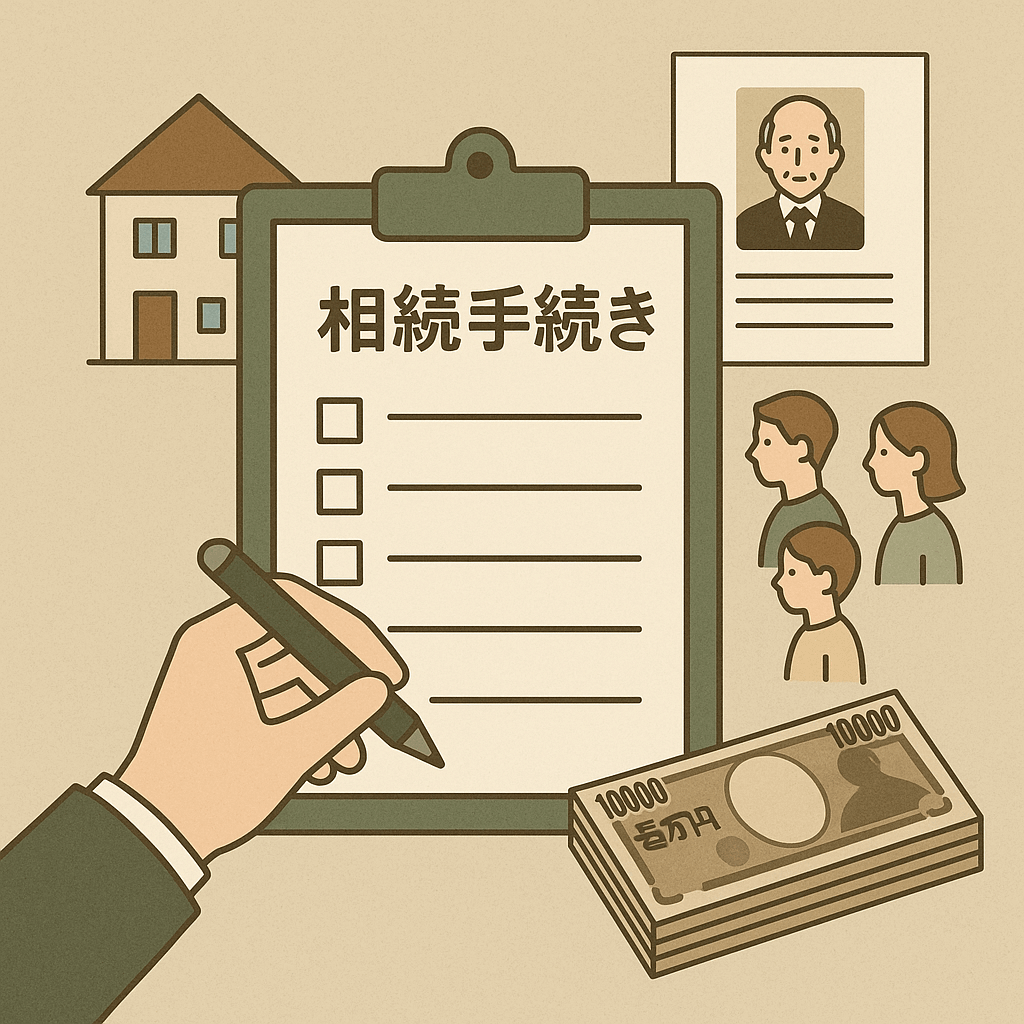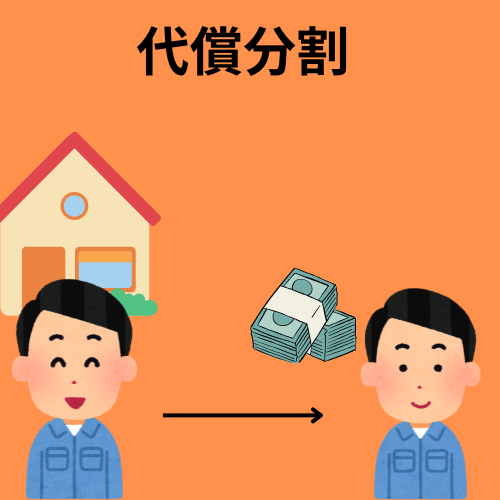文京区湯島の司法書士行政書士栗栖英俊です。
「親の介護をずっとしてきたのに、遺産は兄弟と均等に分けるの…?」「相続が発生したけれど、この遺産分けに納得がいかない…」
そんなふうに感じている方は、「寄与分(きよぶん)」という制度を知っておくことで、損を防げるかもしれません。
この記事では、寄与分について初心者にもわかりやすく解説します。
相続に関する疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 寄与分(きよぶん)とは?
寄与分の意義
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、その貢献度に応じて、他の相続人よりも多く財産を受け取ることができる制度です。
これは民法第904条の2に定められており、「公平な遺産分割」を実現するための大切な仕組みとなっています。
第904条の2【寄与分】
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4. 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
寄与分権者の範囲
被相続人の面倒を見たりすれば、誰でも寄与分権者になれるわけではありません。
寄与分権者は相続人に限定されます(民904条の2第1項)。
相続放棄者,相続欠格者,相続廃除者は寄与分権者たり得ず,内縁配偶者や事実上の養子等も寄与分権者になることは出来ません。
もっとも、相続法改正によって、「相続人ではない親族」については、特別寄与料を請求できる「特別寄与者」となりうるとされていることに注意が必要です。
第1050条
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2. どんな場合に寄与分が認められる?具体的な4つのタイプ
寄与分が認められるには、単なる援助や同居だけでなく、「特別な貢献」があったことが必要です。
以下にいくつかのタイプと具体例をご紹介します。
(1)療養看護型の寄与
親の介護を長期間、他の相続人に頼らずに無償で行っていたケース
具体例:
長女が仕事を辞めて、5年間にわたり自宅で父親を介護。介護保険だけでは足りない部分を補い、父親の健康状態改善にも寄与していた場合。
この場合は、単に同居しているだけというのではなく、被相続人に療養介護の必要性があったことなどが要件となります。
(2)家業従事型の寄与
家業や事業を長年無給で支え、発展に貢献したケース
具体例:
長男が大学卒業後から30年間、父親の工場で経理や営業を担当。新規取引先の開拓や経費削減に尽力し、他の兄弟は事業に関与していなかった。
この場合特別の寄与となるには、特別の貢献をしたことや無償性などが要求されますが、認められるのはなかなか難しい部分があります。
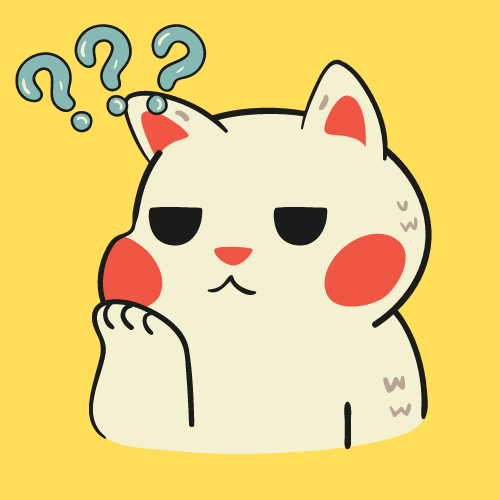
(3)金銭的援助型の寄与
多額の資金提供により、被相続人の生活や事業の維持に貢献したケース
具体例:
父親が事業に失敗し、多額の借金を抱えた際、次男が自分の貯蓄から500万円を支援し、事業の立て直しに成功した。
これは想像しやすいと思います。単に財産を給付するだけなので、継続して行うことなどの要件は必要とされていません。
(4)扶養型の寄与
通常の扶養義務を超える支援を行っていた場合に、例外的に認められることがあります。
注意点:
夫婦間の協力や子が親を扶養する義務の範囲内では、寄与分として認められないのが一般的です。
単に一度支援をしたというだけでは不十分で、毎月仕送りをしたとか、同居してい面倒を見ていたなどの要件が必要です。
当然ですが、被相続人が扶養を必要としていることも大事な要件です。
これ以外にも、被相続人の財産を管理して、財産の維持形成に寄与した場合などが、寄与分の認められるタイプとしてあげられます。
▼ 事例:遺産総額3,600万円、相続人3名(長男・長女・次男)
それでは、寄与分が認められた場合の相続分について、具体例で確認してみましょう。
- 通常の法定相続分 → 各1,200万円
- ただし、長女が5年間にわたり父親の介護を無償で行っており、寄与分600万円と認定された場合
再計算の流れ:
- 遺産全体に寄与分を差し引く→ 3,600万円-600万円(寄与分)=3,000万円
- 相続人3人で均等に割る → 3,000万円 ÷ 3人 = 1,000万円(理論的相続額)
- 長女の取り分:1,000万円+寄与分600万円=1,600万円
長男・次男:各1,000万円、長女1,600万円
寄与分が認められたことにより、長女の取り分が法定相続分より増加し、長男と次男の取り分が減少していることがわかると思います。
4. 寄与分を主張するには?必要な証拠や手続き
当事者間で寄与分について話がまとまらない場合の解決方法としては、調停と裁判所の審判による方法があります。
当事務所は司法書士行政書士事務所なので、ここでは概要を述べるだけにします。
調停申立の手続き
調停の場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に調停を申し立てることになります(家事事件手続法245条1項)。
この場合の申立人は、「寄与をした」相続人に限られます。
審判による方法
寄与分を定める審判は,相続に関する審判事件に属するため,被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所の管轄となります(家事事件手続法191条1項、2項)。
通常は、家事調停により調整がされ,合意ができないときに審判による判断がされます。
また、審判申立ての際には、申立ての趣旨と実情を明らかにする以外に,①寄与の時期,方法および程度その他の寄与の実情,②遺産分割の申立てがあった場合には,当該事件の表示,民法910条の価額請求がなされた場合には,共同相続人および相続財産の表示,認知された日,すでになされた分割その他の処分の内容を明らかにする必要があります。
家事事件手続規則
第102条
2 寄与分を定める処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 寄与の時期、方法及び程度その他の寄与の実情
二 遺産の分割の審判又は調停の申立てがあったときは、当該事件の表示
三 民法第910条に規定する場合にあっては、共同相続人及び相続財産の表示、認知された日並びに既にされた遺産の分割その他の処分の内容
▼ 主張の際に役立つ証拠例
寄与分を集中する場合に、役に立つ証拠としては以下のようなものがあります(あくまで例示です)。
- 介護日誌、医療費・介護費の領収書
- 金銭的援助を示す通帳記録や振込明細
- 事業手伝いの実績を示す帳簿や契約書
- 他の相続人とのやり取りの記録(メール・手紙)
私自身、かつて本人訴訟をしたことがあるので、裁判に出す証拠というものがどういうものでなければならないかは知っています。
裁判で寄与分の請求をする場合は、ただ単に「私が世話をしていました」といっても意味がないので、具体的にその事実を示すものを提示するひつようがあります。
上に示した資料以外にも、被相続人に対して、通常の扶養の範囲を超える支援をしていたという事実の証明になるものがあれば、出したほうがいいと思います。
5. 専門家に相談するメリットと注意点
寄与分は非常にデリケートで、法律的な判断が求められるテーマです。
自己判断で進めようとすると、他の相続人との間でトラブルになってしまうことも少なくありません。
当事務所(文京区湯島の司法書士・行政書士事務所)では、相続に関するご相談を丁寧にお伺いし、必要に応じて遺産分割協議書の作成や証拠整理のサポートを行っております。
ただし、相続人同士で既に揉めている場合や、紛争性が高い場合には、司法書士では対応できない可能性があります。
そのようなケースでは、弁護士事務所へのご相談をおすすめいたします。
6. FAQ|寄与分に関するよくある質問
- 寄与分とは何ですか?
-
寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持・増加に対して特別な貢献(寄与)をした相続人に対して、その分を考慮して遺産を多く受け取ることができる制度です。
民法第904条の2に規定されており、相続における公平性を保つ目的で設けられています。
- 寄与分は誰でも主張できますか?
-
寄与分を主張できるのは相続人のみです。
被相続人と親族関係にあっても、相続人でなければ通常の寄与分の請求はできません。
ただし、相続人以外の親族(例:長男の妻など)が療養看護などに特別な貢献をした場合には、「特別の寄与(特別寄与料)」という制度(民法第1050条)に基づき、相続人に金銭の請求を行うことができます。
- どのようなケースで寄与分が認められますか?
-
寄与分が認められるには「特別な貢献」が必要です。以下のようなケースが代表的です:
- 長期間にわたる無償の介護(療養看護型)
- 家業への無給従事による事業貢献(家業従事型)
- 金銭的な援助や資金提供(資金援助型)
単なる同居や定期的な訪問などでは、寄与分が認められないこともあります。また、これらの場合に該当しても寄与分が認められない場合もあります。
- 寄与分はどのように計算されますか?
-
寄与分の計算に明確な法定式はありません。実務上は以下のような考え方が用いられます
- 被相続人が死亡時に有していた相続財産総額から、寄与分を差し引く
- 残った財産を、法定相続分に従って相続人全員で分ける
- 寄与した相続人には、その法定相続分に加えて寄与分を上乗せして支給する
- 寄与分を主張するにはどうすればいいですか?
-
遺産分割協議の中で他の相続人に対して寄与分を主張する必要があります。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停か審判を申し立てることになります。
- 寄与分を証明するために必要な証拠は?
-
主張を裏付ける証拠として、以下のような資料が有効です:
- 医療費の領収書
- 金銭援助の記録(振込明細、通帳など)
- 家業従事の証拠(帳簿、契約書など)
これらの証拠をできるだけ具体的に用意することが必要になり
- 特別の寄与(特別寄与料)とは何ですか?
-
「特別の寄与」とは、相続人ではない親族が被相続人に特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭請求ができる制度です(民法第1050条)。たとえば、亡くなった義理の母の介護を長年無償で行っていた長男の妻などが対象になります。
特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき,または相続開始の時から1年を経過したときは,もはや特別寄与料の支払を求めることはできなくなります(民1050条2項ただし書)。
- 寄与分について司法書士に相談できますか?
-
はい、司法書士は寄与分に関する相続支援業務として、相談対応や証拠整理、遺産分割協議書の作成などが可能です。
ただし、相続人間で寄与分をめぐり争い(紛争性)が生じている場合は、司法書士では対応できないため、弁護士への相談をおすすめしています。
- 文京区以外からの相談も可能ですか?
-
当事務所は文京区湯島にありますが、東京都全域、千葉県、埼玉県、神奈川県からのご相談にも対応しております。是非、お気軽にお問い合わせください。
まとめ|「寄与分」を知って公平な相続を
今回は寄与分について解説しました。
寄与分が問題になるときは揉め事になっていることが多いため、司法書士である私の出番ではないのかもしれません。
もっとも、寄与分の制度を正しく理解することで、ご自身の貢献が正当に評価される可能性が高まります。
「頑張ったのに報われない…」と感じる相続人の皆様の役に立てばと思い、記事を作成いたしました。
寄与分以外のことでも、相続のことでお悩みの方は、文京区湯島で相続のサポートを行う栗栖司法書士行政書士事務所にご相談いただければと思います。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。