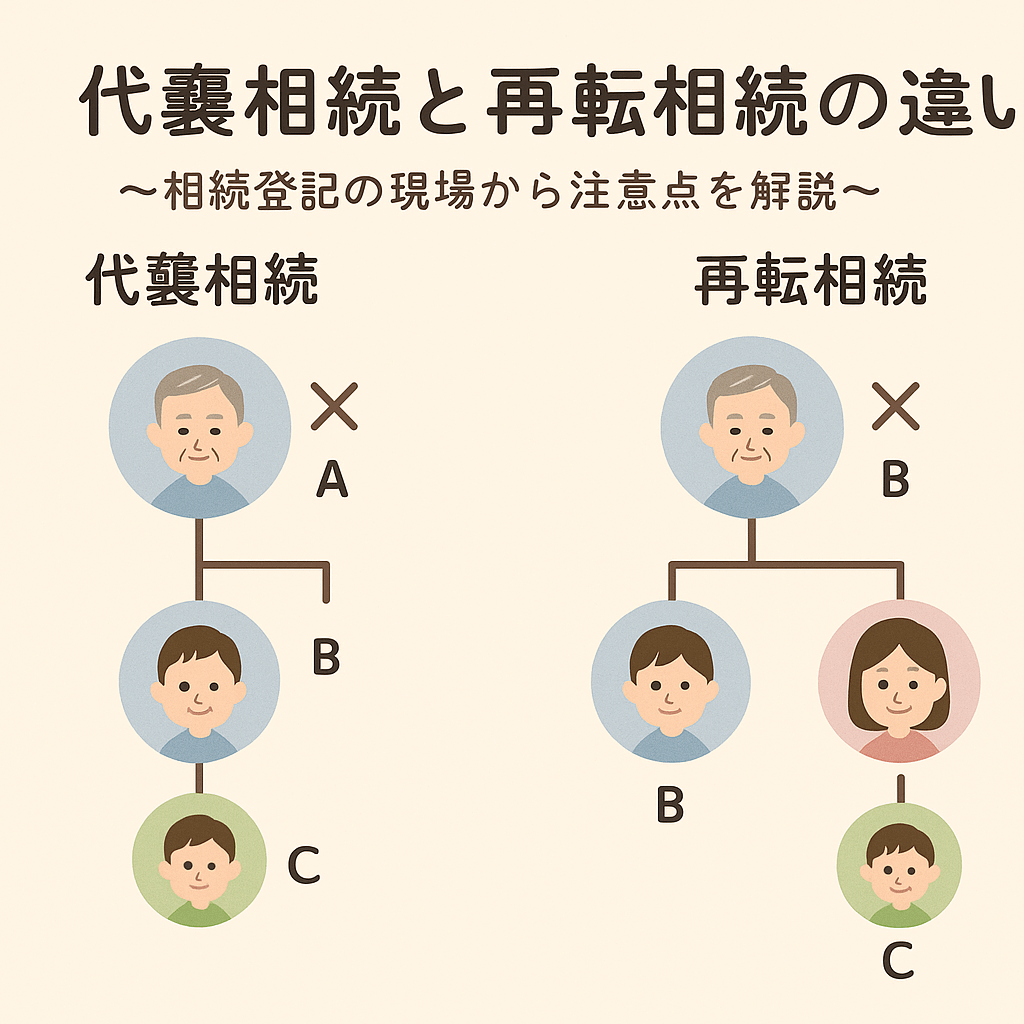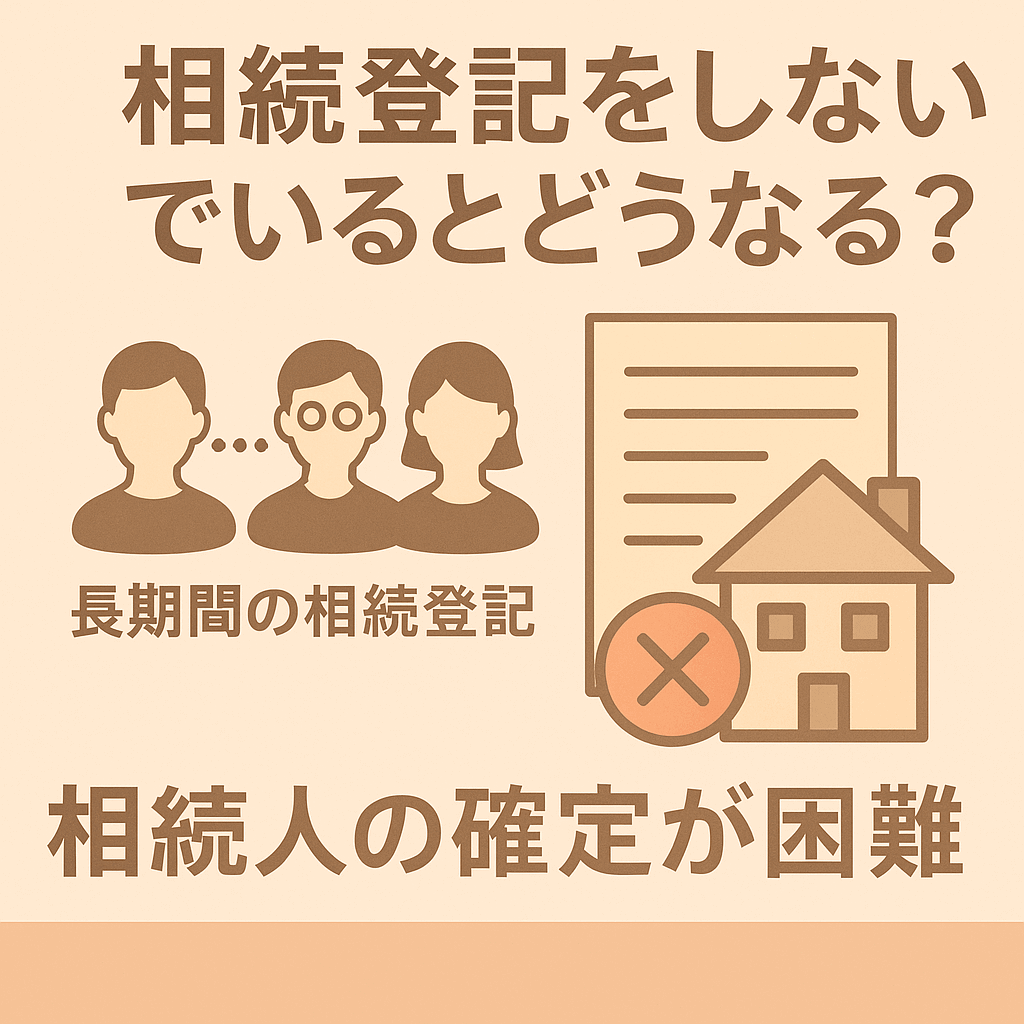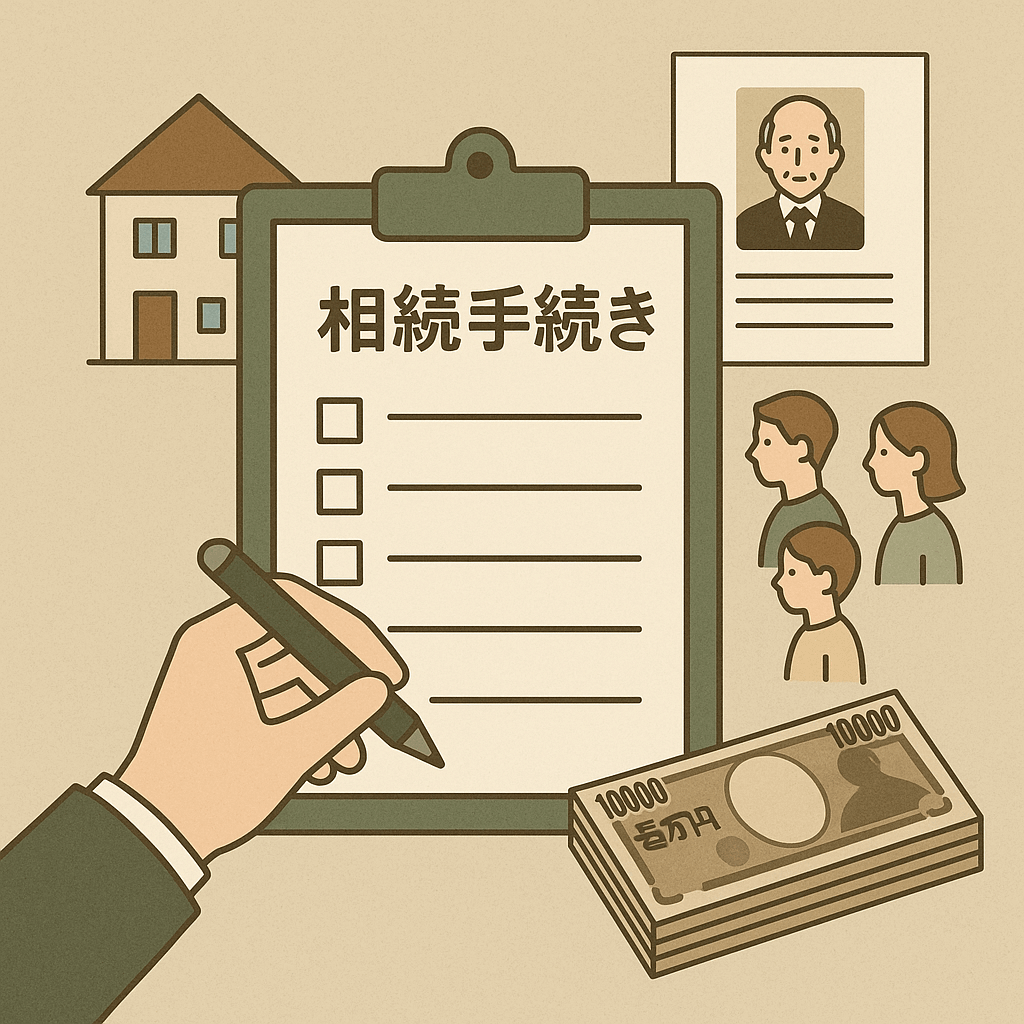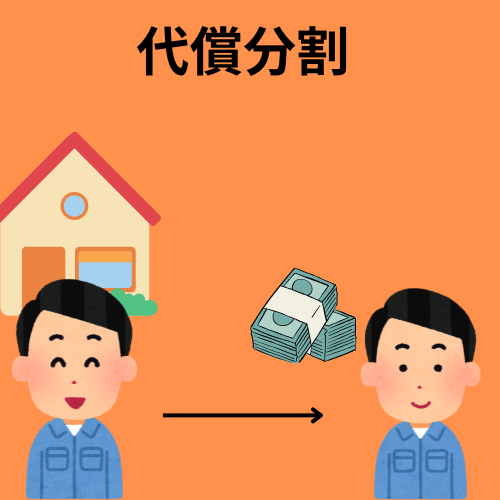相続の場面では、「相続放棄」「相続分の放棄」「相続分の譲渡」といった言葉が登場します。
一見似ているように思えますが、それぞれ意味や効果が異なります。
本記事では、これらの違いについて、具体例も交えてわかりやすく解説します。

相続放棄とは?【具体例付き】
「相続放棄」とは、相続人としての立場そのものを放棄する手続きです。
具体例その1
被相続人Aが亡くなり、相続人は子ども3人(B、C、D)だとします。Aには借金が500万円あります。
このとき、Bが「相続放棄」すると、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、相続人はCとDの2人になります。
借金500万円の負担もCとDで分けることになります。
ポイント
相続放棄をした場合、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産を相続することがなくなるだけでなく、負担していた債務についても、相続することがなくなります。
そのため、相続放棄は、相続される方が、被相続人の借金を負担したくないという場合に有効になります。
もっとも、相続放棄には期間制限があり、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に対して、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないとされています。
より詳細な内容はこちらのページをご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html?utm_source=chatgpt.com
具体例その2
事例
被相続人Aが死亡。相続人は子どもが3人(B・C・D)です。
Aの遺産は現金900万円。
法定相続分は:
- B:1/3(=300万円)
- C:1/3(=300万円)
- D:1/3(=300万円)
▼このとき、Bが「相続放棄」した場合…
Bは最初から相続人でなかったものとみなされるため、相続人はCとDの2人になります。
➡ 相続分の再計算:
- C:1/2(=450万円)
- D:1/2(=450万円)
ポイント
続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、放棄した方の相続分は、他の相続人の間であらためて分け直されることになります。
たとえば、もともと相続人が3人いた場合に1人が相続放棄をしたときは、残った2人で遺産を2等分するような形になります。
つまり、相続放棄をすると、相続人の人数が変わり、結果として相続分の割合も変化してくるわけです。
また、相続放棄をした方は、財産を一切受け取らないだけでなく、遺産分割協議などの手続きにも加わる必要がなくなります。
まさに、初めから相続人でなかったという扱いになるのです。

相続分の放棄とは?【具体例付き】
「相続分の放棄」とは、自分の取り分を主張しないという意思表示です。
相続放棄と異なり、相続分の放棄には期間制限がありません。
ただし、相続人としての地位は残ります。
そのため、債権者に対する債務の支払いは依然として残り、相続分の放棄があったことを債権者に対して対抗することは出来ません。
また、相続分の放棄は、相続放棄と異なり、その場限りの効果しかないことにも注意が必要です。
相続分の放棄は、相続開始後から遺産分割までの間であれば、いつでも可能であり、その方式も問わないとされています。
もっとも、実務上は、相続分の放棄の意思を明確化するため、相続人本人に相続分放棄書のような書面を作成して、署名、実印での押印及び印鑑登録証明書の添付を求めることが一般的です。
事例:父が亡くなり、母と子ども2人が相続人
【家族構成】
- 被相続人(父)A
- 相続人:妻B、子C、子D
- 遺産:1,200万円
【法定相続分】
妻B:1/2(600万円)
子C:1/4(300万円)
子D:1/4(300万円)
Cが相続分を放棄した場合
この場合、実務では,長女Cの相続分4分の1(1/2×1/2)は「残された相続人の相続分率」に応じて再配分されると解されています。
すなわち、Cの1/4あった相続分を、BとDの相続分の割合で分けるわけです。
具体的には、Bの相続分が2/4でDの相続分が1/4なので、BとDの相続分の割合は2対1となり、Bが2/3、Dが1/3の割合で、Cの相続分を分け合うことになります。
計算
B:1/4×2/3=1/6
D]1/4×1/3=1/12
これに、もともとあったB とDのそれぞれの相続分を加えて計算します。
すると
Bの相続分 1/6+1/2(3/6)=4/6=2/3
Dの相続分 1/12+1/4=4/12=1/3
となり、Bが2/3、Dが1/3の相続分となります。
まとめ
- 家庭裁判所での手続きは不要
- 他の相続人の取り分が相続分の割合に応じて増える

相続分の譲渡とは?【具体例付き】
「相続分の譲渡」とは、自分の相続分を他の人に譲ることができる制度です。
譲渡先は他の相続人でも、まったくの第三者でも可能です。
相続分の譲渡は、相続放棄と異なり、特別な手続きが不要です。この点は相続分の放棄と同じです。
譲受人は,譲渡を受けた割合的持分に相当する積極財産のみならず,債務を承継することになります。
もっとも、相続分の譲渡は債権者の関与なくして行われるものなので,譲渡人が対外的に債務を免れることはできません。この点にも注意が必要です。
具体例
Aが亡くなり、B・C・Dが相続人。Bは自分の相続分(1/3)をCに譲渡する契約を結びました。
この場合、Cは2/3の相続分(自分1/3+譲渡された1/3)を持つことになります。
そのため、相続登記の申請の際には、Cが持ち分2/3、Dが持ち分1/3で申請することになります。
✔ ポイントまとめ
相続分の譲渡は、自分の持っている相続分を、他の相続人はもちろん、まったく関係のない第三者に譲ることも可能です。
譲渡を行う際には、「相続分譲渡契約書」や「相続分譲渡証明書」といった書面を作成しておくのが一般的です。
実務においては、「相続分譲渡契約書」や「相続分譲渡証明書」には、譲渡人の印鑑証明書の添付が必要となることに注意してください。
譲渡を受けた人は、譲られた相続分を主張できるようになりますので、その分について遺産分割に参加することになります。
一方で、譲った人は自分の相続分を手放しているため、原則としてその後の遺産分割協議には関わる必要がなくなります。
このように、相続分の譲渡は、相続人同士の事情や関係性に応じて柔軟に対応できる制度です。
対応エリア|東京都文京区湯島を中心に幅広く対応
文京区湯島にある当事務所では、以下の地域を中心に対応しております。
- 文京区・千代田区・台東区・新宿区・豊島区など東京23区
- 埼玉県:さいたま市・川口市・戸田市
- 千葉県:船橋市・市川市・松戸市・柏市 など
- 神奈川県:川崎市・横浜市など
相続の不安、今すぐご相談ください
今回の記事では、相続放棄・相続分の譲渡・相続分の放棄について記載しましたが、当事務所では相続に関する幅広い相談に対応しています。
相続に関する悩みをお持ちの方は、お気軽に相談ください。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号03-3815-7828
メールアドレス kurisu.yushima@gmail.com
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。