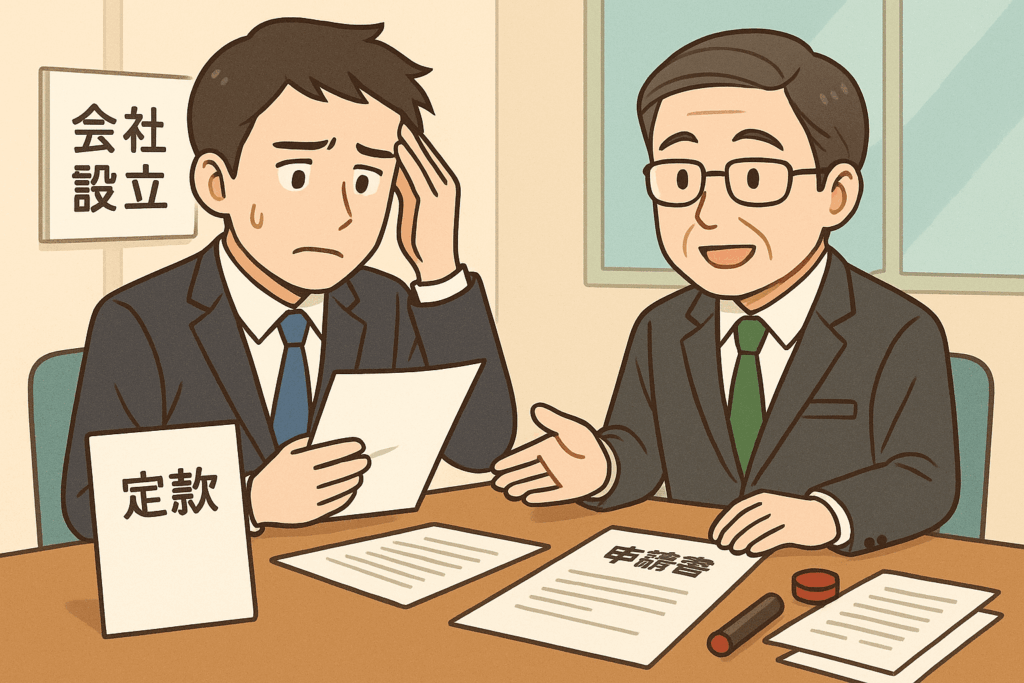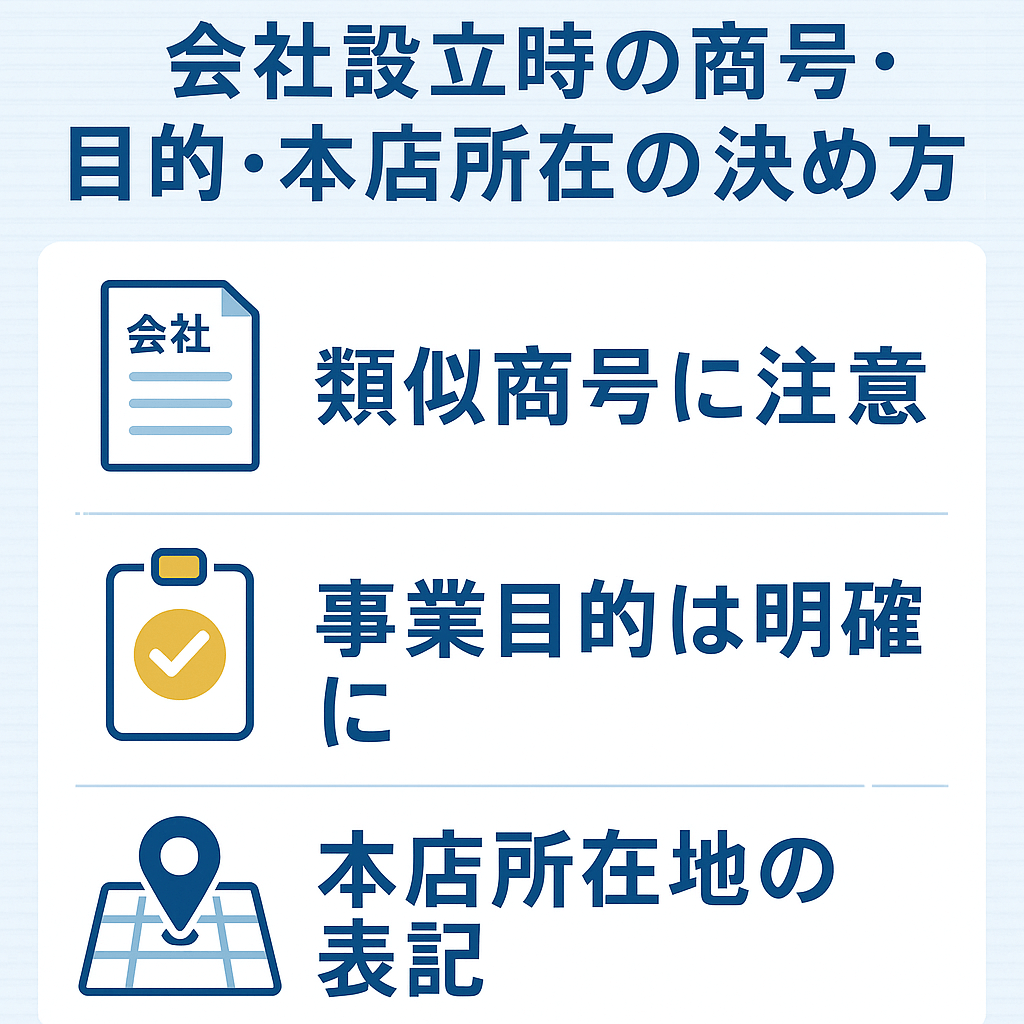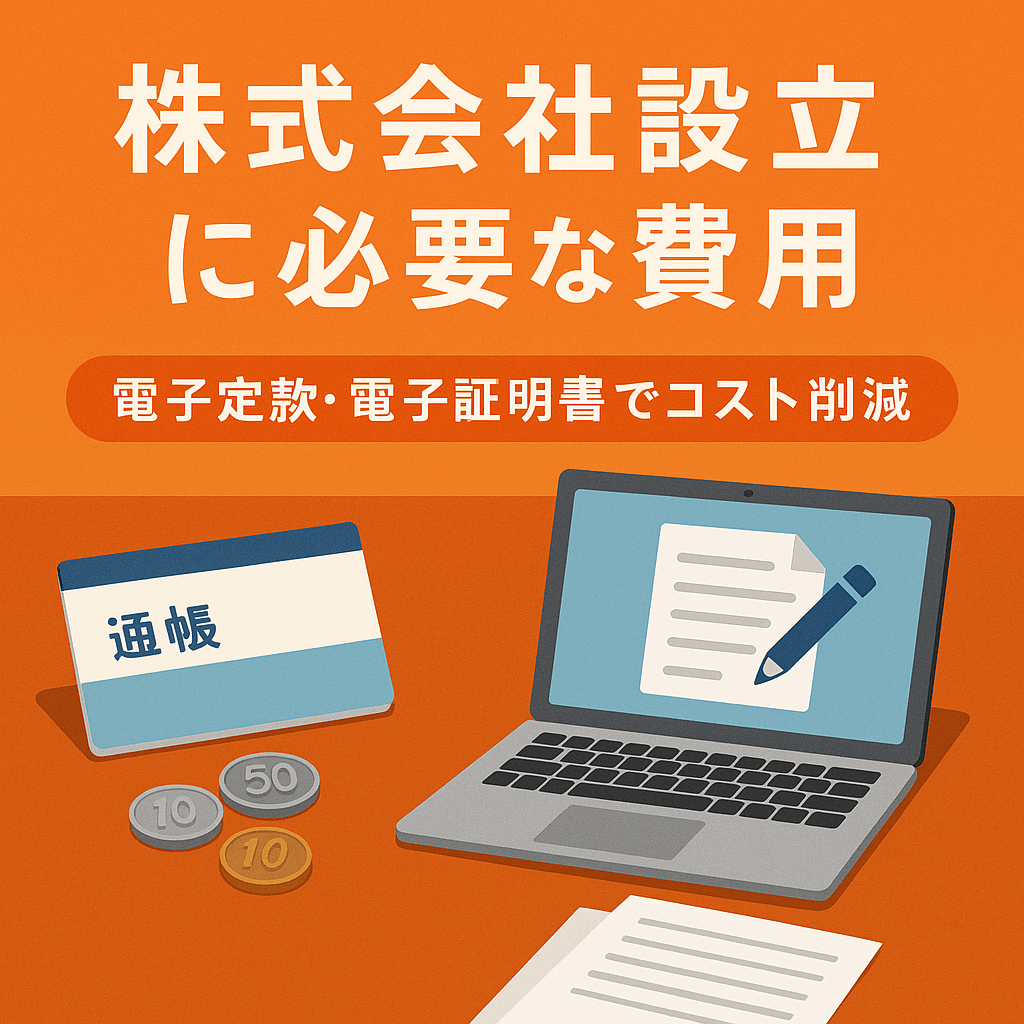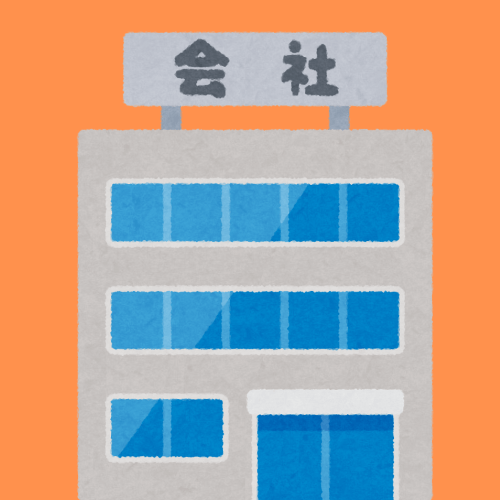はじめに:株式会社を設立したいあなたへ
株式会社を設立しようと思ったとき、必ず出てくるキーワードが「発起人」です。
でも、「発起人って何をする人?」「誰でもなれるの?」「責任はあるの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、発起人の意味・役割・なれる人の条件・責任・よくある勘違い・発起人同士で決定すべき事項まで、一通りわかりやすく解説します。
なお、当事務所は発起設立をメインとして扱う事務所なので、以下は発起設立を前提として話をさせていただきます。

発起人とは?株式会社設立の第一歩を操る人
発起人とは,株式会社の設立を企画する者のことをいいます。
もっとも、法律上は,発起人として定款に署名または記名押印した者だけが発起人とみなされます。
第二十六条 (定款の作成)
1 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
発起人として定款に署名等をしていない者は,たとえ事実上,設立を企画しそれに尽力しても,法律上は発起人とみなされることはありません。
ただ、この場合、擬似発起人として責任を負う可能性があります。
発起人の役割
発起人は、会社設立事務の義務と権限を有しており、設立に関する主な事務は発起人が行います。
発起人以外の者が行う設立事務としては以下のものがあります。
- 設立時取締役や監査役による設立手続の法令・定款違反の調査(会社法46条・93条)
- 設立時代表取締役等の選任・解任など
- 設立後の会社を代表する者による設立登記の申請(商業登記法47条)
発起人の設定要件と質的要件
発起人の員数や資格には原則制限はありません。
個人でも法人でも発起人になることは出来ますし、外国人でも大丈夫です。
さらに、未成年者や成年被後見人と言った制限行為能力者も発起人になることが出来ます。
もっとも、未成年者や成年被後見人等が発起人になる場合は、法律上必要な手続(法定代理人の同意など)が必要となります。
ただし、発起人は法定上の責任を負うため、「権利義務の主体となりうる能力」が必要であると解されています。
ゆえに法人格なき組合などは発起人になれません。ここは注意が必要です。

発起人の責任
発起人の負う責任としては以下のようなものがあります。
発起人の会社に対する任務懈怠責任
発起人が職務を行う際に、その任務を怠ったときは,成立後の株式会社に対し,それによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります(会社法53条1項参照)。
ちなみに、複数の発起人に、任務懈怠があった場合は、連帯責任になります(会社法54条)
発起人の出資に関する責任
発起人が、設立時募集株式の発行の際に、出資の履行を仮装した場合は、成立後の会社に対して仮装出資に係る払込金額の支払義務を負うことになります(会社法52条の2第1項)。
また、現物出資等の財産の会社成立時における実価が,定款記載価額に著しく不足する場合,発起人及び設立時取締役には,原則として,連帯して,その不足額を会社に支払う義務を負うことになります(会社法52条の2第2項)。」
もっとも、発起設立の場合は、検査役の調査を受けた場合と、発起人が職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合は,責任は生じないとされています(過失責任)。
ちなみに、発起人の会社に対する任務懈怠責任と出資に関する責任は、総株主の同意があれば免除できます。
発起人の第三者に対する責任
発起人,設立時取締役または設立時監査役が,職務を怠ったことについて悪意または重過失があったときは,それによって第三者に生じた損害についても責任を負うものとされています(会社法53条2項)。
この場合、複数の者が責任を負う場合は連帯責任となります。
この責任は、第三者に対する責任なので、総株主の同意があっても免除できません。
会社不成立の場合の発起人の責任
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する(会社法56条)。
この責任は無過失責任です。

発起人と取締役、株主の違い
会社設立をされる方の中には「発起人と取締役の違いがわからない」という方がいらっしゃいます。
わかりやすく言えば、発起人は、会社の設立に関わる存在であり、取締役は、設立後の会社の経営に携わる存在と言えます。
発起人は、会社設立後に取締役となり経営に関わることも出来ます。
また、発起人は必ず一株以上株式を引き受けなければいけません(会社法25条2項)。
第二十五条
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
そのため発起人は株主となり、会社経営に参加することも出来ます。
発起人同士の決定事項について
発起人の複数同志が存在する場合、定款の内容や会社の基本方針は発起人の協議によって決定されます。
これらの決定事項は設立手続の過程の中で順次決定していっても問題はありません。
もっとも、事前に決めておくことで全ての手続が順調に進みます。
そんため、「発起人協議書」(または発起人が一人の場合は「発起人決定書」)を作成しておくことをおすすめします。
【発起人の過半数による決議が必要な事項】
発起人またはその議決権の過半数で決定できる主な事項には、次のようなものがあります:
- 株主名簿管理人の決定
- 本店の所在場所の決定
- 支店設置場所の決定
- 支配人の選任
【定款に定めない限り発起人全員の同意が必要な事項】
- 発起人が割当を受ける株式の種類および数(会社法32条1項1号、28条1号)
- 割当株式と引換に払い込む金銭の額(32条1項2号)
- 成立後の会社の資本金および資本準備金の額(32条1項3号)
- 設立時募集株式の種類および数(58条1項1号・2項)
- 設立時募集株式の払込金額(58条1項2号・2項)
- 設立時募集株式の払込期日または期間(58条1項3号・2項)
これらの法定事項は、定款に定めがない限り、発起人全員の同意によることが要件とされます。

よくある質問(FAQ)
- 発起人と取締役は同じ人でも構いませんか?
-
はい、構いません。設立時の取締役に発起人が就任することは可能です。
- 発起人は何人必要ですか?
-
発起人の人数は1人でも構いません。
- 未成年者でも発起人になれますか?
-
はい、可能です。ただし、単独で行うには法定代理人(親権者など)の同意が必要です。
- 法人格のない団体や組合でも発起人になれますか?
-
いいえ、発起人には「権利義務の主体となりうる能力」が求められるため、法人格のない団体(法人格なき社団等)は発起人にはなれません。
- 発起人になることでどのような責任が生じますか?
-
発起人は出資実行義務を負うほか、設立過程で損害が生じた場合は、会社や第三者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
株式会社設立のご相談は当事務所へ
発起人に関する手続きや設立登記に関するご不安がある方は、ぜひ一度「栗栖司法書士行政書士事務所」へご相談ください。
当事務所では、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の株式会社設立手続をサポートしています。
定款作成から登記申請、発起人に関する法的アドバイスまで丁寧に対応いたします。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号 03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。