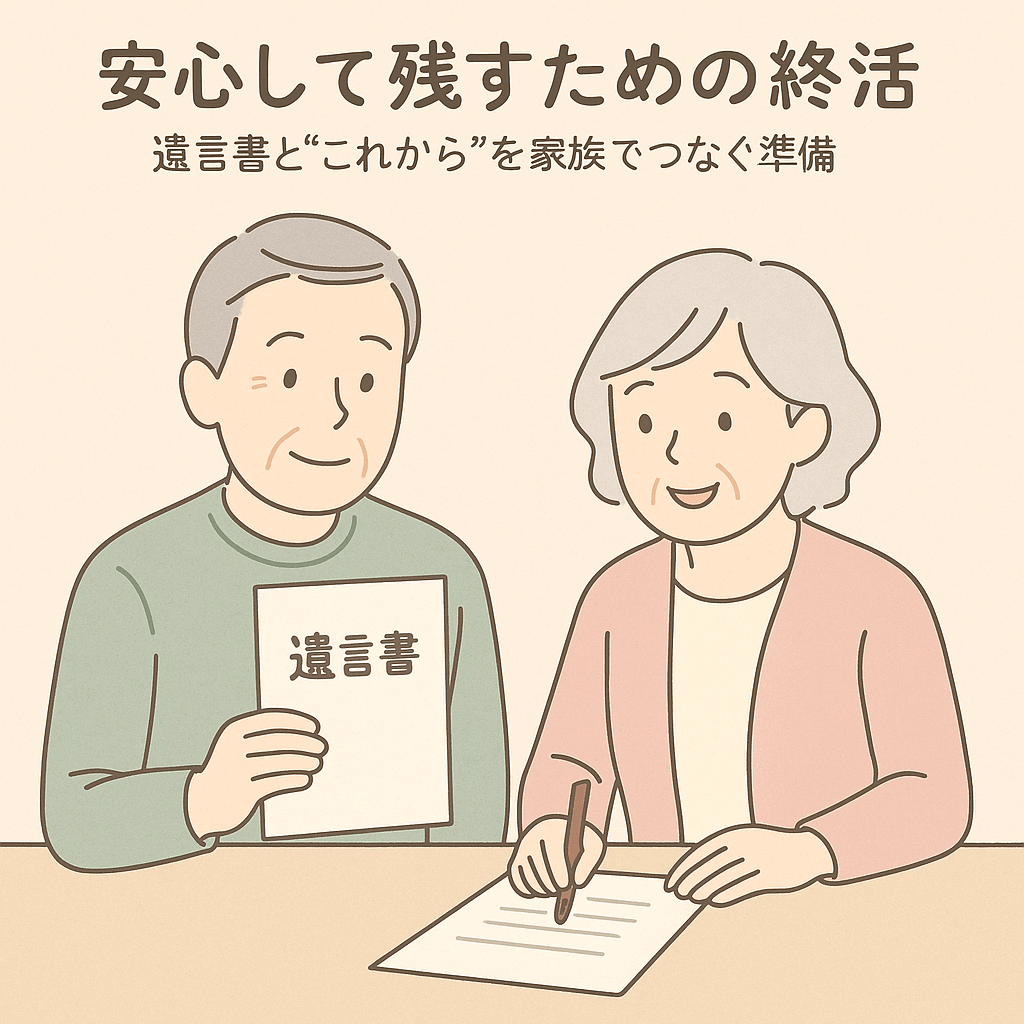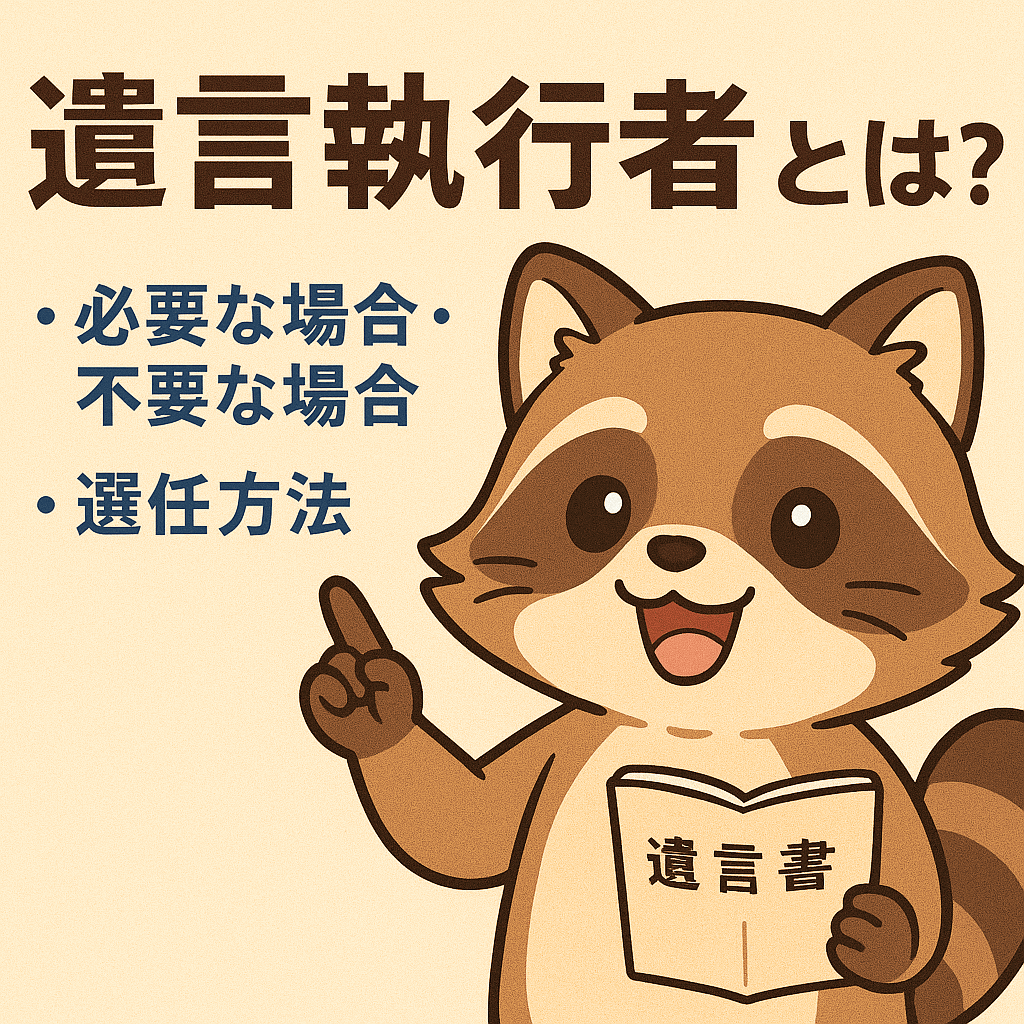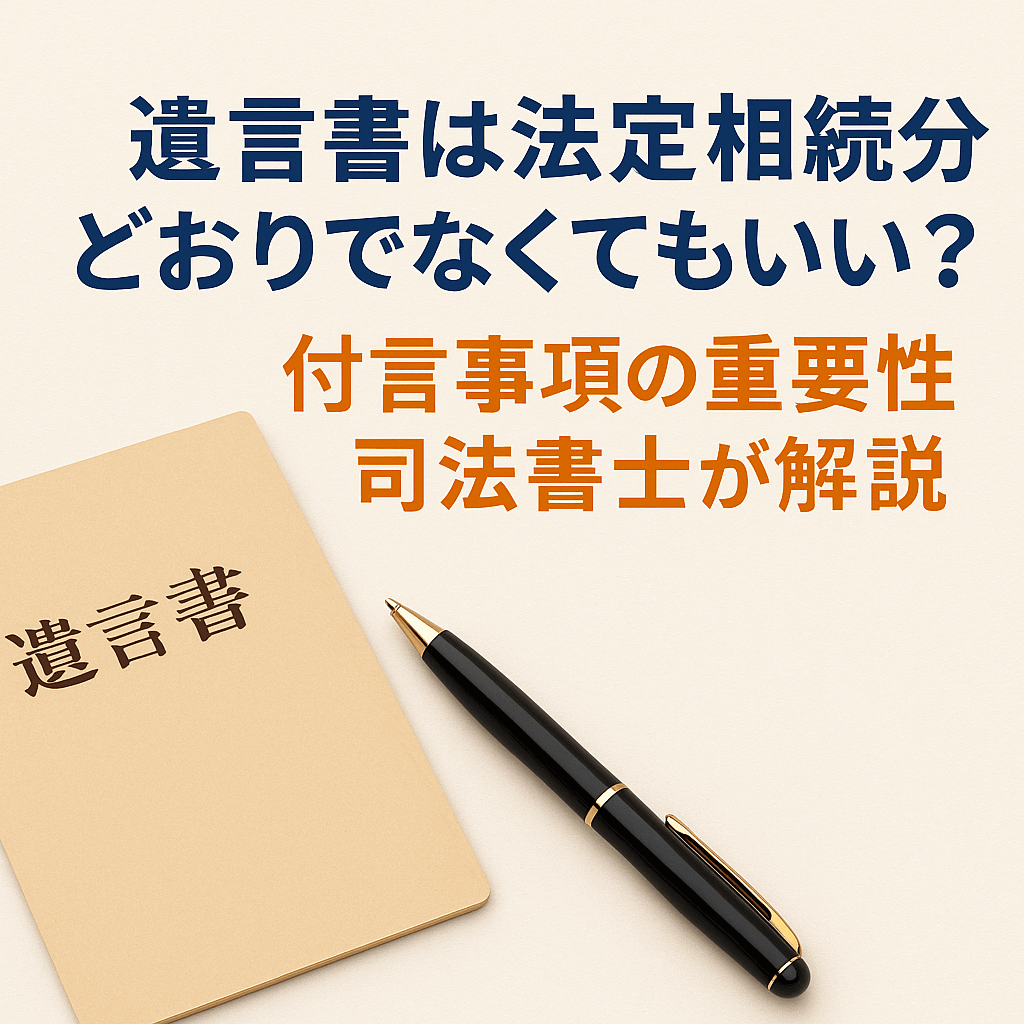小学生の時、従兄弟の家にいる犬の話をして友人と盛り上がっていた時、同級生に「動物なんてどうでもいいから、人間の相手をしなさいよ」と言われたことがあります。
実は、動物は法律上は「物」とされており、人間とは異なる扱いを受けます。
しかし、犬や猫が好きという人は非常に多いです。カメを飼育している方もいます。
動物が大好きという方にとって、ペットは大切な家族の一員です。

しかし、自分にもしものことがあったとき、ペットは誰が面倒を見てくれるのでしょうか?
近年、飼い主の高齢化や単身世帯の増加により、「ペットの将来を遺言で守る」という考え方が注目されています。
令和元年に制定された動物愛護法でも、飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼育することが求められています(動物愛護法7条4項)。
自分が飼ったペットの面倒を最後まで見ることは、飼い主として果たすべき重要な責務です。
この記事では、大事なペットのためにできる遺言の書き方や注意点について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
ペットは「相続人」になれる?──法律上の位置づけ
先程も書きましたが、ペットは民法上「物(動産)」として扱われます。
つまり、人間のように「相続人」として遺産を受け取ることはできません。
「家のワンちゃんは家族同然なのにどうして?」と仰る方もいると思います。
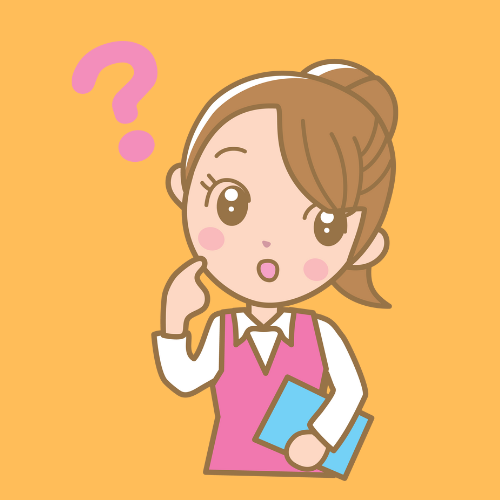
しかし、法律というものは杓子定規なものです。文句を言ってもどうにもならないこともあります。
もっとも、ペットの世話を任せたい人に財産を渡すことは可能ですし、ペットの面倒を見てもらうことは可能です。
たとえば、「○○がうちの犬の世話をしてくれることを条件に、○○万円を相続させる」といった形の遺言が代表的です。
ペットを守る遺言の3つの基本パターン
① ペットの世話をしてくれる人に財産を託す(負担付遺贈)
これはもっともシンプルで実務的な方法です。
例文:
「私の飼い犬ポチの世話を生涯にわたって行うことを条件に、妹○○に金○○万円を遺贈する。」
このように、「世話をすること」を条件として財産を渡すことで、ペットの生活を守ることができます。

また、受遺者が遺言を適切に執行しない場合に備えて、遺言執行者を指定しておくこと、個人的にはお勧めです。
負担付の死因贈与でペットの世話を頼む
遺贈が単独行為とされるのに対し、死因贈与が成立するには、贈与者と受贈者との間で、負担付死因贈与契約について、意思の合致がなければいけません。
この場合、当事者間でペットの飼育に対して、意思の合致があるわけですから、ペットの飼育が適切に行われる確率は高くなります。
また、死因贈与の場合も、死因贈与の執行者を指定することができるので、死因贈与執行者を指定することで、ペットの世話が適切に行われるように監視することができます。
② ペット信託の活用(信託制度を使った備え)
信頼できる人がいない場合や、より確実に管理したい場合には、ペット信託という仕組みも検討されます。
これは、信託契約により信託財産(お金)を管理し、ペットの飼育を目的として第三者を受託者として委託する方法です。
遺言書で気をつけたい4つのポイント
ペットについて具体的に記載すること
遺言書には、「ペット」とだけ書くのではなく、「犬のポチ(トイプードル・オス・15歳)」などと明記しましょう。
単に「ペット」などと書くと、犬と猫を飼っていた場合などは「どれのこと言ってるの?」となってしまい、死後にペットの世話をしてもらうという目的を達成できなくなります。
ペットの将来のためにも、しっかりと記載してください。

ペットの飼育等の希望も書いておくと安心
遺言でペットの世話を頼んだと言っても、やはりどういう飼育をされるか不安になるという方は多いと思います。
また、ペットにも命があります。ペットがなくなった場合のことについても心配されている買主の方は多いのではないでしょうか。

そういった場合に備えて、遺言書に、飼育についての希望やペットがなくなった場合についての希望を一言添えておくといいと思います。
例としては「私の愛犬○○を大切に飼育しなければならない。また、愛犬○○がなくなった場合は、手厚く供養して埋葬すること」などと記載することが考えられます。
もしご自身が「必ずそうしてほしい」という願いがあるのであれば、相手の方にとって必要以上の負担にならない限りで記載するのもいいと思います。
ペットの飼育をお願いする人の同意を事前に得る
遺言書でペットの飼育を依頼しても、いきなり頼まれた場合は「なんで俺がするの?」となる場合もあります。
そうなると、遺贈の放棄をされてしまい、ペットの世話をしてくれる人がいなくなってしまう場合があります。

こういった、トラブルを防ぐためにも、必ず了承を得てから遺言に記載しましょう。
遺言書にはこういった事は記載されませんが、非常に重要なことです!
できれば公正証書遺言で作成を
確実に執行できる形にするには、公証人を通じて作成する「公正証書遺言」がおすすめです。
よくある質問(FAQ)
- ペットの世話を頼みたい友人に財産を渡してもいいの?
-
はい、可能です。友人や第三者にも遺贈はできます。ただし、その人の同意は得ておくべきです。
- ペットが複数いる場合はどう書くの?
-
各ペットごとに名前・種類・年齢・世話を依頼する人などを分けて明記するのが望ましいです。
- 負担付遺贈で指定した人が拒否したらどうなる?
-
拒否された場合は法的義務がなくなります。代替の飼育者も想定しておくと安心です。
まとめ:ペットの将来は、飼い主の「今の準備」で守れる
私たちが最期まで安心してペットと暮らすためには、「自分に何かあったときのこと」をしっかり考えておくことが大切です。
遺言書にペットのことを書くのは、残された命を守る優しさの表現といえます。
当事務所では、ペットを守るための遺言書作成のご相談を承っております。
もし、遺言書を作成する際にペットのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ともご相談ください。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号 03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。