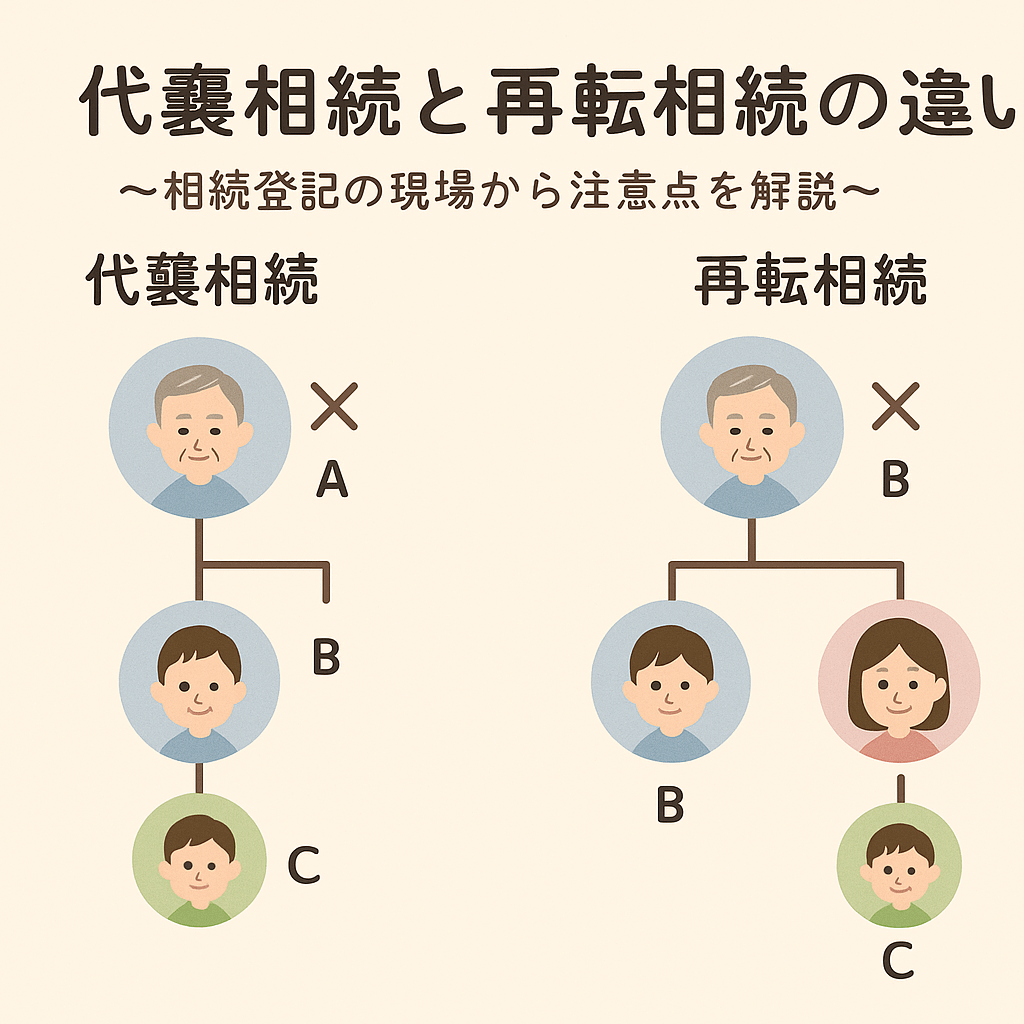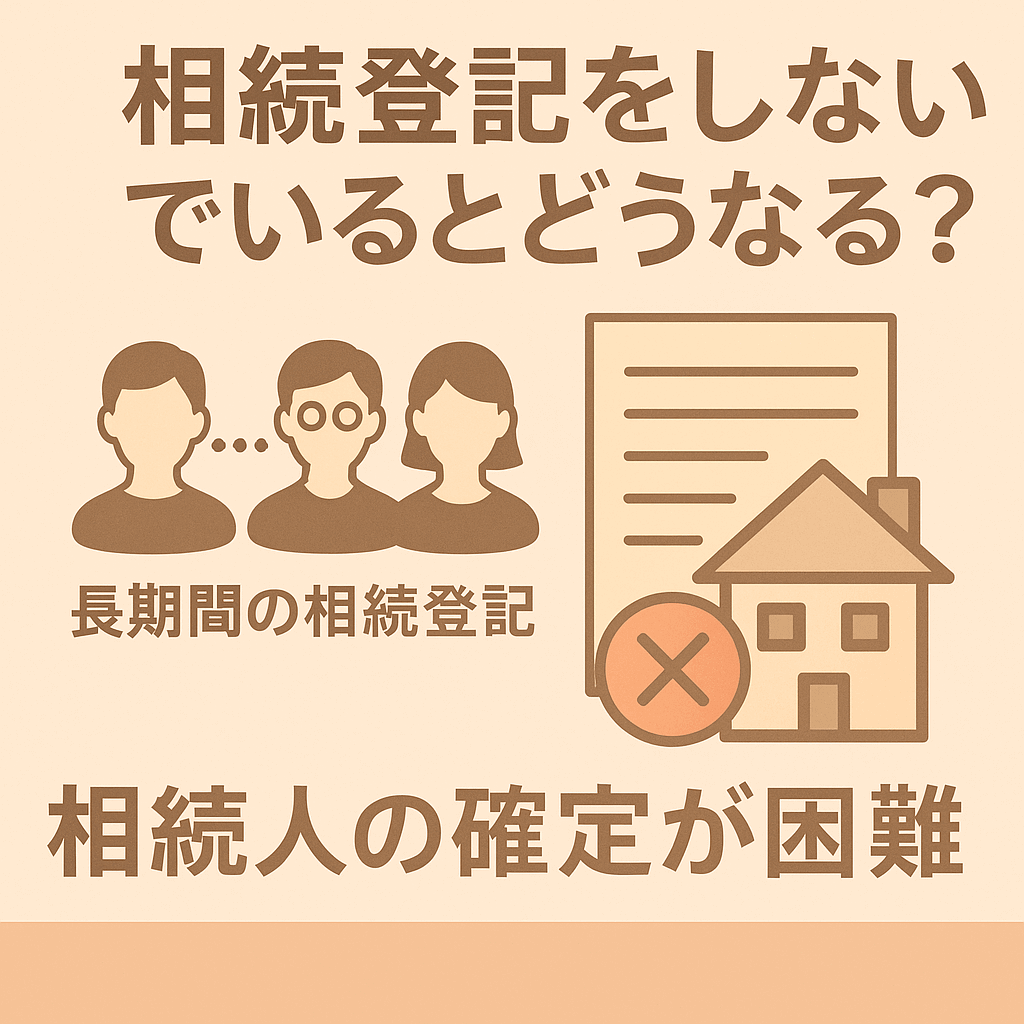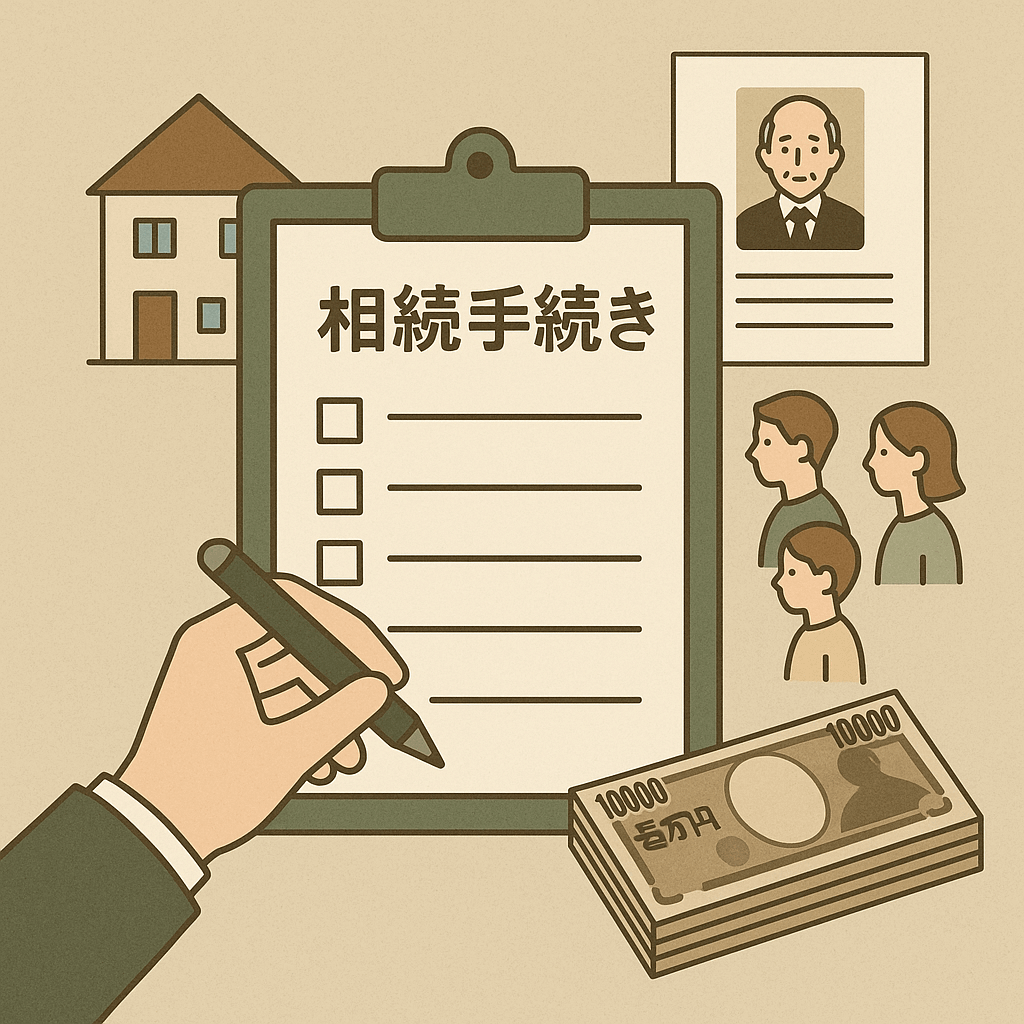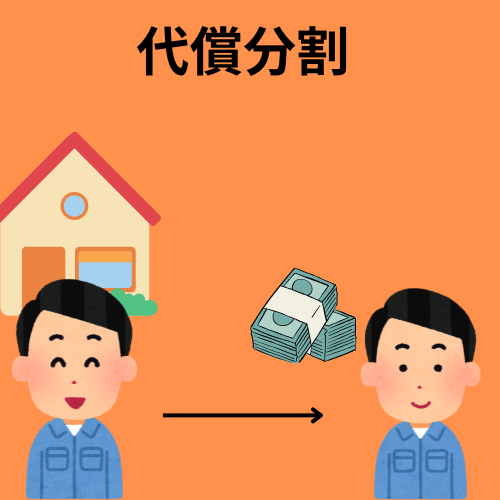相続における「特別受益の持戻し免除」という言葉をご存じでしょうか?
これは、2020年(令和元年)に改正された民法により明文化された制度で、主に配偶者の相続を保護する目的で設けられたものです。
これにより、相続発生後に不動産をめぐる争いを避け、配偶者の住まいと生活を守るための法的な仕組みが整えられたのです。
今回は、この特別受益の持戻し免除について説明していきたいと思います。

特別受益とは?まずは基礎から理解しましょう
相続において、被相続人(亡くなった方)から遺贈または生計の資本として贈与を受けた相続人がいた場合、その贈与は「特別受益」として扱われることがあります。(民法903条1項参照)。
これは、他の相続人との公平性を保つために設けられた制度です。
たとえば、ある相続人だけが生前に多額の贈与を受けていた場合、それを考慮せずに遺産を均等に分けると不公平が生じてしまいますよね。
そこで、生前贈与を「先に相続した分」として遺産分割時に持ち戻すのが通常のルールです。
相続法改正で明文化された民法第903条第4項
民法の改正前から、「持戻しの免除」については、実務の現場ではすでに一定の運用が行われていました。
婚姻期間の長い高齢の夫婦の一方が、他方に居住用不動産を生前贈与するようなケースでは、たいていの場合、その贈与は長年の貢献に対する感謝や、老後の生活を安定させる目的で行われたと認められ、特別受益の持戻しを免除する意思があったと推定されることが多かったといわれています。
また、判例においても、東京高等裁判所平成8年8月26日決定のように、妻に他の資産や住まいがなかった事情を踏まえ、妻への贈与については遺産分割の対象から除外すべきと「持戻しの免除」を認めたものもありました。
これらの実務や裁判例を踏まえて、相続法は改正され、民法第903条第4項が新設されました。
これにより、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与や遺贈があった場合には、被相続人が持戻し免除の意思を有していたと推定するという明文化されたルールが整備されたのです。
第903条【特別受益者の相続分】
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
この改正によって、従来の実務慣行が法的に裏付けられ、配偶者が相続においてより多くの財産を確実に取得できる道が開かれました。
これは、老後の生活を安定させるため、配偶者の取得額を事実上増やす効果があります。
適用開始日と注意点
民法903条4項によって、「持戻しの免除」が明文化されたのは喜ばしいのですが、注意すべき点があります。
それは、この規定は、令和元年7月1日以降に開始された相続に適用されるということです。
過去の相続には遡って適用されません。
また、このルールはあくまでも「推定規定」であるため、被相続人が持戻しを希望する意思表示をしていた場合には適用されません。
特定財産承継遺言との関係
遺言によって「この不動産は配偶者に相続させる」と指定する「特定財産承継遺言」の場合、形式上は遺贈とは異なるため(相続によって直ちに相続人に財産が帰属する)、民法第903条第4項の直接的な適用はありません。
しかし、実質的に贈与と同じ意味を持つと考えられるため、同様の効果が得られることも多いです。
複数用途の不動産における取扱い
居住用と事業用など、複数の用途がある不動産については、居住用部分のみにこの規定が適用されます。
それ以外の部分については、不動産の使われ方や構造、遺言の内容などを総合的に判断する必要があります。
遺留分への配慮も忘れずに
持戻し免除の意思表示がある場合でも、それによって他の相続人の「遺留分」(最低限保障されている取り分)を侵害する場合は、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
FAQ(よくある質問)
- 特別受益の持戻し免除とは何ですか?
-
相続において、被相続人が生前に配偶者へ不動産などを贈与した場合でも、それを相続財産に含めない(持ち戻さない)と推定する制度です。2020年の民法改正により明文化されました。
- この制度はいつから適用されていますか?
-
令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続に適用されます。それ以前の相続には遡って適用されません。
- 配偶者に不動産を贈与しただけで自動的に適用されるのですか?
-
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与または遺贈があった場合には、持戻し免除の意思があったと法律上推定されます。ただし、被相続人が明確に「持ち戻す意思」を示していた場合は適用されません。
- 他の相続人の遺留分はどうなりますか?
-
特別受益の持戻しが免除されたとしても、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。
- 特定財産承継遺言を使った場合も、この制度は使えますか?
-
特定財産承継遺言は形式上「遺贈」ではないため、民法903条4項の直接の適用はありません。ただし実質的に同様の効果を持つことがあり、遺言内容や状況に応じて判断されます。
まとめ|配偶者の老後を守るための大切な制度
特別受益の持戻し免除制度は、長年連れ添った配偶者の生活を守るために生まれた、大変重要な仕組みです。
相続財産に不動産がある場合はトラブルになりやすいため、事前に贈与や遺言の内容をしっかり確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
文京区湯島に所在する当事務所では、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に、相続に関するご相談を承っております。
相続対策や遺言書の作成、生前贈与についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。