相続の場面では、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、他の相続人との間で不公平が生じることがあります。
このような不公平を是正し、相続人間の公平を保つために用いられるのが「特別受益(とくべつじゅえき)」という考え方です。
この記事では、東京都文京区湯島にある当事務所が、特別受益の定義・具体例・計算方法・主張や証明の注意点まで、相続実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
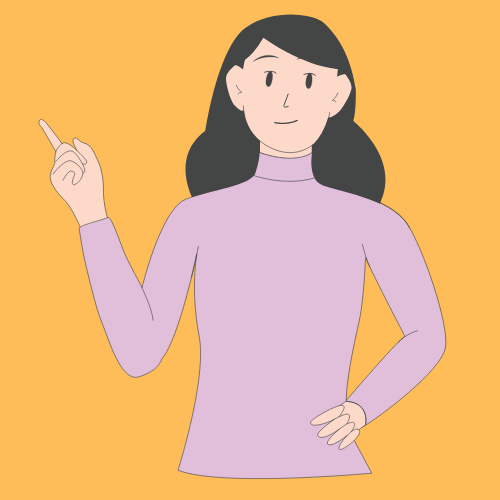
特別受益とは?
特別受益とは、民法第903条に定められたもので、被相続人が生前に、相続人のうち特定の人に対して財産の一部の前渡しにあたるような贈与や遺贈を行った場合に、それを考慮して遺産分割を行う仕組みです。
民法が特別受益として認めるのは、以下の3つに限られます。
特別受益に該当する3つのパターン(民法903条)
- 遺贈
被相続人の遺言により、相続人が特別に財産を受け取ること。遺贈は特別受益として当然に扱われます。 - 婚姻または養子縁組のための贈与
たとえば、高額な持参金や支度金などがこれに該当します。結納金や挙式費用などは、生活水準や他の相続人とのバランスを踏まえて判断されます。 - 生計の資本としての贈与
起業資金、自宅購入費用など、生活の基盤となる援助が含まれます。ただし、金額や目的、他の相続人との比較により、個別具体的に判断されます。
特別受益に「なりそうでならない」ものもある
以下のような利益が常に特別受益と認められるわけではありません:
大学・大学院などの高等教育費用
大学などの授業料については、その家庭の経済状況や他の相続人への扱いとのバランスにより判断されます。
私立大学の医学部の授業料の場合は、非常に高額となるので、特別受益と判断されることが多いそうです。
借金の肩代わり
被相続人が求償せず免除した場合、特別受益と見なされることがあります。
これも金額次第だと思います。
特別受益を踏まえた具体的相続分の計算方法
特別受益がある場合、各相続人が実際に受け取るべき遺産(具体的相続分)は以下のステップで計算します。
① 特別受益の有無・金額を確認
特別受益があったかどうかを確認し、その内容と金額を把握します。
※ 特別受益の評価額は相続開始時(死亡時)の時価で評価されます。
💡 相続税法では「受益時の額」で評価されますが、民法上の特別受益とは評価基準が異なりますので注意が必要です。
② みなし相続財産の計算
特別受益を受けた財産を、遺産に「持ち戻す」ことで、全体の分配基準を明らかにします。
📌 計算式:
みなし相続財産 = 相続開始時の財産 + 特別受益の合計額
③ 相続人ごとの取り分(相続割合)を計算
法定相続分または遺言による指定相続分に基づいて、各相続人が受け取るべき金額を計算します(この時点では特別受益を控除しません)。
📌 計算式:
各相続人の取り分(基準)= みなし相続財産 × 各相続人の相続割合
④ 特別受益の控除による具体的相続分の算出
特別受益を受けた相続人は、その額を差し引いた金額が実際に受け取る相続分になります。
📌 総合計算式(特別受益がある相続人の場合):
具体的相続分
=(相続開始時の財産 + 特別受益の合計額)× 各相続人の相続割合 - その相続人が受けた特別受益額
🧮 計算例
- 被相続人の遺産:4,000万円
- 相続人:A・B(2人)
- Bは生前に1,000万円の贈与を受けた(特別受益)
- 法定相続分:各1/2
【みなし相続財産】
4,000万円+1,000万円=5,000万円
【取り分の計算】
5,000万円 × 1/2 = 2,500万円(各人の基準取り分)
【具体的相続分】
- A:2,500万円(特別受益なし)
- B:2,500万円-1,000万円=1,500万円
特別受益の主張には「立証」が必要です
注意が必要なのは、特別受益を主張する場合、単に「不公平だ」「優遇されている」と感じるだけでは不十分ということです。
🔍 特別受益の立証責任
特別受益は、主張する側(通常は他の相続人)に立証責任があります。
つまり、相手方が「生計の資本」として贈与を受けたことなどを立証する必要があるのです。
まとめ|特別受益を正しく理解して、円満な相続を実現するために
- 特別受益は、被相続人から相続人への財産の一部の前渡しとされる特別な利益です。
- 「遺贈」「婚姻・養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」のみに限定されます。
- 実際の遺産分割では、「みなし相続財産」を基にして、具体的な取り分を公平に計算します。
- 特別受益を主張するには、その該当性と金額についての立証が必要です。
- 評価は相続開始時の時価で行う点にも注意が必要です(相続税とは異なります)。
相続についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください
当司法書士・行政書士事務所(東京都文京区湯島)では、相続手続き・遺産分割・遺言書作成等に関するサポートを、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県エリアを中心に承っております。
相続問題についてお悩みの方はぜひ当事務所にご相談ください。丁寧にサポートさせていただきます。
ただし、司法書士が取り扱える相続業務は、あくまで相続支援業務(手続き支援・書類作成等)に限られます。
そのため、相続人同士の間で深刻な争いごとや対立が生じている場合(=法律上の「紛争状態」)*は、司法書士が関与できないことがあります。
そのような場合には、当事務所ではなく、弁護士事務所へのご相談をおすすめすることになります。ご理解ください。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。