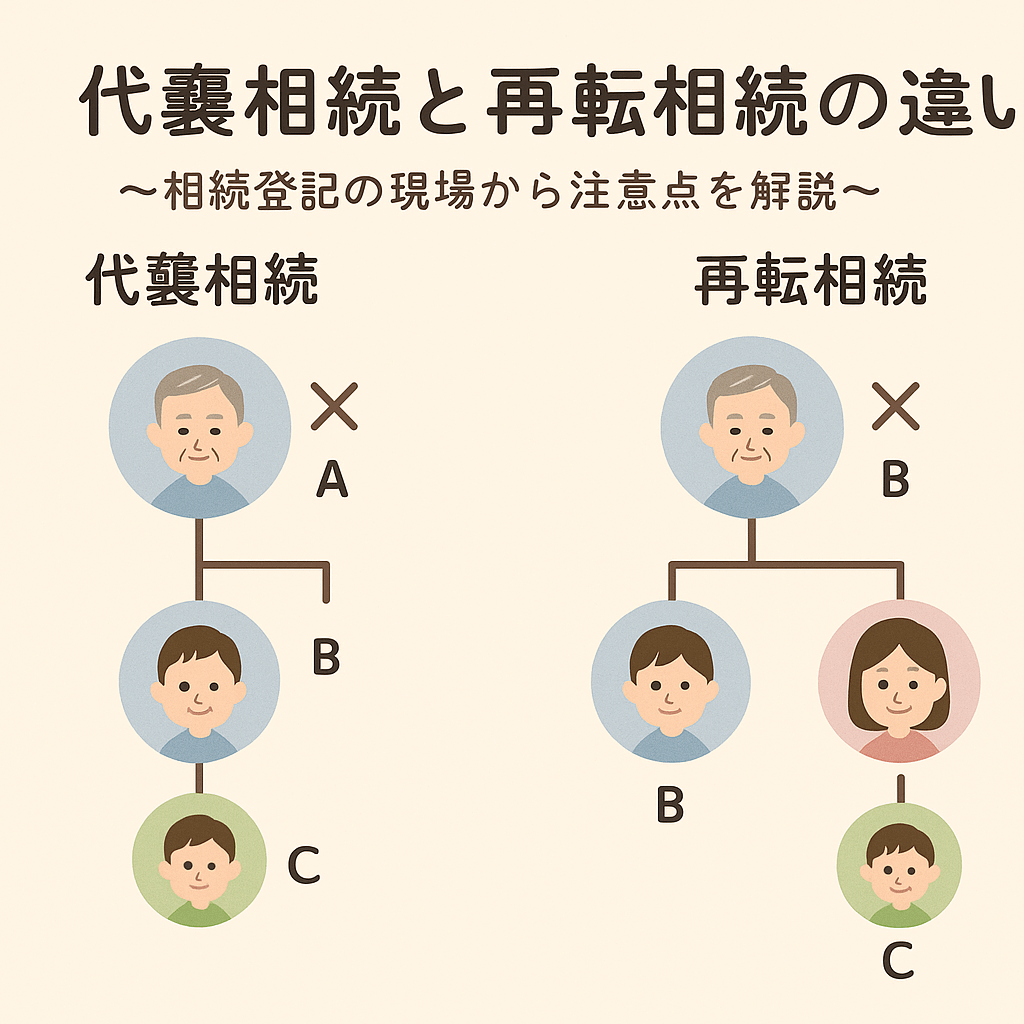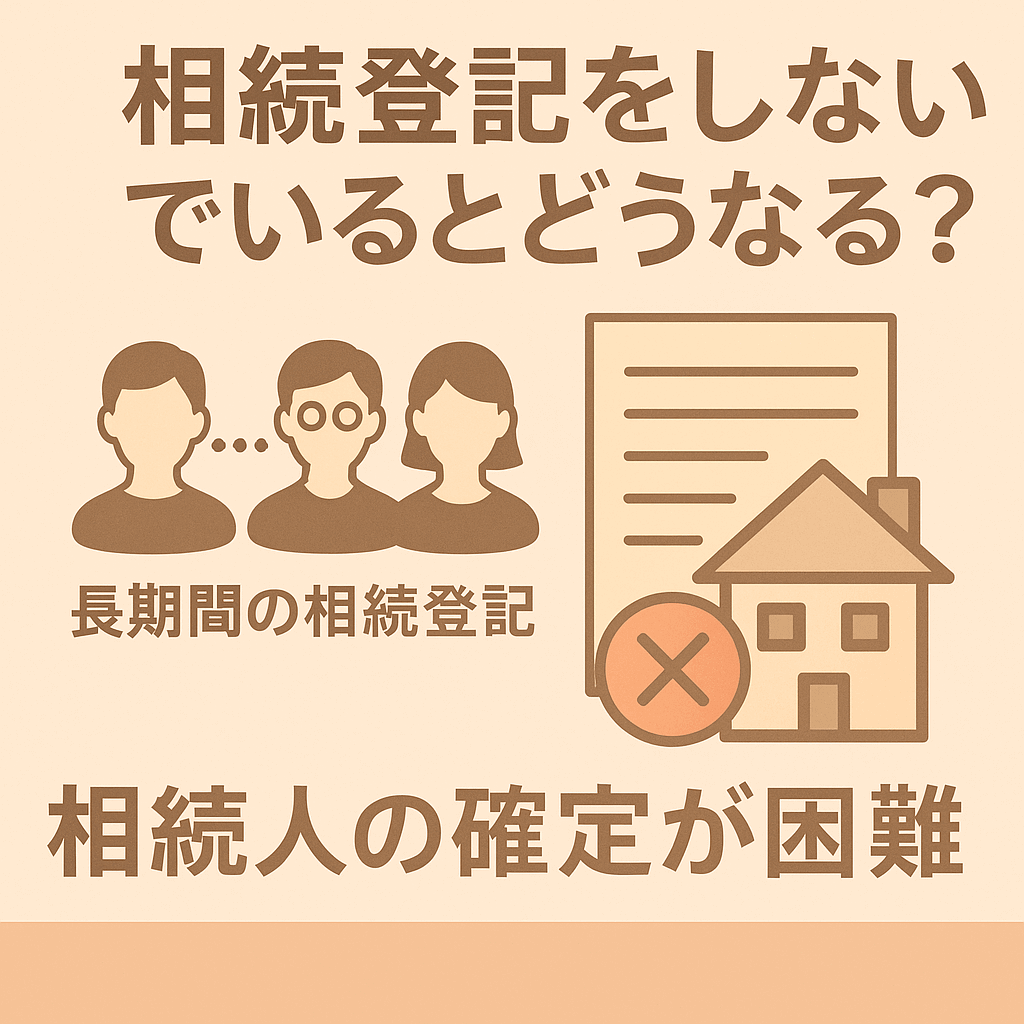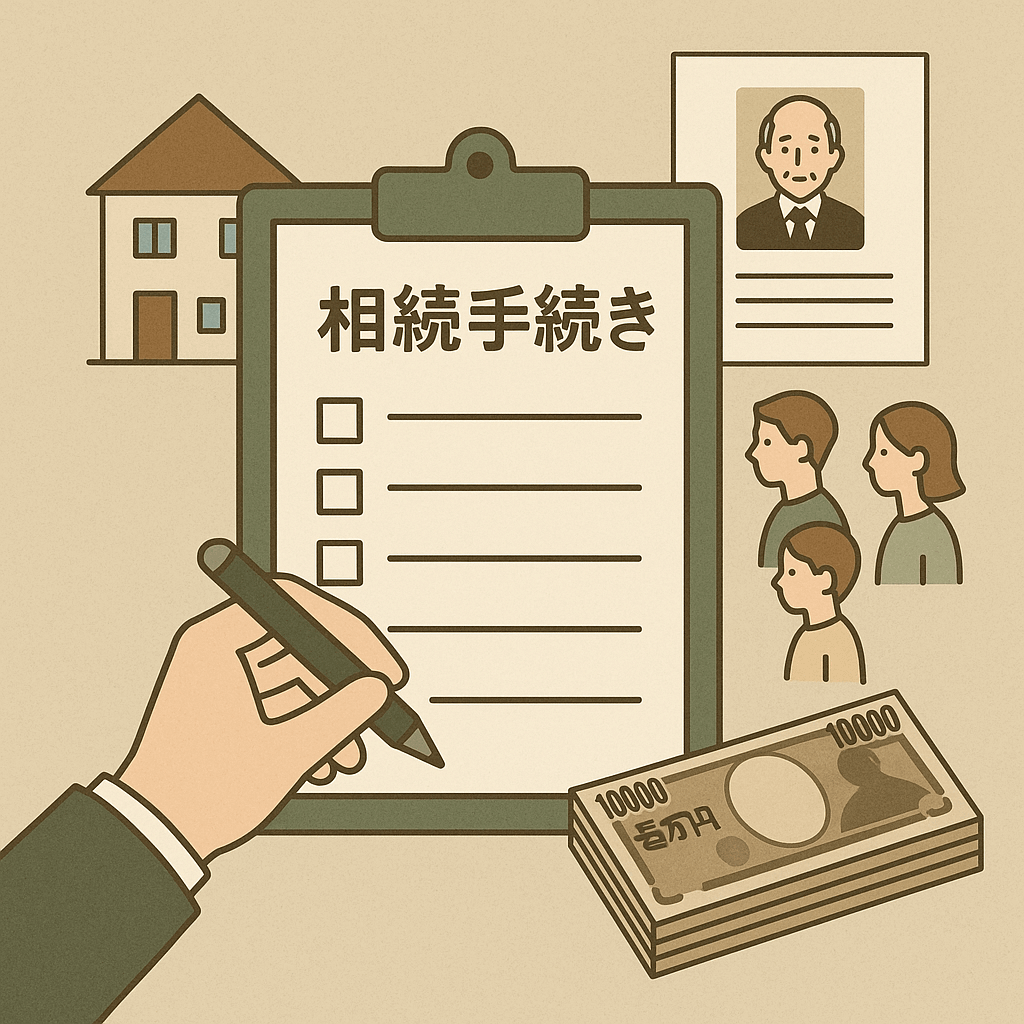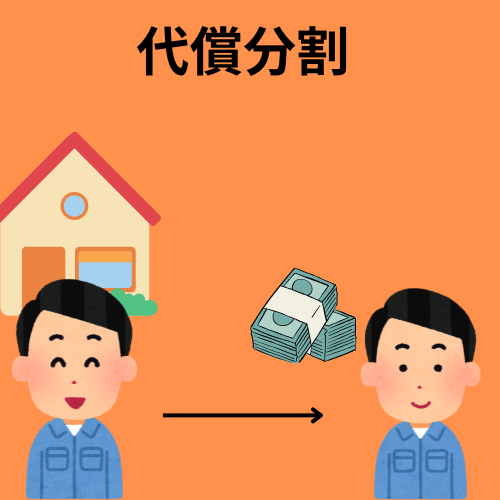ご主人の遺品整理中に見つかった「自筆の遺言書」――開封していいの?
「父の死後、タンスの引き出しから遺言書が見つかったんだけど、開けて良いのかわからない?」
こういった不安を感じる方は少なくありません。
相続は人生でそう何度も経験することではないため、「どうすればいいの?」と戸惑ってしまうのも無理もありません。
この記事では、「遺言書の検認」とは何か、どのように手続きを進めればよいのかを、司法書士行政書士栗栖英俊がわかりやすく解説します。
「検認」とは?自筆証書遺言を見つけたときに必要な家庭裁判所の手続き
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html(裁判所ホームページより)
また、自筆で書かれた遺言書(=自筆証書遺言)と、公正証書で作成された遺言書(=公正証書遺言)では扱いが異なります。
自筆証書遺言には検認が必要ですが、公正証書遺言には検認は不要です。
また、自筆証書遺言でも、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、裁判所の検認は不要です。
遺言書の検認手続きの流れ
遺言書の検認は、通常以下のような流れで進みます(上記裁判所ホームページを参照しています)。
① 検認期日の通知
遺言書の検認を申し立てると、家庭裁判所から相続人全員に「検認を行う日(=検認期日)」が通知されます。
検認期日に出席するかどうかは相続人それぞれの自由で、全員が出席しなくても手続きは進行します。
ちなみに、申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。
🔹申立人は、以下のものを持って裁判所へ出向きます:
- 遺言書の原本
- 申立人の印鑑
- その他、裁判所から指示された書類等
② 遺言書の開封と確認(検認)
検認期日には、申立人が遺言書を裁判所に提出し、出席した相続人の立ち会いのもと、裁判官が遺言書を確認します。
もし遺言書が封印された状態で保管されている場合は、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと開封されます。これは民法で定められたルールです。
③ 検認済証明書の申請
検認が終わったら、実際に相続手続きを進めるためには、遺言書に「検認済証明書」を添付する必要があります。
証明書の交付を受けるには:
- 遺言書1通につき 150円分の収入印紙
- 申立人の印鑑
を用意して、家庭裁判所に申請します。

遺言書の検認手続に必要な書類について
遺言書の検認を家庭裁判所に申し立てる際には、いくつかの書類を用意する必要があります。
まず、申立人自身の戸籍謄本(全部事項証明書)を市役所などで取得します。
あわせて、遺言者(被相続人)の戸籍も、除籍謄本や改製原戸籍を含めて、出生から死亡までの一連の記録がわかるものすべてを揃える必要があります。
また、すべての相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)も提出書類に含まれます。
これらに加え、検認の対象となる遺言書の原本を、家庭裁判所から指定された検認期日に持参します。
なお、遺言書がすでに開封されている場合には、申立て時にその写しを添付する必要があります。
遺言書の開封の際に、「これが本当に遺言者の筆跡なのか」という筆跡鑑定のようなものは行いません。
一応家庭裁判所の裁判官は、相続人に「本人の筆跡ですか?」「問題ないですか?」と言った趣旨の話はするのですが、その程度です。
もし、本人の筆跡でないと思う相続人がいる場合は、証拠を出して訴えを提起する必要があります。
遺言書の検認を行わなかった場合のリスクとは?
遺言書の検認を行わなかった場合のリスクとして、考えられるものは以下のとおりです。
① 遺言書を使った相続手続きができない
遺言に基づく所有権移転登記では、遺言書が検認を受けていることが必要となります。
また、預貯金の解約などにおいても、検認を受けた遺言書を要求されます。
このように、検認を受けた遺言書が要求される場面は多いため、遺言執行手続きを速やかに行うためには、検認が必要と言えます。
② 勝手に開封した場合、過料の対象になることも
封のされた遺言書を、家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、民法により「5万円以下の過料」に処される可能性があります(民法1005条)。
③ 偽造や隠匿を疑われ、相続権を失うリスクも
遺言書の存在を他の相続人に知らせず、長期間保管したり、提出を怠った場合、「遺言書の隠匿」として相続欠格に該当する可能性もあります(民法891条5号)。
相続欠格になれば相続権を失うことになります。
また、他の相続人から「遺言書の内容を書き換えたんじゃないの?」などと不信感を持たれ、相続トラブルの原因にもなりかねません。
これらのトラブルを避けるためにも、検認手続は速やかに行うべきです。
よくあるご質問(FAQ)
- 自筆の遺言書がある場合、必ず検認が必要ですか?
-
はい。封がされている・されていないに関わらず、自筆証書遺言は検認が必要です。ただし、公正証書遺言には検認は不要です。
- 勝手に遺言書を開封してしまったらどうなりますか?
-
5万円以下の過料が科される可能性があります。また、他の相続人とのトラブルの原因にもなります。
- 検認をしないと遺言書は無効になりますか?
-
いいえ、検認をしないことで遺言書が「無効」になるわけではありません。しかし、相続手続きでは、検認手続きのなされた遺言書の提出が求められる場合が多いため、相続手続きが速やかに行われないことになります。
- 遺言書が2通あった場合はどうすれば?
-
抵触する部分については、遺言の撤回をしたものとみなされ、後の日付の遺言が有効となります。抵触していない部分については、前の遺言書も有効ですので、両方を家庭裁判所に提出して、検認を受ける必要があります。
個人的には、トラブル防止のため、遺言書を新しく作成した場合は、前の遺言書は破棄しておくことをお勧めします。
遺言書の検認手続きは相続手続きの大切な第一歩です
自筆の遺言書を見つけたとき、「どうすればいいの?」と不安に思う気持ちは当然です。
しかし、家庭裁判所で検認を受けることで、遺言書を問題なく活用できるようになります。
当事務所では、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を中心に、相続に関する相談を受け付けています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。