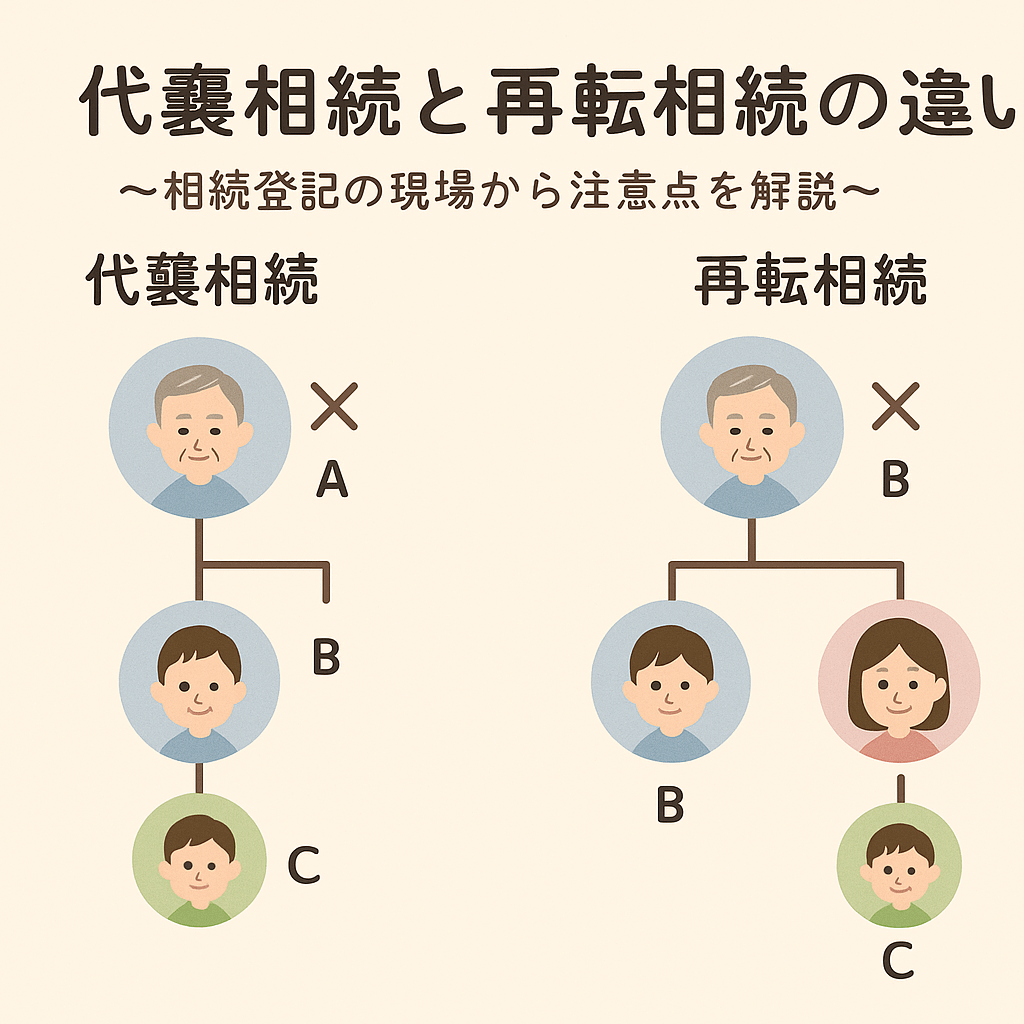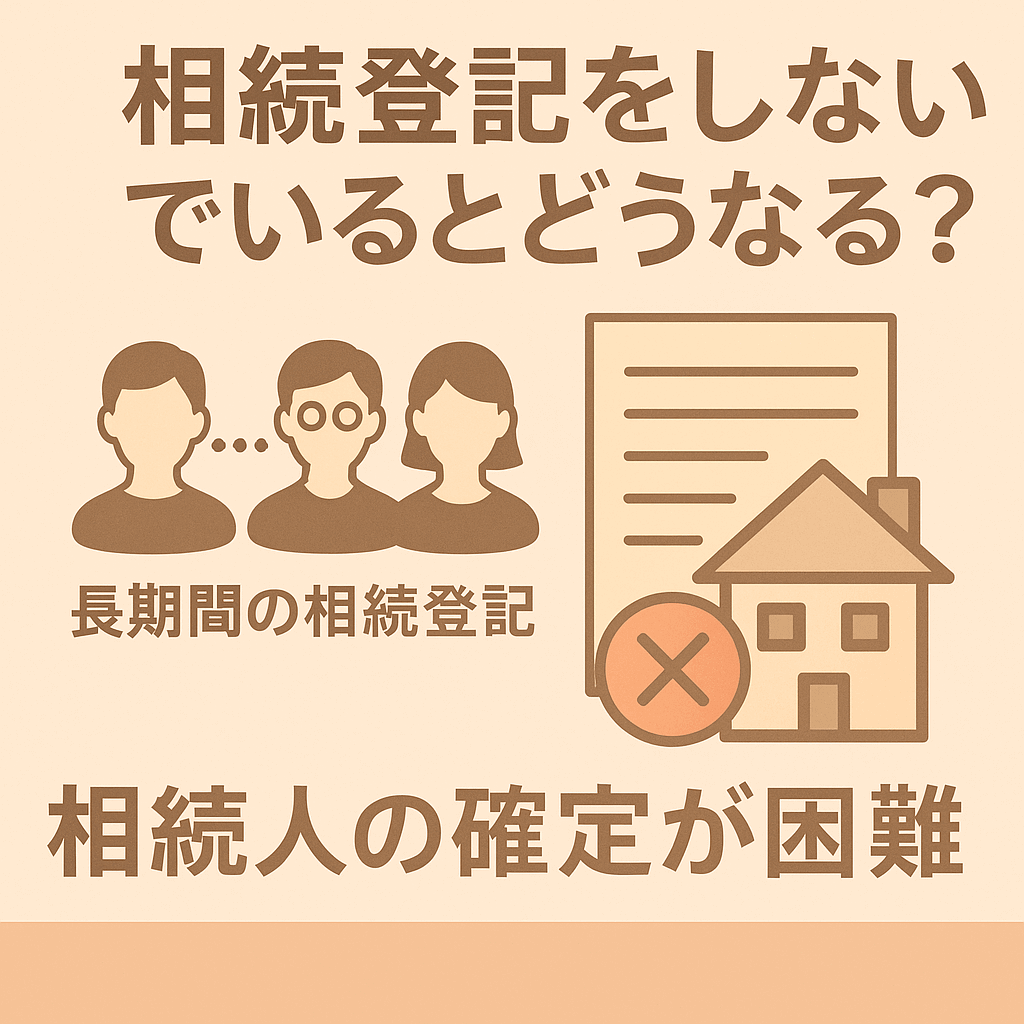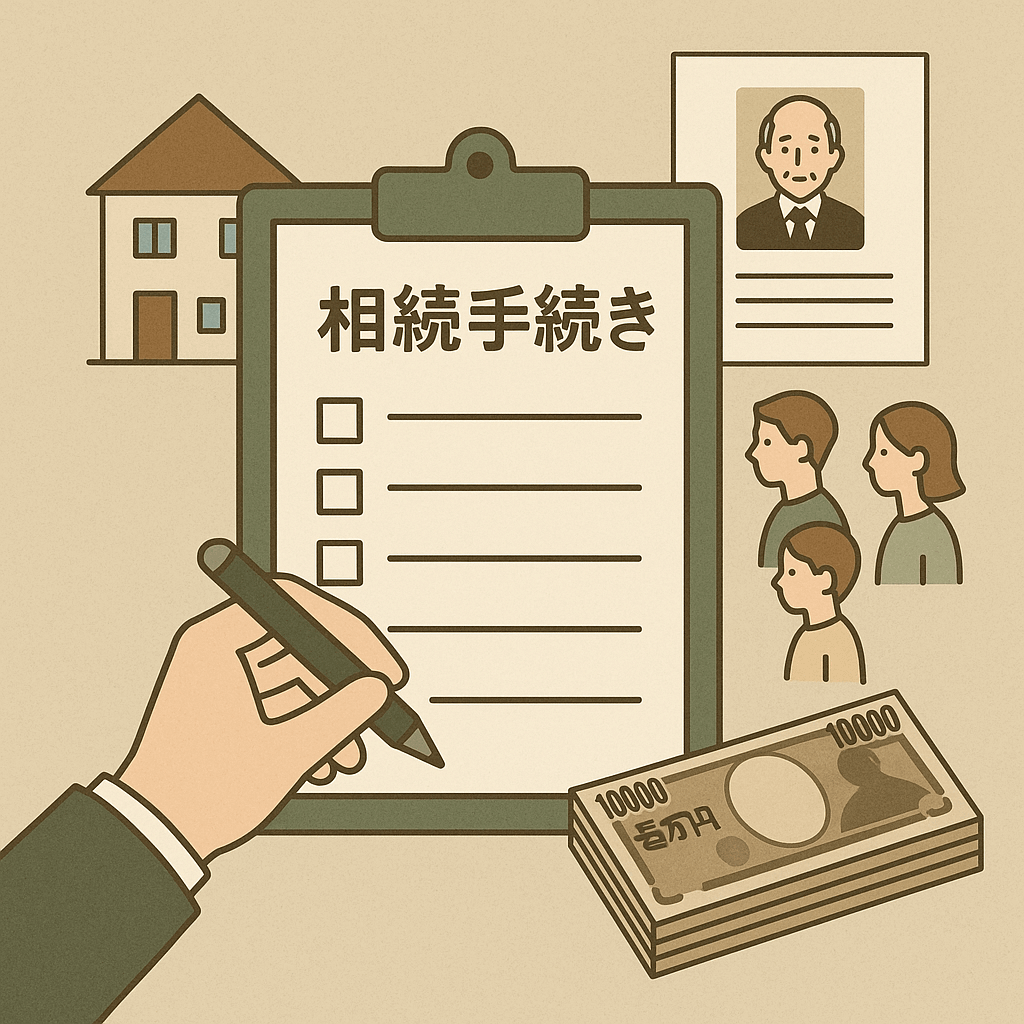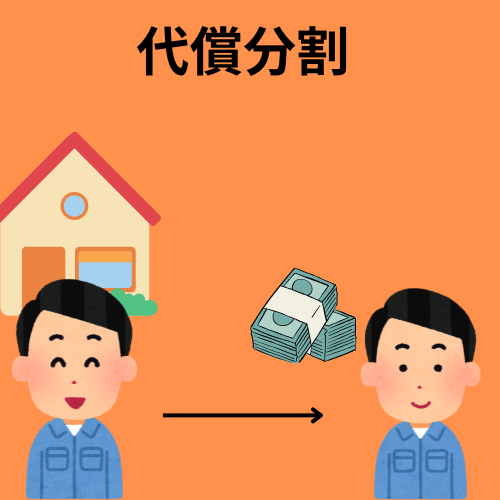「相続税ってうちにも関係あるの?」「税金がかかるとしたら、いくらぐらいになるの?」
相続が発生したとき、まず気になるのが相続税がかかるかどうか、そしてどのくらいかかるのかという点です。
相続税は複雑なイメージがありますが、この記事では「基礎控除」と「大まかな計算方法」を中心に、相続税の仕組みについて、FP2級を持ちAFP登録をしている司法書士栗栖英俊がわかりやすく解説します。

とくに東京都内、千葉県、埼玉県、神奈川県といった都市部にお住まいの方は、不動産の価値が高いため、相続税の対象になりやすい点にも注意が必要です。
相続税がかかる人はどのくらい?東京都の実態
国税庁の統計では、全国の相続件数のうち相続税が課税された割合は約8〜9%。
一方、東京都では、令和4年度に相続税が課税された方は18.7%もいます。
👉日税ジャーナルオンラインより
これは、都心部では土地やマンションの評価額が高いため、現金が少なくても基礎控除額を超えてしまうケースが多いためです。
つまり、
「今は関係ない」と思っていても、将来的に相続税の対象となる可能性が十分にある
ということです。
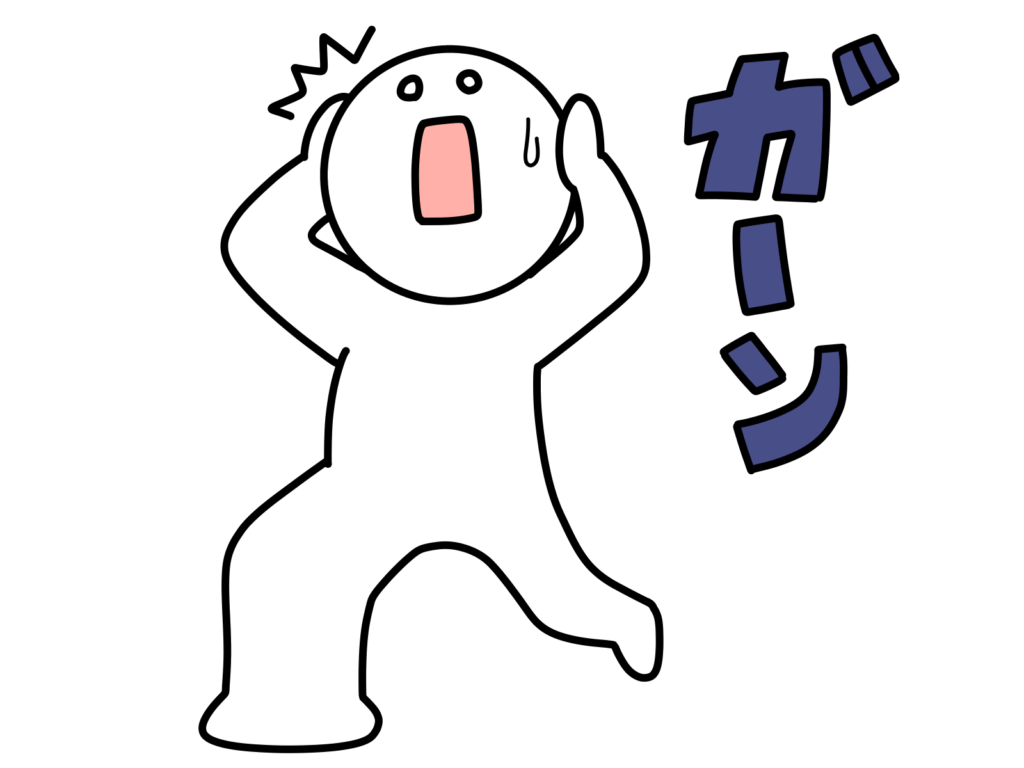
相続税の基礎控除とは?申告が必要かを判断するライン
相続税は、財産のすべてに課税されるわけではありません。
まずは**「基礎控除」という非課税枠**を差し引いた上で、残った額に対して課税されます。
■ 基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:配偶者と子1人が相続人 →
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
この金額を遺産総額が超える場合に限って、相続税の申告・納税が必要です。
【重要】相続税の基礎控除では相続放棄しても相続人の数に含まれる?
はい、相続放棄をした人も、「基礎控除額の計算においては法定相続人の数に含まれます」。
たとえば、子が3人いてそのうち1人が相続放棄した場合でも、基礎控除の計算上は「相続人3人」として計算されます。
ただし、相続税の納税義務は実際に遺産を取得した人のみに生じます。
相続税の計算方法(ざっくり把握)
実際の相続税額は個別のケースで異なりますが、以下のようなステップで計算されます。
【相続税の計算の流れ】
- 相続財産の合計(不動産、預貯金、株、生命保険など)
- 債務・葬儀費用を差し引く
- 基礎控除を差し引いて「課税遺産総額」を出す
- 法定相続人の数で按分し、税率を適用
- 控除後の合計額を各相続人の取得割合で割り振る
詳しくは、国税庁のサイトでご確認ください。
相続税の税率表(2024年度)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~1,000万円 | 10% | なし |
| ~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| ~5,000万円 | 20% | 200万円 |
| ~1億円 | 30% | 700万円 |
| ~2億円 | 40% | 1,700万円 |
| ~3億円 | 45% | 2,700万円 |
| ~6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
これも、国税庁のサイトで確認できます。
あくまで、2024年度のものであることにご注意ください。
相続税の簡易シミュレーションも活用を
「うちは相続税がかかる?」と不安な方は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で簡易診断が可能です。
※当事務所では税務相談や相続税申告の業務は行っておりません。
相続税の計算や節税対策については、税理士にご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
- 相続放棄をしても、基礎控除の相続人の数に入るの?
-
はい、相続放棄をしても「法定相続人」として数えます。ただし、実際に遺産を受け取らないので相続税の納税義務はありません。
- 相続放棄をしていたのですが、相続税の支払いをしてしまいました。どうすればいいですか?
-
この場合は、本来の相続税の支払い人に求償できるとされています。
- 不動産だけでも相続税がかかることはありますか?
-
あります。東京都やその近郊では、土地の評価額が高いため、不動産だけで基礎控除を超えてしまうこともあります。
- 相続税がかからなくても申告は必要?
-
基礎控除の範囲内であれば、申告自体も不要です。ただし、「小規模宅地等の特例」などを使う場合は申告が必要です。
- 申告しなかったらどうなるの?
-
本来申告すべきだった場合には、加算税や延滞税が課される可能性があります。早めの確認が大切です。
- 生前贈与で対策できるの?
-
生前贈与も節税の一つですが、贈与税や相続時精算課税制度との関係があるため、税理士への相談が不可欠です。
- AFP登録をしているそうですが、そちらの事務所では相続税についての相談を受け付けているのでしょうか?
-
私はFP2級を所持しており、AFP登録もしていますが、税金に関する細かな相談は税理士でないのでお受けすることはできません。あくまで制度の概要をお伝えしているとお考え下さい。
税金に関する詳しい相談は税理士にお願いします。
相続に関するご相談は文京区湯島の「栗栖司法書士行政書士事務所」へ
今回の記事では、相続税に関する一般的な記事を書かせていただきましたが、相続の問題が発生した場合相続人の確定や不動産の調査、登記など、司法書士による手続きのサポートが必要になってきます。
「相続登記をしたい」「相続人が分からない」「遺言書を確認してほしい」
そういったお悩みは、ぜひ当事務所までご相談ください。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。