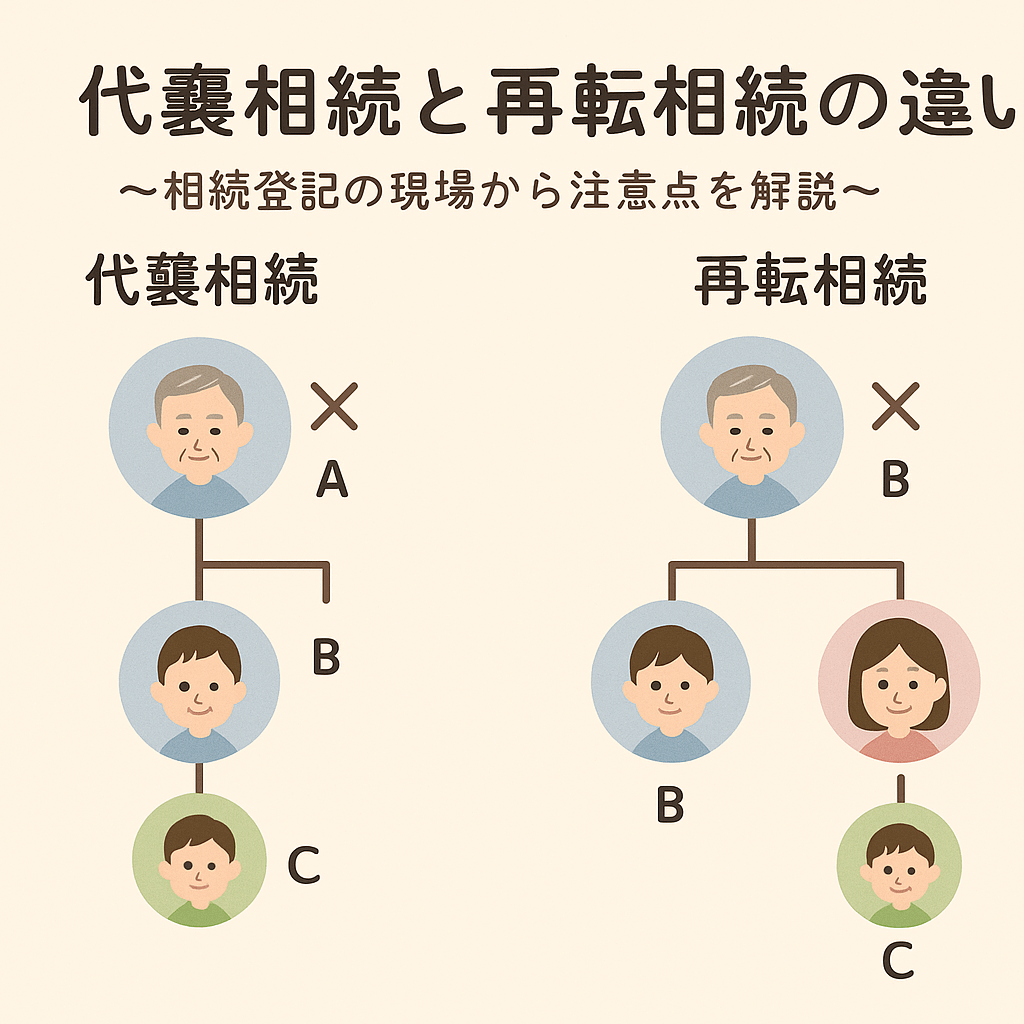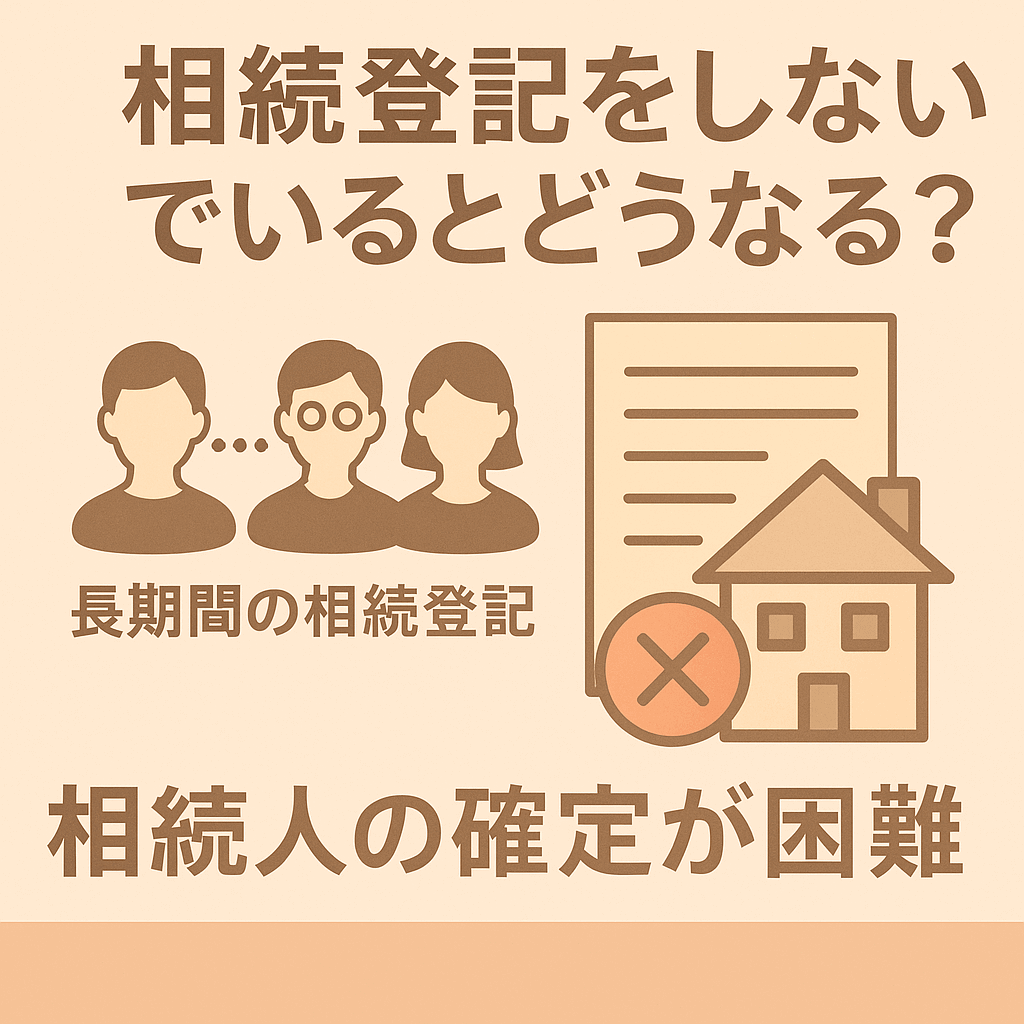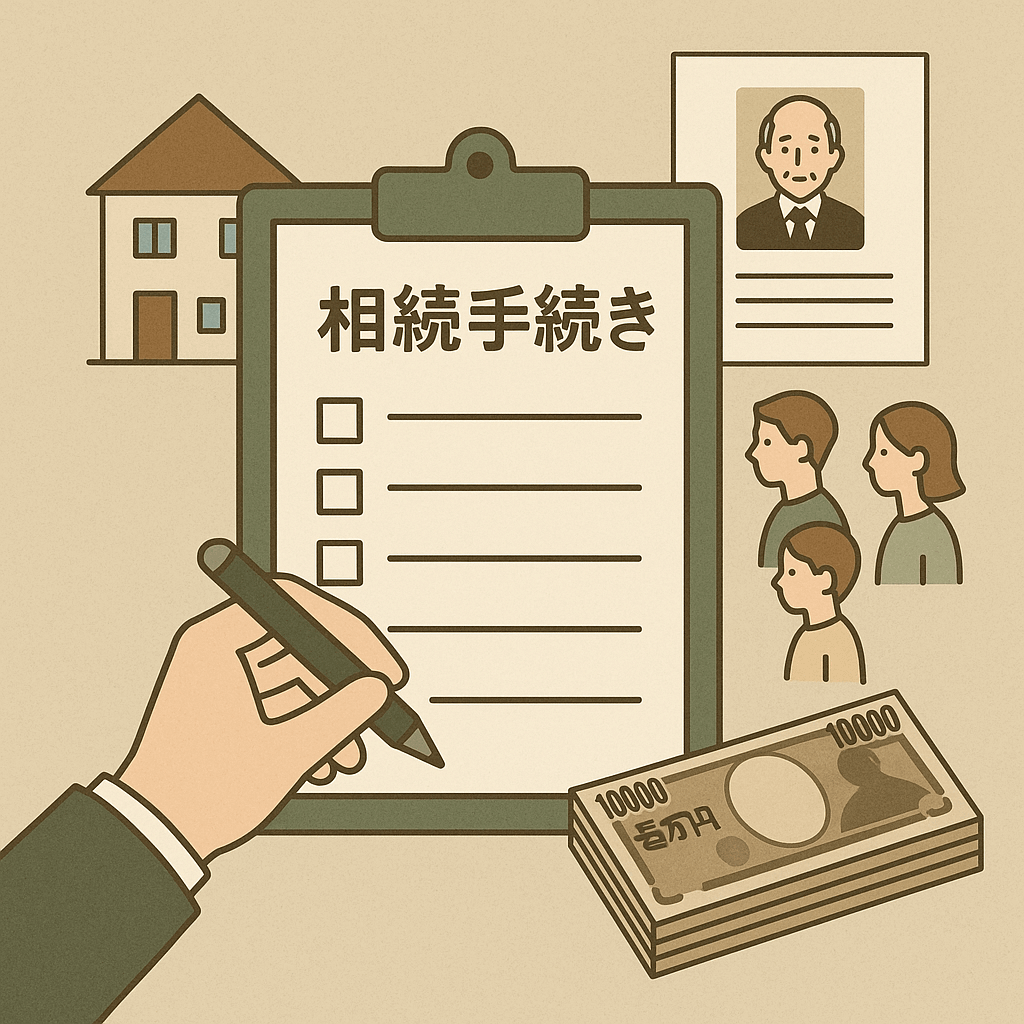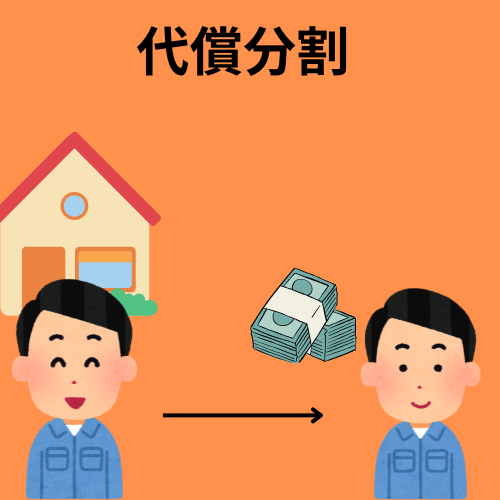配偶者居住権とは?なぜ注目されているのか
2020年4月、民法改正により新しく創設された制度に「配偶者居住権」があります。
これは、被相続人が亡くなった後も、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権が創設されるまでは、自宅を相続するには「不動産そのものの所有権」を取得する必要がありました。
この場合、不動産が相続財産の多くを占める場合、配偶者が自宅を相続すると、預貯金など他の財産を受け取れないことがありました。
そうした不公平を是正し、高齢の配偶者が安心して暮らし続けられるように設けられたのが、配偶者居住権です。
第1章:配偶者居住権とは?基本的な仕組みを解説
■ 配偶者居住権の定義
配偶者居住権とは、「配偶者が、亡くなった被相続人が所有していた建物に、自分が亡くなるまで(または一定期間)住み続けることができる権利」です。
これは不動産の「所有権」ではなく、「使用する権利」だけを認めるもので、財産評価上の金額も抑えられるという特徴があります。
そのため、他の相続人も相続により取得する金融資産の額は少なくなるものの、居住建物の所有権は確保されているため、配偶者死亡後、配偶者に別の相続人がいた場合でも、その居住建物の所有権者が建物全体を使用収益することがで切るというメリットがあります。
■ 配偶者短期居住権との違い
よく混同されがちなのが「配偶者短期居住権」です。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 根拠 | 遺言または遺産分割協議 | 民法の規定により当然に発生 |
| 期間 | 終身または一定期間 | 最長6か月程度 |
| 登記の必要 | あり | 登記できない |
| 相続税評価 | 評価あり | 評価なし |
短期居住権は、被相続人が配偶者に居住建物を相続させない意思を表示させた場合であっても、被相続人の死後に急に住む場所を失うことがないように、一時的に住み続ける権利を保障する制度です。
一方、配偶者居住権は長期的・恒久的な住居の安定を図る趣旨から、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を満たした場合に、被相続人が死亡した後も、配偶者が、賃料の負担をすることなくその建物に住み続けることができるようにしたものです。
第2章:配偶者居住権の成立要件とは?
配偶者居住権は、誰でも自動的に取得できるものではありません。法律に基づき、いくつかの要件を満たす必要があります。
■ 主な成立要件
- 配偶者が被相続人の所有する建物に居住していたこと
配偶者が生前にその建物に実際に住んでいたことが前提です。 - 配偶者居住権の取得が、以下のいずれかで認められていること
- 遺産分割で配偶者居住権を設定
- 遺言(遺贈)による指定
- 家庭裁判所の審判
- 遺産分割で配偶者居住権を設定
このような要件を満たすことで初めて、配偶者居住権を設定することができるようになります。
■ よくある誤解と注意点
借地上の建物や借家には適用されない
対象となる建物は被相続人が所有していたものに限られます。そのため、借地に建てられた建物や賃貸住宅など、被相続人が所有していない建物には配偶者居住権は認められません。
被相続人の死後に初めて居住した配偶者は対象外
被相続人の死亡後に初めて建物に住み始めた配偶者も、配偶者居住権の対象にはなりません。
配偶者居住権は、配偶者の被相続人の生前からの生活をそのまま保護するためのものです。
生前からその建物に実際に居住していたことが必要です。
適用されるのは、令和2年4月1日の相続から
配偶者居住権を設定できるのは、令和2年4月1日以降の相続からです。令和2年3月31日以前に相続が発生した場合は、配偶者居住権を設定することはできません。
遺産分割が令和2年4月1日以降になされても、同様になります。
重要なところなので注意が必要です。
第3章:配偶者居住権の登記方法と必要書類
先ほども述べましたが、配偶者居住権を有効に主張するには、「登記」が不可欠です。登記によって第三者にもその権利が認められるようになります。
■ なぜ登記が必要なのか?
配偶者居住権は不動産に関する権利であるため、登記をしなければ法的に第三者に対抗できません。
たとえば、その建物が他の相続人名義で登記された場合、登記がなければ配偶者の権利は守られません。
こういったトラブルを避けるためには、配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続をする必要があります。
民法第1031条
① 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
■ 登記のタイミングと流れ
- 遺産分割協議や遺言書によって配偶者居住権が設定される
- 相続登記と同時に配偶者居住権の登記申請を行う
- 登記完了後、配偶者は正式に居住権を得る
注意が必要なのは、配偶者居住権の設定をする前に、相続や遺贈を原因とする所有権移転登記をする必要があるということです。
配偶者居住権が、被相続人名義のままで配偶者居住権の設定登記をすることはできないことに注意してください。
第4章:配偶者居住権の登記申請書
相続登記がなされた後に、遺産分割で配偶者居住権が設定された場合の申請書です。
登記申請書
登記の目的 配偶者居住権設定
原因令和2年7月8日遺産分割
存続期間令和2年6月1日から配偶者居住権者の死亡時まで
権利者 千葉県船橋市○○町〇番〇号 田中一郎
義務者 千葉県船橋市〇○町〇番〇号 田中芳男
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報(登記義務者のもの) 印鑑証明書(登記義務者のもの) 代理権限証明情報
(以下省略)
必要書類について
必要書類については以下の点に注意が必要です。
まず、配偶者居住権が成立するには、配偶者が被相続人所有の建物に相続開始の時に居住していたことが必要になります。
もっとも、登記原因証明情報として、当該配偶者の住民票の写し等の提供を必要とせず、提供された報告形式の登記原因証明情報の中にその旨を記載すれば大丈夫です。
また、配偶者居住権を取得できる配偶者は、相続開始の時に法律上被相続人と婚姻をしていたものに限られます。
もっとも、登記原因証明情報として、被相続人の住民票の除票の写し等を必ず提供する必要はありません。
提供された報告形式の登記原因証明情報の中にその旨が明らかになっていれば足ります。
第5章:配偶者居住権の設定について専門家に依頼するメリット
配偶者居住権の設定について司法書士に相談するメリットとしては以下のようなものがあります。
書類の不備や手続きミスを防げる
配偶者居住権の登記は、専門的な知識が求められる手続きです。司法書士に依頼することで、書類の不備や手続きミスを防ぐことができ、安心して進められます。
相続登記との同時申請もスムーズにできる
また、相続登記とあわせて一括で申請することもできるため、手続きがスムーズになります。
相続税との兼ね合いも含めたアドバイスが得られる
さらに、相続税との関係もふまえて、全体的なアドバイスが受けられるのも大きなメリットです。もっとも、私はFP2級を取得しており、AFP登録をしていますが、アドバイスできるのはあくまで一般的な見解です。
相続税について詳しい説明を聞きたい場合は税理士に相談する必要があります。
第6章:配偶者居住権のメリット・デメリット
配偶者居住権は、制度として非常に有用ですが、すべての家庭にとって必ずしも「最適」とは限りません。ここではメリットとデメリットを整理してご紹介します。
■ 配偶者居住権のメリット
配偶者居住権のメリットは以下の通りです。
- 住み慣れた家に住み続けられる安心感
→高齢の配偶者にとって、住居の安定は何より重要です。住み慣れた家に住むことで精神的なストレスも顕現されます。 - 不動産以外の財産の取得が可能になる
→所有権と居住権を分けることで、住まいを守りつつ、配偶者は、預貯金など他の財産も取得できる可能性が高まります。 - 相続税の節税につながる可能性
→居住権の評価額は所有権に比べて低いため、相続税の総額を抑えられることがあります。
■ 配偶者居住権のデメリット
配偶者居住権には以下のようなデメリットがあります。
- 自由に売却・賃貸ができない
→居住権は使用に限定されるため、財産としての流動性はありません。 - 他の相続人との調整が難航することがある
→不動産の分け方に対する不満が生じ、遺産分割が長引く可能性もあります。 - 将来の相続(二次相続)への影響
→居住権が残っている不動産は、売却や処分がしづらいため、次世代の相続に支障をきたすケースもあります。
第三者に土地を売ろうとしても、配偶者居住権のついている土地の場合、買い取り手を見つけるのは困難です。
第7章:配偶者居住権を使うべきケースとは?
■ 配偶者居住権を使った方がよいケース
配偶者居住権を使ったほうがいいケースとしては以下のようなものがあります。
- 配偶者に収入がなく、家に住み続けたい場合
- 不動産が財産の大部分を占めており、預貯金を確保したい場合
- 他の相続人との関係が良好で、合意が得られる見込みがある場合
■ 配偶者居住権を使わないほうがよいケース
次に、配偶者居住権を使わないほうがいいケースは以下のようなものがあります。
- 不動産を将来的に売却したい、または活用したい場合
- 配偶者自身が不動産の所有を希望している場合(完全な所有権の取得)
- 他の相続人との間にトラブルの火種がある場合
終章:配偶者居住権の活用を検討するなら専門家へ相談を
配偶者居住権は、被相続人の死亡後も配偶者の生活を維持するために、非常に有効な制度ですが、適用条件や登記手続き、他の相続人との関係など、注意すべき点も多くあります。
そのため、制度の活用を検討されている方は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、以下のようなご相談に対応しています:
- 配偶者居住権を使ったほうが良いかどうか知りたい
- 登記の手続きや必要書類について確認したい
- 遺産分割協議でスムーズに話を進めたい
- 相続登記とあわせて配偶者居住権の登記も依頼したい
もし、配偶者居住権の設定をはじめとする相続問題についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号 03-3815-7828
お問い合わせフォームはこちら👉 https://kurisu-office.com/question/
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします。