「相続が発生したけれど、遺言書の内容に納得がいかない…」「遺産分割で自分の取り分が少ない気がする…」

もしあなたがそう感じているなら、「遺留分(いりゅうぶん)」という制度について知っておくことが大切です。
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、特定の相続人に法律で保障されている最低限の取り分のことをいいます。たとえ遺言書に「一切相続させない」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は、一定の財産を受け取ることができるのです。
この記事では、遺留分の基本的な仕組みから、実際に遺留分侵害額請求を行う方法、注意点、そして最近の法改正までを、東京都文京区湯島の司法書士がわかりやすくご説明いたします。
1. 遺留分とは?最低限保障される相続人の権利
1.1 遺留分の目的
遺留分制度は、被相続人の意思を尊重しつつ、残されたご家族の生活を守るために設けられた制度です。
例えば、配偶者や子どもが相続で全く財産をもらえないような遺言書があった場合でも、一定の財産を請求できる権利が保障されています。

1.2 遺留分を持つ人は誰?
法律上、遺留分が認められるのは以下の方々です。
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人。養子も含む)
- 直系尊属(子がいない場合の父母・祖父母など)
※兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分はありません。
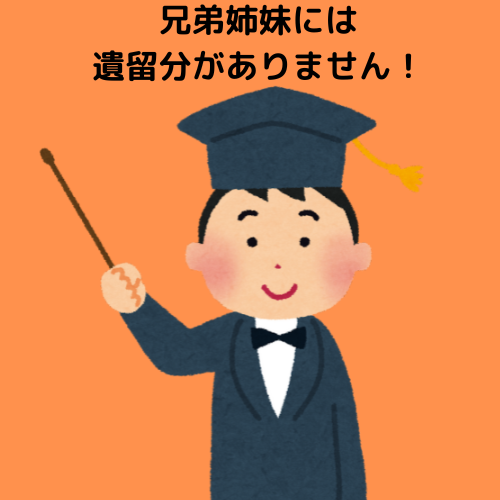
1.3 遺留分の割合について
遺留分の割合は相続人の組み合わせによって変わります。
- 配偶者と子がいる場合:遺産全体の1/2が遺留分。配偶者1/4、子は人数で1/4を分け合います。
- 子のみの場合:遺産全体の1/2(均等に分けます)
- 配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者1/3、直系尊属1/6
- 直系尊属のみの場合:全体の1/3
1.4 計算例
遺産総額が5,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合:
- 遺留分総額:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
- 配偶者の遺留分:1,250万円
- 子ども1人あたり:625万円
2. なぜ遺留分が重要なのか?
2.1 遺言書があっても請求できる
たとえ遺言書で「相続させない」とされていても、遺留分を有する相続人は、侵害された分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求)。
2.2 公平性の確保
長男だけに多く贈与されていたケースなどでは、他の相続人は不公平に感じることがあります。遺留分制度はそうした場合のセーフティネットになります。
2.3 経済的な保障
遺された配偶者や子どもの生活を守る目的もあります。
3. 遺留分侵害額請求の時効について
遺留分侵害額請求は「いつまでに行うか」という期限が定められており、注意しないと権利がなくなってしまうことがあります(民法1048条)。

【1】まずは「短い期限(1年)」に注意
遺留分を侵害された相続人が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって請求できなくなってしまいます。
この1年という期間はとても短いため、少しでも「おかしいな」と思ったら、早めに専門家に相談することが大切です。
【2】たとえ知らなくても「10年」で権利が消えることも
上記とは別に、相続が始まってから10年が経つと、その時点で自動的に遺留分の請求ができなくなります。
【3】請求して「お金の支払いを求める」ことになった場合にも時効があります
もし遺留分の請求をして、お金で解決することになった場合には、今度はその「お金を請求する権利」に対して、別の時効が始まります。
その時効は、
- お金を請求できると知った時から 5年
または - 実際に請求できるようになった時から 10年
いずれか早い方の時点で時効が成立します。
※なお、2020年4月1日より前に請求した場合は、10年が時効の目安になります。

4. 遺留分請求の注意点
4.1 感情的な対立に注意
円満な解決を目指すには、感情的な対立を避けましょう。
4.2 証拠を揃える
遺産の内容や評価額を証明する資料を集めておきましょう。
4.3 専門家に相談する
手続きや計算が複雑な場合は、司法書士や弁護士に相談するのが安心です。
4.4 生前贈与・特別受益の扱い
遺留分を計算する際には、被相続人が亡くなる前に行った贈与や、特定の相続人が特別に受けた利益(特別受益)も考慮されます。
これについては、民法1043条が改正され、遺留分を算定するための財産の価額について、より明確に定められました。
改正後の民法1043条第1項では、
「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」
とされています。
つまり、遺留分の計算にあたっては、被相続人が死亡時点で持っていた財産だけでなく、生前に贈与した財産(特別受益も含む)も加えて総額を出し、そこから借金などの債務を差し引いて、基礎となる遺産総額を算定します。
たとえば、生前に長男だけに不動産を贈与していた場合などは、その不動産の価額も相続財産に加算され、遺留分の計算に反映されることになります。
これにより、特定の相続人だけが得をするような偏った相続を防ぎ、他の相続人の遺留分を正しく守ることができます。

5. 法改正による変更点(2019年)
2019年7月1日に相続法が改正され、遺留分制度にも大きな変更がありました。以下にそのポイントをまとめます。
- 名称の変更:これまでの「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」となり、より実態に即した用語となりました。
- 請求の方法の変更:従来は遺贈や贈与された財産そのものを返還請求できましたが、改正後は原則として「金銭」での請求に一本化されました。
- 適用時期:この法改正は2019年7月1日以降に開始された相続に適用されます。それ以前の相続には旧法が適用されるため注意が必要です。
この改正により、たとえば遺産が不動産しかない場合でも、現物の返還を求めるのではなく、金銭での請求ができるようになり、より柔軟な解決が可能となりました。
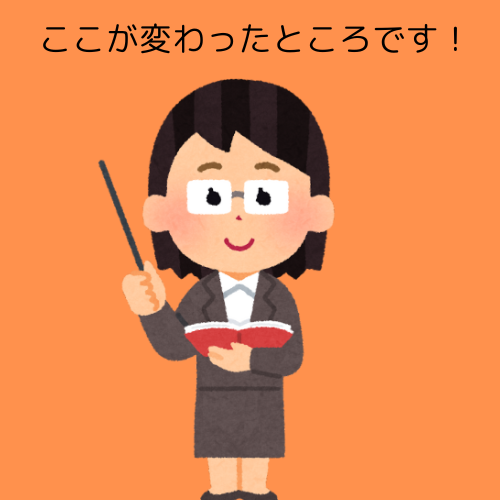
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 遺留分の請求期限は? A. 知った時から1年、または相続開始から10年のいずれか早い方です。
Q2. 遺留分を放棄できますか? A. 相続開始前は家庭裁判所の許可が必要。開始後は自由に放棄できます。
Q3. 遺産が不動産しかない場合は? A. 金銭で請求できます。不動産そのものを渡す必要はありません。
Q4. 何から始めればいい? A. 財産調査と遺留分の試算を行い、必要であれば司法書士などに相談を。
7. まとめ
遺留分は、相続人の権利を守るための重要な制度です。法改正により請求方法も変わりましたので、正確な知識が必要です。少しでも気になる点があれば、お気軽にご相談ください。
当事務所(文京区湯島)では、東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県を中心に相続に関するご相談を承っております。
113-0034
東京都文京区湯島四丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
電話番号 03-3815-7828
なお当事務所は予約制です。事前に電話かメールでの予約をお願いします

