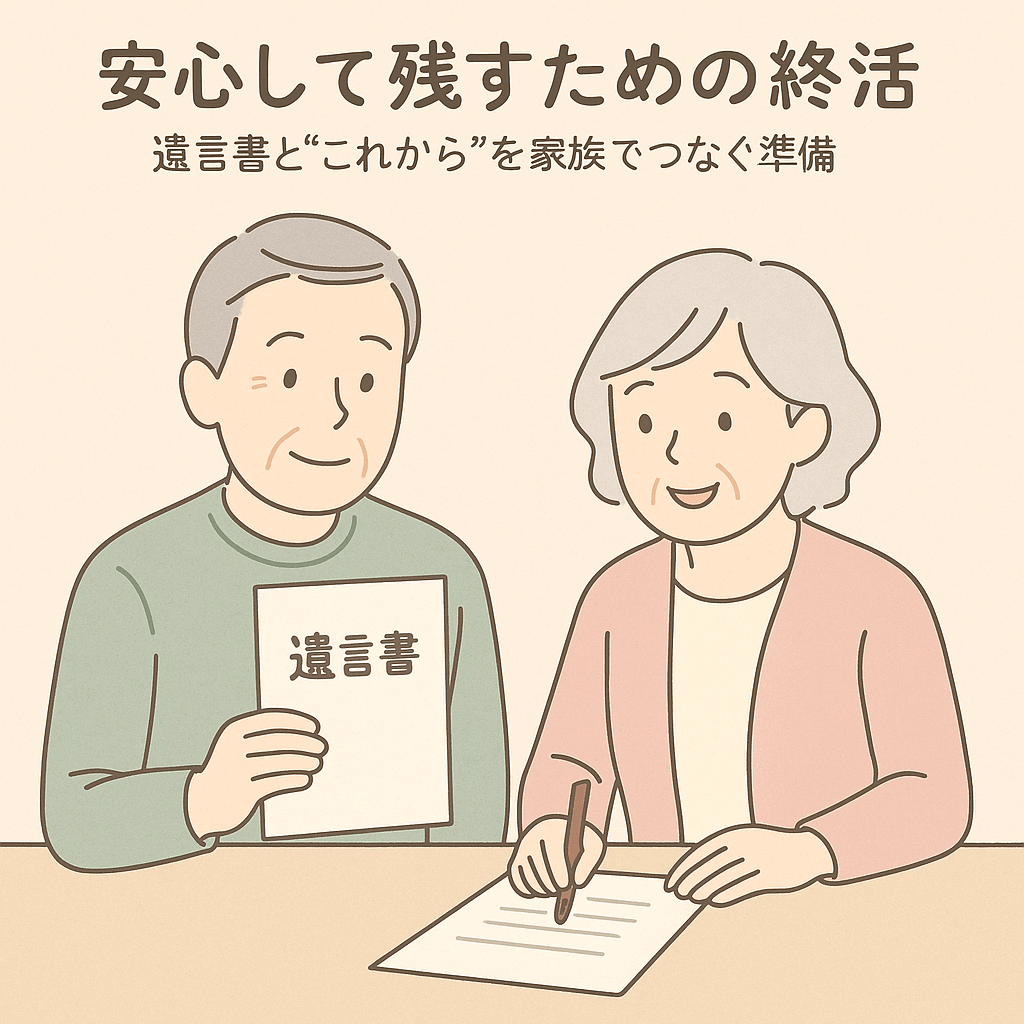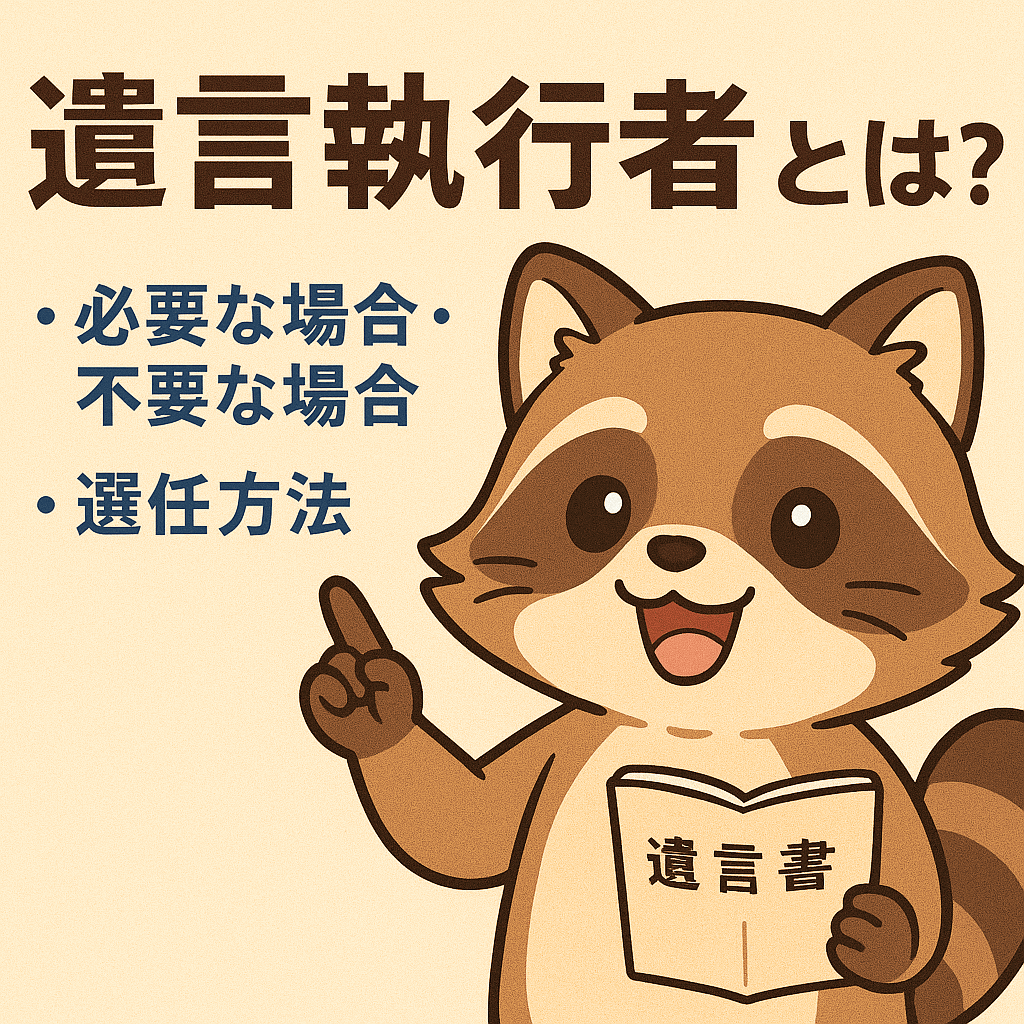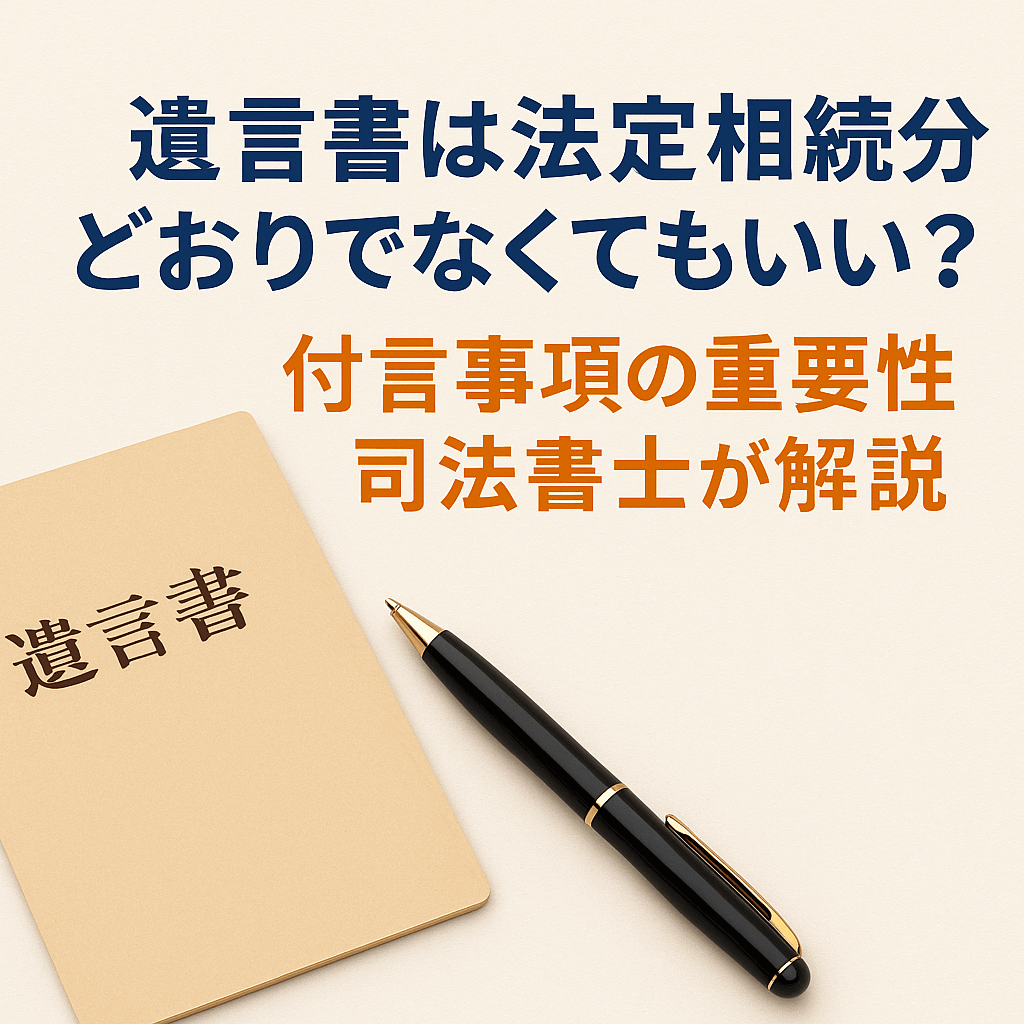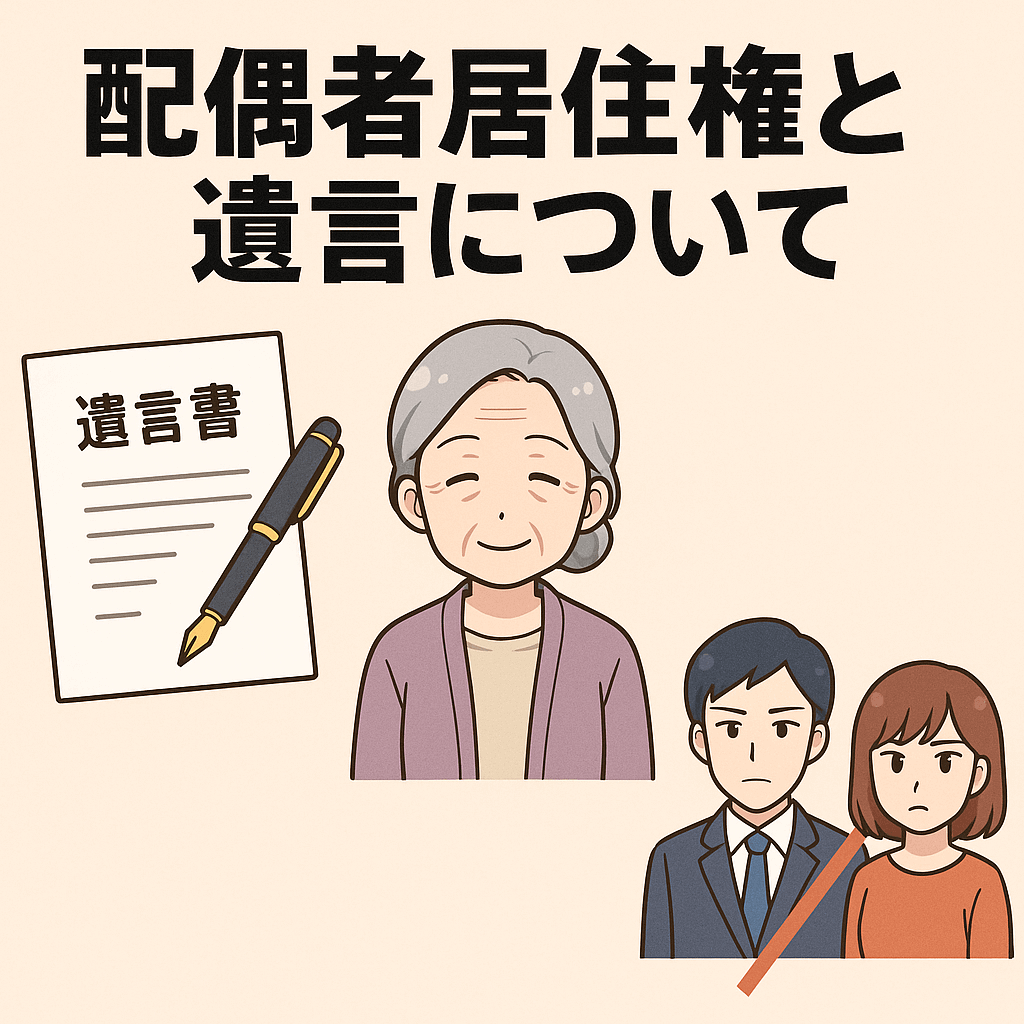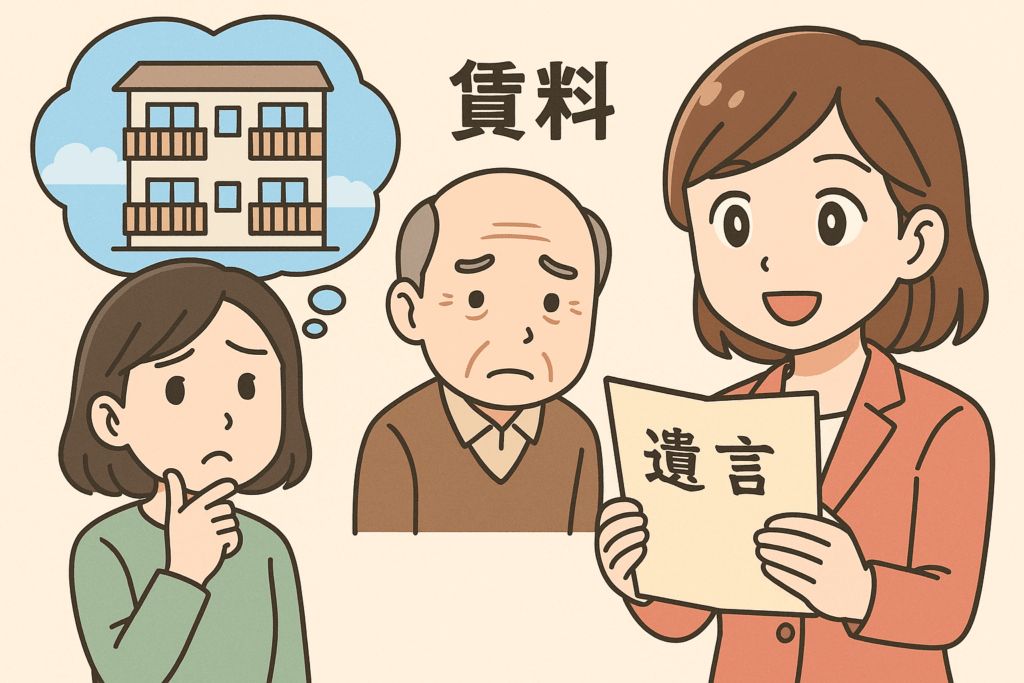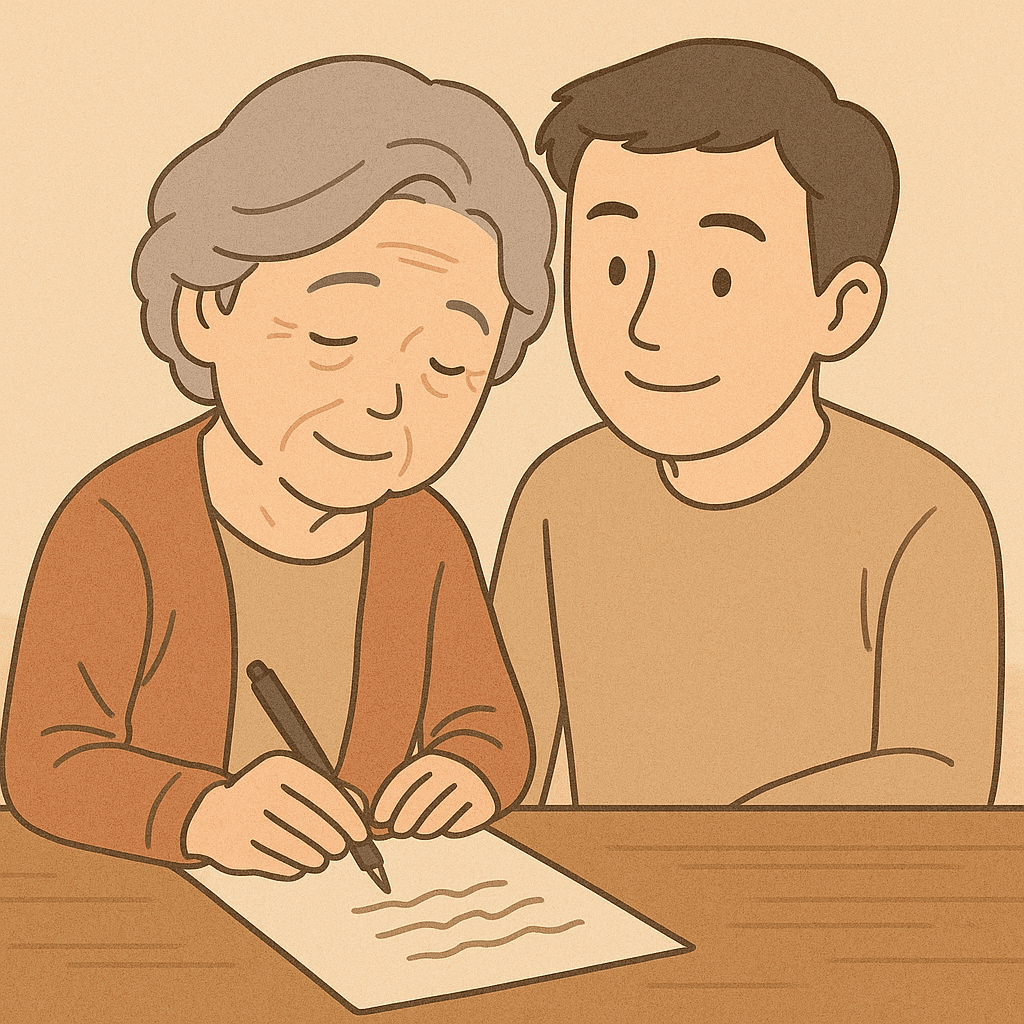文京区湯島の司法書士栗栖英俊です。
以前、どのような種類の遺言書があるかについて、軽く記事を書かせていただきました。
https://kurisu-office.com/2025/03/5209/
今回は遺言書を作成するメリットについてお伝えしたいと思います。
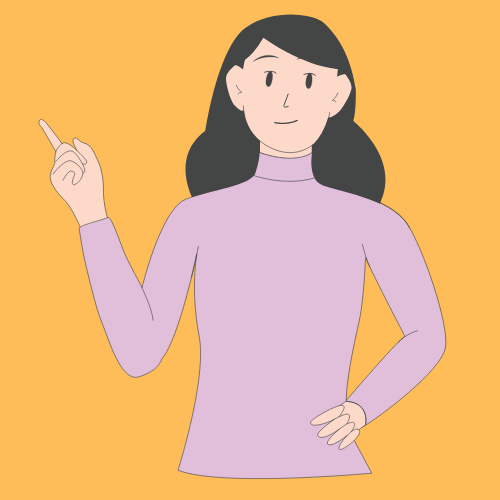
財産が少なければ揉めないは本当か?
「遺言書なんてお金持ちが作るものでしょ?」
「うちは大した財産がないから、家族で話し合えば大丈夫」
こう思っている人は意外と多いですが、これは大きな誤解です。
令和3年 司法統計年報(家事編)を見ると、遺産分割事件の総数6,934件のうち、金額が1,000万円以下のものは2,279件(約33%)、金額が1,000万円より多くて5,000万円以下のものは3,037件(約44%)あります。
一方で、金額が5,000万円より多くて1億円以下の場合は864件(約12%)しかありません。
データの上では「金持ち喧嘩せず」というのは、ある程度当たっていることになります。
このことからすると、世間の大勢の方がお持ちの「うちはそれほど資産がないから遺言書を作成する必要がない」という考えは間違っていることがわかります。
さらに、「そもそも何が遺産に含まれるの?」という疑問を持つ人も多いでしょう。
そこで今回は、遺言書を作成するメリットとともに、遺産(相続財産)に含まれるもの・含まれないものについても解説します。
そもそも「遺産(相続財産)」とは?
遺産とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産のうち、相続の対象となるものを指します。ただし、すべての財産が相続できるわけではなく、相続人に引き継がれるものと、そうでないものがあります。
遺産に含まれるもの(相続できる財産)
以下のものは、基本的に相続財産として遺産に含まれます。
① 金融資産(お金・証券類)
- 預貯金(銀行・信用金庫・ゆうちょなど)
- 株式・投資信託
- 貸付金(人に貸していたお金)
② 不動産
- 自宅や別荘、土地、マンション
- 借地権(他人の土地を借りている権利)
※不動産は評価額の算定が難しく、兄弟間で「もっと高く売れるはず」「安く見積もられた」などのトラブルになりやすいです。
③ 動産(価値のある物品)
- 車、貴金属、骨董品、美術品
- 高価な家具・ブランド品
※特に価値のある美術品や骨董品は、相続時に売却するかどうかで意見が割れることがあるので注意が必要です。
④ 事業関係の財産
- 自営業者の事業用資産(店舗・工場・営業権など)
- 会社の株式(家族経営の企業など)
※後継者がいる場合、遺言書で「誰に事業を引き継がせるか」を明確にすることが重要になります。
⑤ 負債(マイナスの財産)
- 住宅ローン
- 借金・カードローン
- 未払いの税金・医療費
※相続する際は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継ぐ可能性があるので注意が必要です。
この場合、相続放棄を検討することもできます。

❌ 遺産に含まれないもの(相続できない財産)
相続の対象にならないものもあるため、注意が必要です。
① 生命保険の死亡保険金
→ 生命保険の受取人が指定されている場合、その人が受け取るものなので相続財産には含まれません。
※ただし、受取人が「亡くなった人本人」になっている場合は相続財産になるので要注意です。
② 年金
→ 亡くなった人が受け取る予定だった年金は相続の対象外。ただし、未支給の年金(亡くなる前の分)は遺族が請求できることもあります。
③ 祭祀(さいし)財産(お墓や仏壇)
→ お墓・仏壇・位牌などは、一般的な相続財産とは異なり、「祭祀承継者」として特定の人が引き継ぐ。兄弟で分けるものではありません。
④ 亡くなった人の個人的な権利や義務
→ たとえば、以下のようなものは相続の対象になりません。
- 年金受給権
- 労災保険の給付金
- 契約上の地位(借家の賃貸借契約など)
遺産の額が少なくても揉める理由
「うちは大した財産がないから問題ない」と考えている人は多いですが、むしろ遺産が少ないほうがトラブルになりやすいのが現実です。
① 遺産が少ないほど「分けにくい」
例えば、遺産が1億円あれば、相続人が3人いても、それぞれに3,000万円程度ずつ分配できます。しかし、遺産が500万円しかなかった場合、どう分けるかで意見が割れやすくなります。
人間というものは、もらうお金が多ければ「少しくらいはあげてもいいか」と思いますが、もらう金額が小さくなった場合は「少しでも多くほしい」と思うものだということです。
特に、「不動産」が絡むと、さらにトラブルが発生しやすいです。
② 介護・支援の有無で不満が出やすい
- 「自分は親の面倒を見てきたのに、兄弟と同じ額なんて納得できない!」
- 「疎遠だった兄弟が急に相続を主張してきた!」
こうした感情的な対立が、遺産の少ない家庭ほど深刻になりがちです。
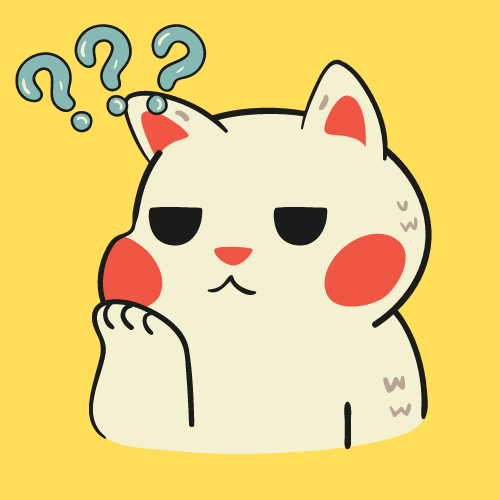
遺言書を作成するメリット
✅ 「誰に何を渡すか」を明確にできる
→ 遺産を巡るトラブルを未然に防ぐことができます。
✅ 介護や貢献に報いることができる
→ 「長年世話をしてくれた人に多めに渡す」などが可能になります。
✅ 手続きをスムーズに進められる
→ 遺言書がないと、相続人全員の合意が必要になり、時間がかかる場合があります。
✅ 相続税対策にもなる
→ 遺言書を活用すれば、節税対策が容易になります。
まとめ
遺言書を作成することは、「財産の多い・少ない」に関係なく重要です。特に、以下のようなケースでは、遺言書を残しておくことを強くおすすめします。
✔️ 不動産を持っている(自宅や土地)
✔️ 子どもが複数いる
✔️ 家族関係が複雑(離婚・再婚など)
✔️ 介護をしてくれた子どもがいる
✔️ 事業をしている
「うちは大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると、思わぬトラブルが起こることがあります。大切な家族のためにも、早めに遺言書を作成し、「争族」ではなく「円満相続」を実現しましょう!
113-0034
東京都文京区湯島4丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
【営業時間】 9:00~17:00
【電話番号】
03-3815-7828
【FAX番号】
03-3815-7986
当事務所は予約制です。いきなり事務所にご来所いただいても、対応できない場合があります。
事前にメールまたはお電話でのご予約をお願いいたします。