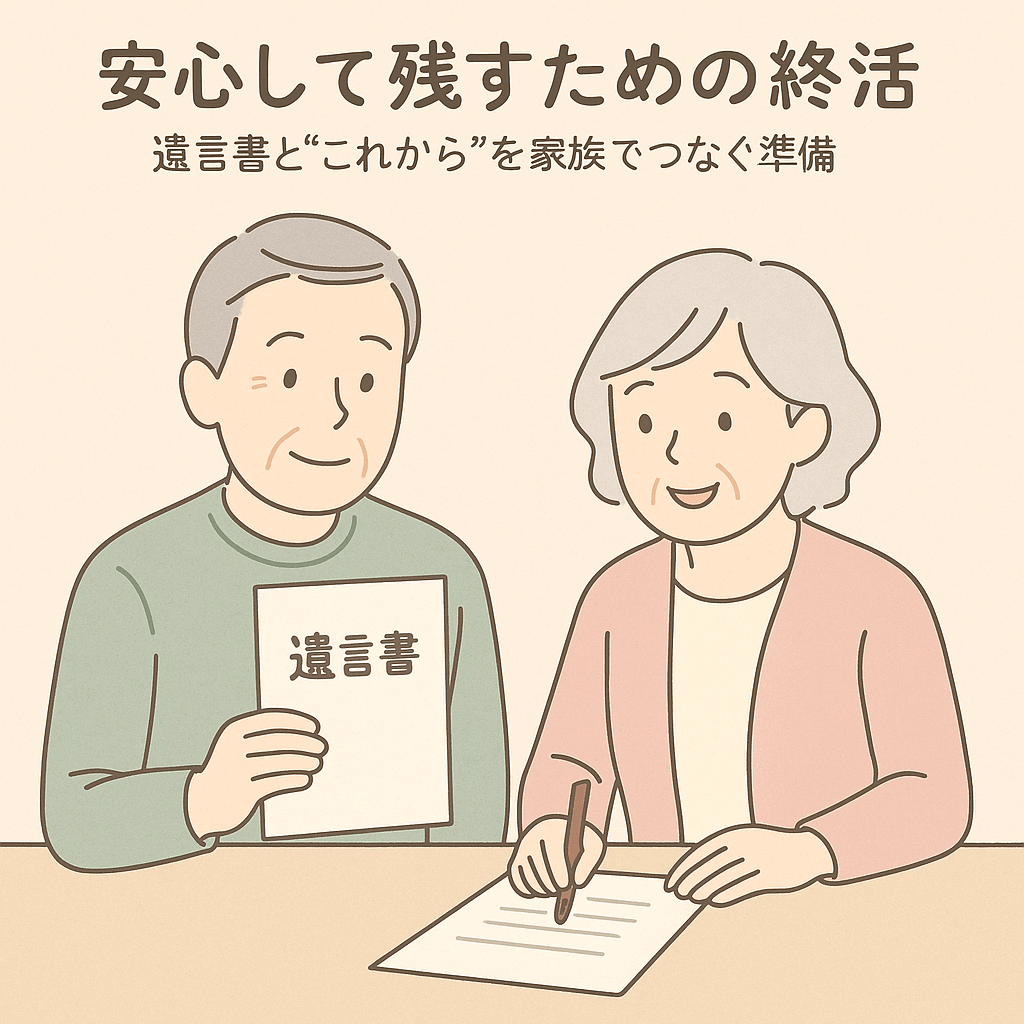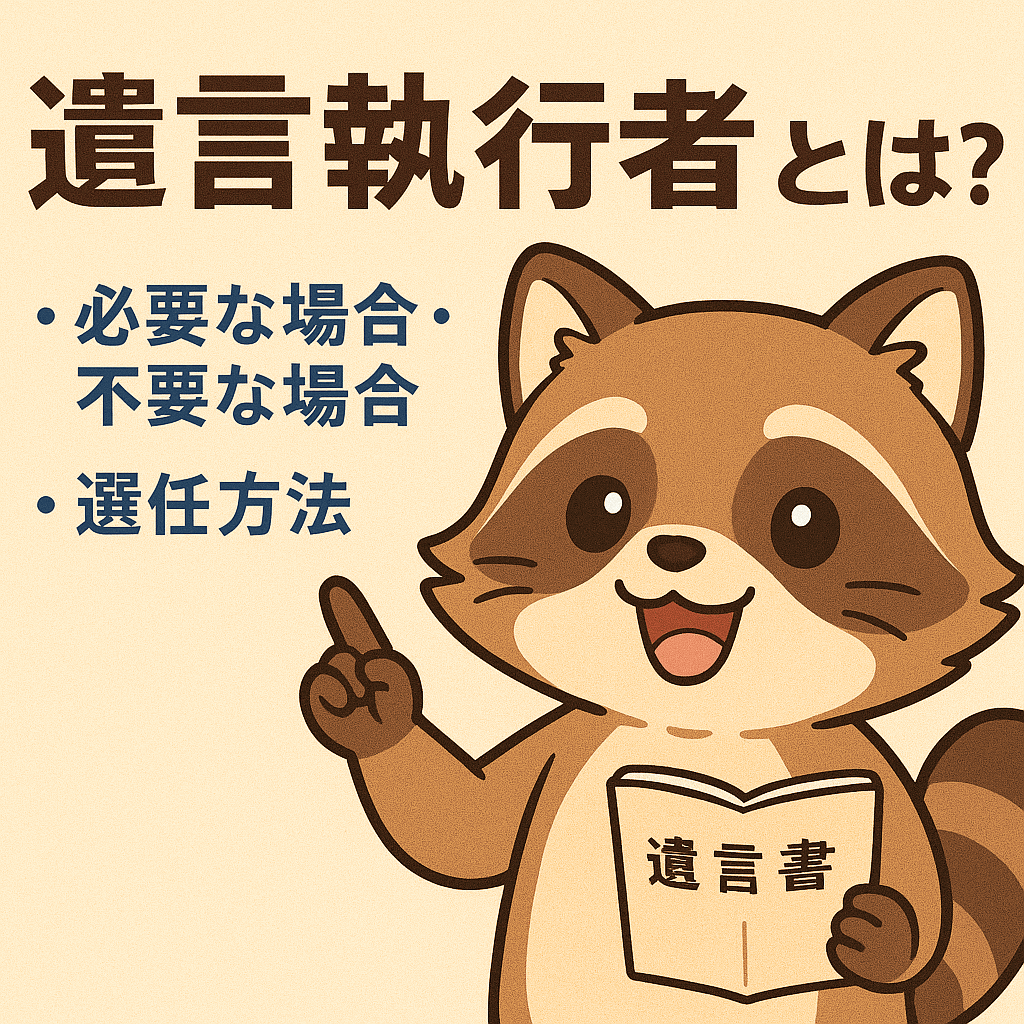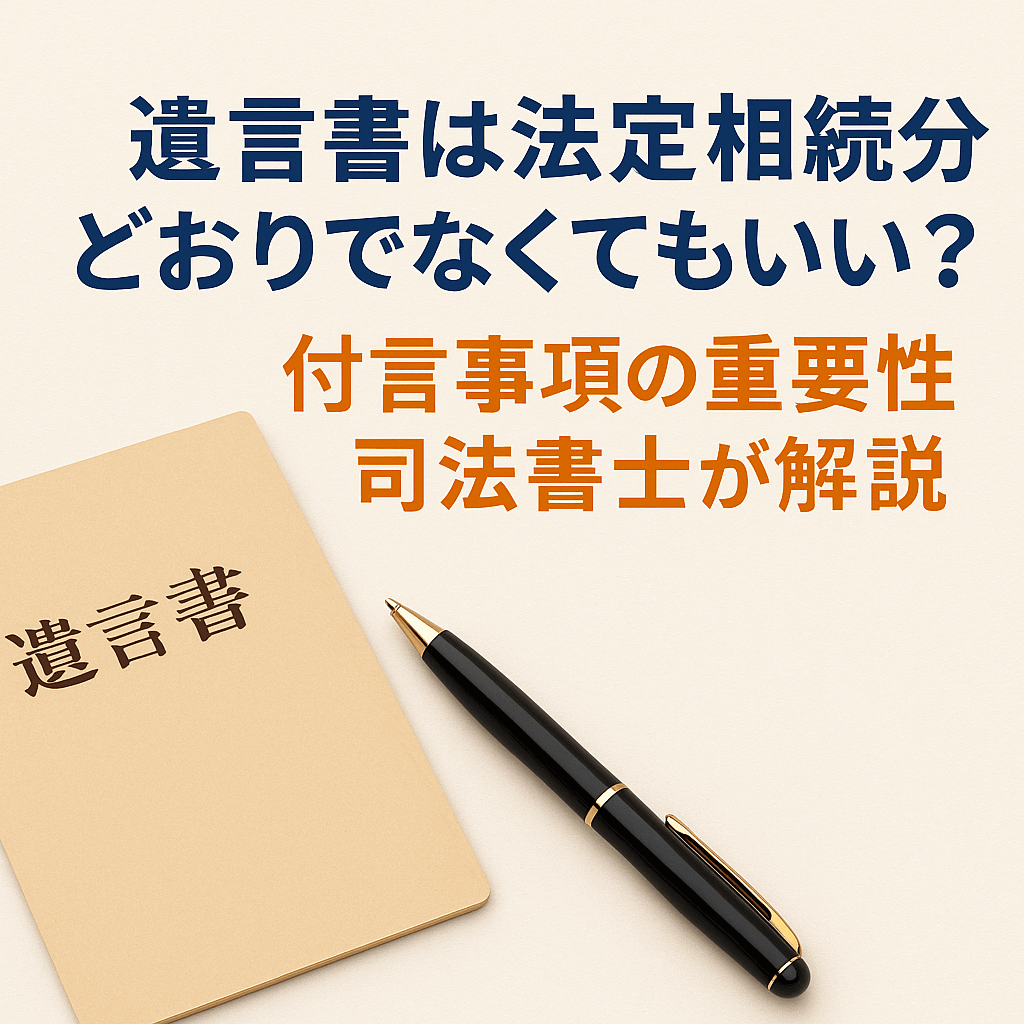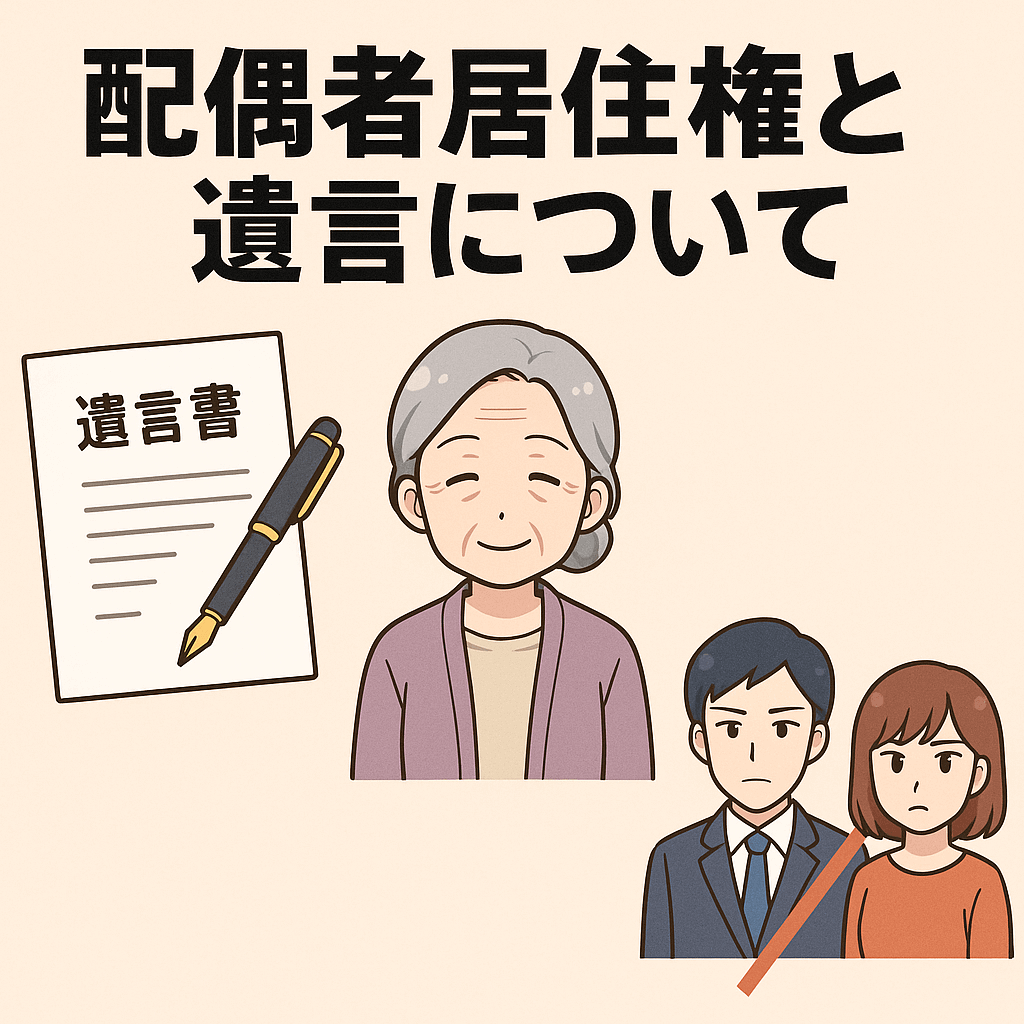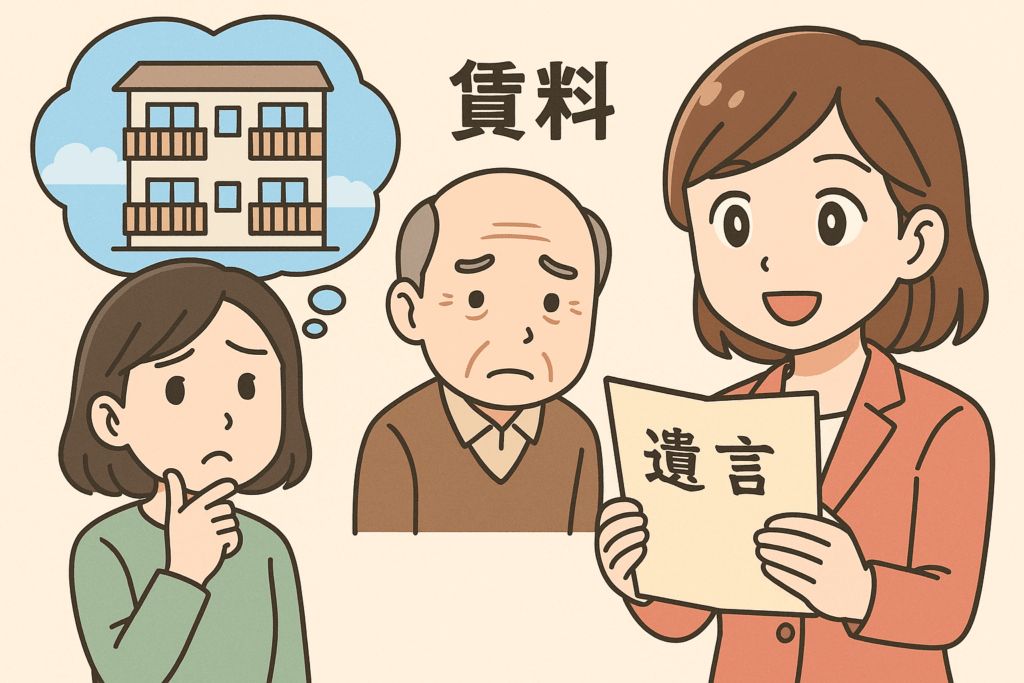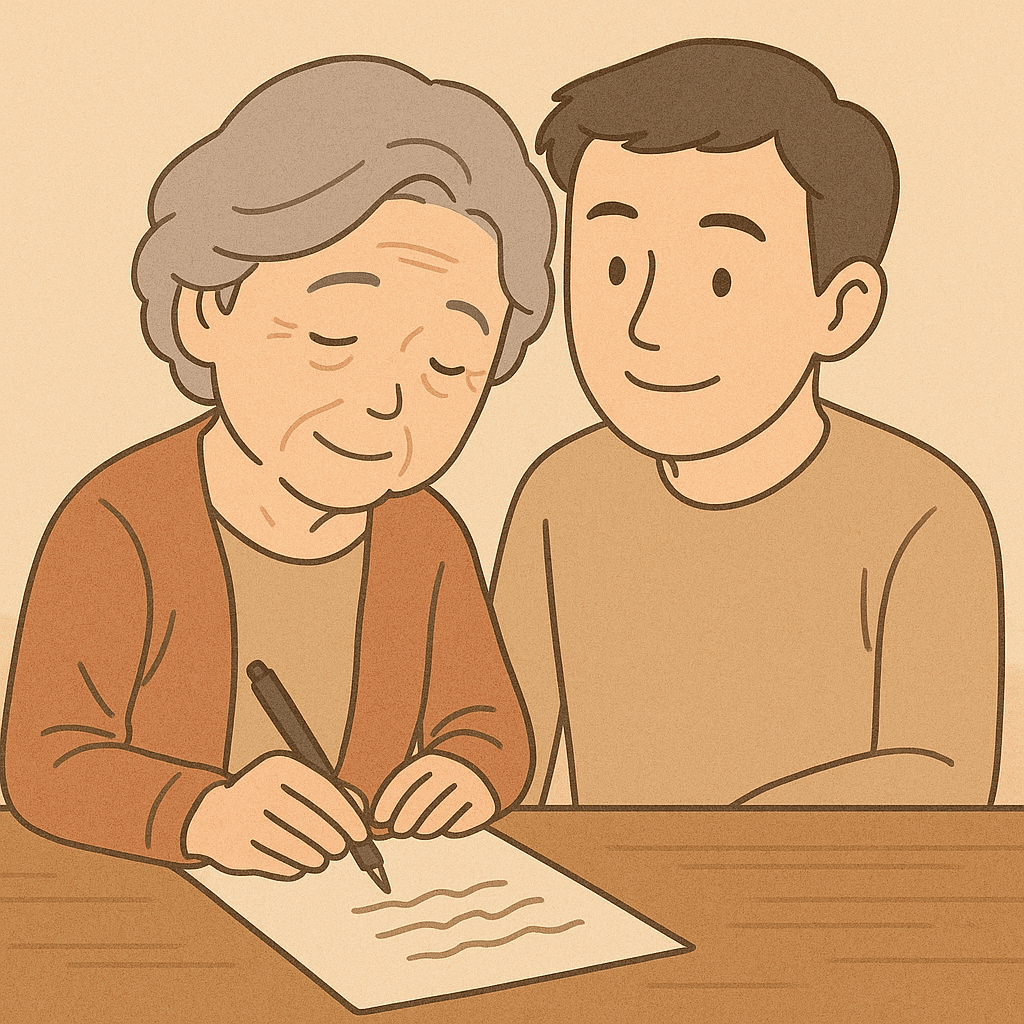人生の最終章において、ご自身の「想い」を正しく伝え、家族に負担をかけないためには、遺言書の作成が非常に大切です。
特に、お墓や仏壇などの祭祀財産の承継や葬儀の希望の伝達については、適切な準備が必要です。
文京区湯島にある当司法書士事務所では、東京都23区を中心に、千葉県・埼玉県・神奈川県の一部地域に対応しております。
この記事では、祭祀承継・葬儀の遺言書への記載方法と具体的な手続き方法をわかりやすく解説します。

祭祀財産とは?
「祭祀財産」とは、先祖供養のために用いられる財産で、相続財産とは区別され、特定の1名が単独で承継するものです。
民法897条は、祭祀財産,すなわち,祭祀を営むために必要な「系譜,祭具及び墳墓の所有権」は,相続財産に属せず,祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとしています。
第897条
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
次に用語の説明をしたいと思います。
まず、系譜とは,家系図・過去帳など先祖代々からの家系を書き記した文書や図書のことを指します。
次に、祭具とは,神棚,位牌,仏壇など祖先や親族等の祭祀を行うために用いる用具のことを指します。
最後に、墳墓とは,土葬の場合の遺体や火葬の場合の遺骨を葬る目的で設けられた墓石,墓碑,埋棺,霊屋などの設備などをいいますが、その維持のために必要とする土地の所有権や墓地使用権もこれに含まれるか、墳墓に準ずるものとして含まれるとするのが一般的のようです。
これらの財産は金銭的な価値よりも「供養の継続性」が重視されるため、遺産分割の対象にはなりません。
この点については注意が必要です。
祭祀承継者の指定について
法律上、祭祀財産は「祭祀を主宰すべき者」が単独で承継します。以下の順序で決定されます:
- 被相続人が指定した者
- 慣習により定まった者
- 家庭裁判所が指定した者
遺言で指定する際の注意点:
遺言によって明確に「祭祀承継者(祭祀主宰者)」を指定することは有効ですが、指定された人には法的義務はなく、承継を拒否することも可能です。
そのため、遺言書を作成する前に候補者本人と話し合い、意思確認を行うことが極めて重要です。
さらに、承継者は供養の方法や頻度などを自由に決定する裁量を持っており、遺言者の希望が必ずしも実現されるとは限らない点にも注意が必要です。
遺言書での祭祀承継者の記載例
第〇条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男中村守(昭和35年1月7日生)を指定する。
遺言者は、長男守に〇〇霊園にある墓地、系譜、祭具などの祭祀用財産を承継させる。
2長男中村守が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男の子中村晃(平成3年7月1日生)を指定する
この遺言書で重要なのが、2項の予備的遺言の部分です。
祭祀承継者を指定しても、遺言書作成から遺言者が死亡するまでに、相当の期間が経過する場合があります。
その場合に、祭祀承継者が遺言者より先に死亡する場合もあることから、次の順位のものを予備的に指定するということが、遺言者の意思を実現するためにも必要となります。

葬儀について遺言で指定する意味と限界
葬儀の方法(宗派・規模・場所など)を遺言に記すことで、家族の混乱やトラブルを防ぐことができます。
ただし、遺言による葬儀の希望は法的拘束力がなく、実際にどのような葬儀を行うかは家族や祭祀承継者の判断に委ねられます。
このため、「誰に任せるか」が非常に重要です。
さらに、遺言以外の手段を活用することで、希望の実現性が高まります。

葬儀の希望を実現する3つの方法
1. 死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)
信頼できる人と公正証書によって契約を結び、死後の事務(葬儀・納骨・役所手続きなど)を委任します。
法的な効力を持ち、実務上非常に有効です。
死後事務委任契約
(中略)
第〇条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務を委任する。
(省略)
(2)葬儀及び埋葬に関する事務葬儀は、遺言者の信仰する〇〇宗〇〇派の儀礼、方式に従って執り行い、遺言者の遺骨は、〇〇寺にある先祖代々の墓に納骨する。
(省略)
2. 負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
財産を譲る代わりに、葬儀の実施を条件とする遺言です。以下のように記載されます
第〇条 遺言者(山本太郎)は、遺言者の所有する次の預金債権を、田中朋子(平成2年8月9日生)に遺贈する。
〇〇銀行△△視点 普通預金 口座番号 ○○○○○〇〇
2 田中朋子は、前項の遺贈の負担として、負担として、遺言者の葬儀・埋葬を以下のとおり実施しなければならない。
(1) 遺言者の葬儀は、遺言者の信仰する〇〇宗〇〇派の儀礼、方式に従って執り行う。
(2) 遺言者の遺骨は、〇〇宗が〇〇において設営する〇〇墓地に納骨すること。
(省略)
3. 付言事項で希望を伝える
遺言書の「付言事項」に希望を記すことで、家族に思いを伝えることができます(例:「家族のみで静かに見送ってほしい」など)。
(付言)
1遺言者の葬儀は、遺言者の信仰する〇〇宗〇〇派の儀礼、方式に従って執り行ってください。
2遺言者の遺骨は、〇〇寺にある山田家代々の墓に埋葬してください。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 指定された祭祀承継者が辞退したらどうなりますか?
A. 他の親族や家庭裁判所が承継者を指定することになります。
Q2. 葬儀の宗派を指定できますか?
A. はい、付言事項や契約で指定できますが、実行の保証はありません。
Q3. 仏壇などを複数人で分けることはできますか?
A. 基本的には1人にまとめて承継されます。分割は推奨されません。

専門家に相談することの大切さ
祭祀承継や葬儀に関する希望は、法律・慣習・家族の状況など、複雑な要素が絡みます。自己判断で書いた遺言書では、希望が実現されない可能性もあるため、専門家の助言を受けることが重要です。
当事務所では、司法書士が親身になってご相談を承り、最適な形で遺言書をサポートいたします。
113-0034
東京都文京区湯島4丁目6番12号B1503
栗栖司法書士行政書士事務所
【営業時間】 9:00~17:00
【電話番号】
03-3815-7828
【FAX番号】
03-3815-7986
当事務所は予約制です。いきなり事務所にご来所いただいても、対応できない場合があります。
事前にメールまたはお電話でのご予約をお願いいたします。